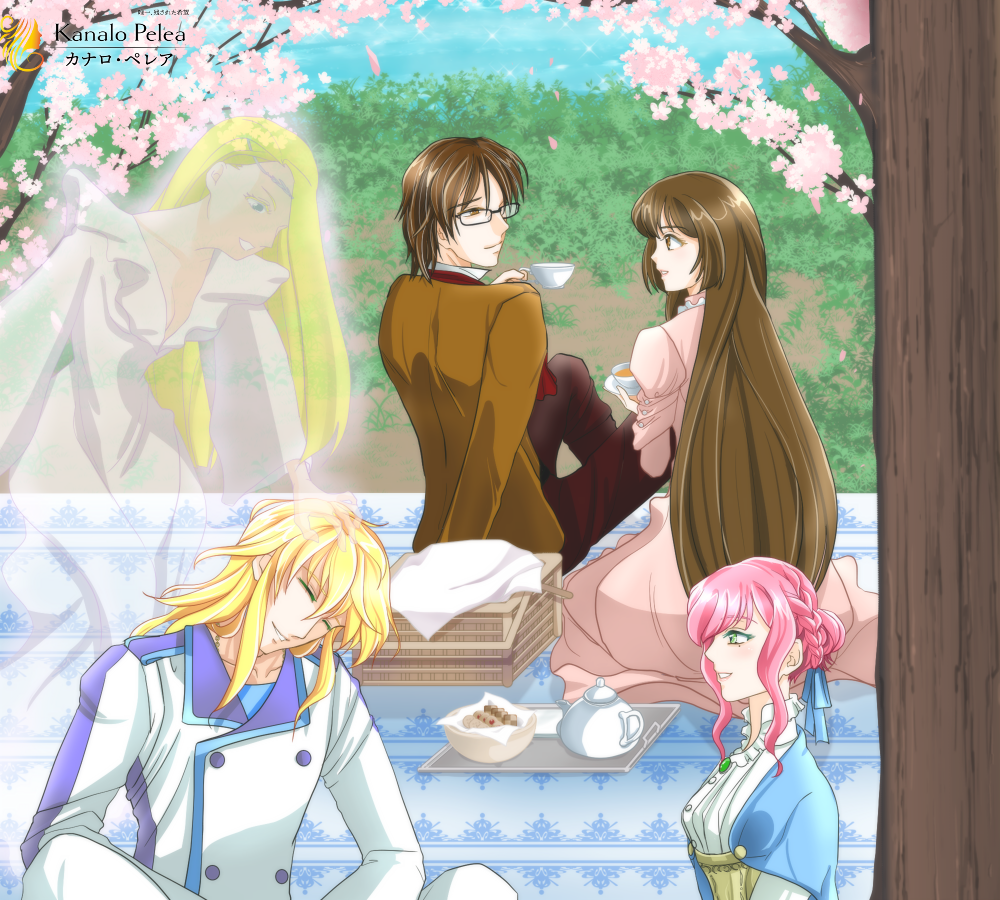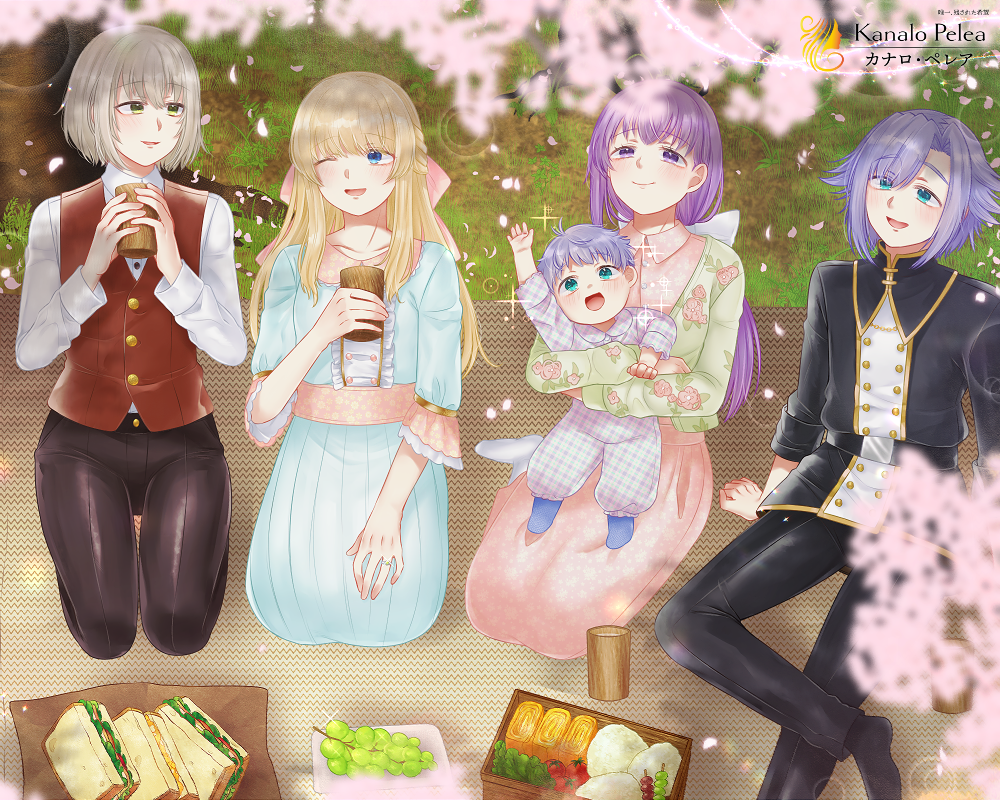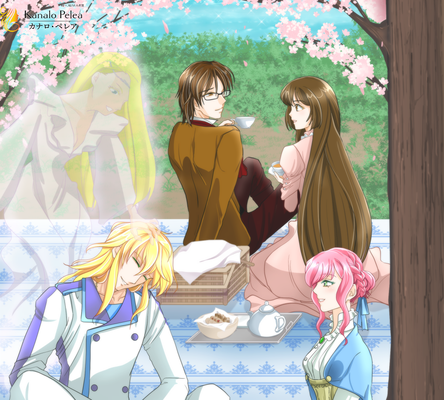全ての魔力を統べる王となった、ランガス・ドムドールが護る園。
美しい花が咲き誇る島に、人々が集っていく。
如何なる人を害する魔法も発動出来ないこの地に、人間と神の使い、そして精霊たち――多くの笑顔の花も咲き始める。
オアシス島に箱船が到着してすぐのこと。
「今日は待ちに待った日ですね、バートさん」
夫、バート・カスタルに手を差し出して、ピア・カスタル(ピア・グレイアム)は微笑んだ。
「ああ」
返事をして、バートは眩しそうに空を見上げた。
それからピアの手を取って歩き出す。
「花キレー、キレー、キレー!」
「走ったらダメですよ!」
ピアの反対の手は、息子、リィト・カスタルと繋がれていた。
茶色の髪に、青い瞳。バート似で元気いっぱいな男の子だ。
「悪いな、リィト。遊ぶ前に叔父さんに会いに行こうな」
バートがそう言うと、リィトはうんと強く頷いた。
「きっと、来ていますよね」
ピアは桜が立ち並んでいる方向へと目を向ける。
リィトにとっての叔父――バートの弟は、きっとここに来ている。
「兄ちゃん!!」
歩きはじめた途端。
海岸にいた青年が大声をあげて駆けてきた。
「バ、バリか……?」
驚くバートの手を離し、ピアは彼の背を押してあげた。
「うん」
青年、バートの弟のバリ・カスタルがバードに飛びついてくる。
「お、お前でかくなりすぎ。誰だかわからなかったぞ」
「兄ちゃんは変わってない……。いや、少し、小さくなったかな」
バートに抱き着きながら、バリは声を詰まらせ、涙を浮かべながら笑う。
「同じくらいだな……。なんか、若いころの自分と会ってるみたいだ」
バートは強くバリを抱きしめた後、身体を起こしてハンカチを取り出し、バリの涙を拭いた。
「やめろよ、余計泣ける」
それはバリがバートに贈ったハンカチ。結婚してからもずっと、バートはこのハンカチを身に着けていた。
「寂しい思いさせて、悪かったな」
「……うん。早く行こうぜ。兄ちゃんを待ってる人、沢山いるんだ!」
そして、バリは兄の手を引いて、皆が集まる場所へと引っ張っていく。
「おじちゃん?」
「お父さんの弟さんですよ」
不思議そうに言うリィトの手を引いて、ピアはバートとバリの後に続いた。
「ははうえは、ふだんおすがたをおみせにならないのです」
ふわふわの金髪の男の子が、母親に肩車をしてもらい、はしゃいでいる。
「はしゃぎすぎて落ちるなよ」
母、リンダ・キューブリックの顔は、普段通りの仏頂面……いや心なしか微妙に緩んでいるようにも見える。
息子、チェーザレ・アジャーニとは離れて暮らしており、共に過ごすのは久しぶりであった。
チェーザレの父は、エクトル・アジャーニ。リンダは彼と結婚して、一度はアジャーニ家に入った。
しかしアジャーニ家での生活にどうしても馴染めず、現在はエクトルと別居状態。息子はアジャーニ家で育てられている。
「おはなおはなおはなー。ははうえのあたまにおはなーですー」
燃えるようなライオンヘアを、わしゃわしゃかきまわして、花びらを絡めていく。
「危ないぞ」
チェーザレを見ていると、亡きコルネリア・クレメンティを思い出すことがある。どことなく似ているところがあった。今日は彼女の弟で弟子の、バルダッサーレ・クレメンティを伴って訪れたのだが、共にいると彼の子だと間違えられることさえある。気をきかせてか、バルダッサーレは今は騎士仲間と花見を楽しんでいた。
エクトルの方は、リンダに息子を任せて、挨拶に訪れた貴族やマテオの民となにやら難しい話をしているようだ。
何の柵もなく、愛する息子と過ごす至福の時間だった。
「こんにちは、リンダさん。今日は息子さんと一緒なんですね」
声をかけてきたのは、アレクセイ・ハルベルト(アレクセイ・アイヒマン)。息子のヴァレリー・ハルベルトを抱きかかえている。
「そうだ……です。チェーザレ、挨拶」
アジャーニ家は当主のエクトルが継承者の一族となり、更に彼の功績により爵位が上がったのだが、それでも皇家の血を引くハルベルト公爵家よりは格下だった。
「こんにちは~! ははうえのりんだ、あじゃーにでーす」
「こら、母を紹介しろとは言っていない」
それに今は、キューブリックを名乗っている。と、続けようかと思ったが、やめておいた。
「ふふふ、かわいいですね」
アレクセイの言葉に、リンダは思わず首を大きく縦に振っていた。
「ヴァレリーも挨拶できるかな?」
アレクセイはヴァレリーを抱き直して屈み、チェーザレの方に向けた。
「こんいちわ」
喋れるようになったばかりのヴァレリーの口から、可愛らしい声が発せられた。そしてすぐに、ヴァレリーはアレクセイにぎゅっと抱き着く。
「人見知りが激しくて。チェーザレくん、仲良くしてあげてね」
「うん、いいよー。あそんであげる」
言って、チェーザレはヴァレリーに手を伸ばした。二人の手が触れ合った途端。
パチッと小さな衝撃が二人の手に走った。
「ふ、ぎゃーーーっ」
ヴァレリーは泣きだし、チェーザレは自分の手をさすりながら、母を見上げた。
「ははうえ、いたい、いたいです」
「大丈夫だ、泣くなよ」
リンダはチェーザレの小さな手を確かめるが、怪我などはしていない。
衝撃は一瞬だけであり、びっくりして泣いただけのヴァレリーもすぐに泣きやんだ。
「異なる継承者の一族同士だからですよ」
そう声をかけてきたのは、サーナ・シフレアンだった。
ウォテュラ王国の王家の血を引いており、水の継承者の一族でありつづけた女性。傍らには、ラトヴィッジ・シフレアン(ラトヴィッジ・オールウィン)がおり、彼もまた小さな子供を抱えていた。
サーナとラトヴィッジは帝国に訪れた後、結婚をしており、娘が一人、生まれていた。痣を持つ子である。
「いつも起きる現象ではないのですが、初めて触れた時や、久しぶりに触れた時に発生しやすいんです」
「うちのお姫様とも発生すると思うけど、仲良くしてくれるか?」
ラトヴィッジはチェーザレににっこりと笑顔を向けて、娘のリーゼロッテを下ろした。
「ほら、挨拶してみな?」
「こんにちは。よろしくおねあいいた、ます」
リーゼロッテはぺこっと頭を下げる。
「こんにちはー! よろしく~」
チェーザレはそろっと手を伸ばして、リーゼロッテに触れると、パチッと衝撃が走る。
続いてリーゼロッテの方からチェーザレに触れるけれど、衝撃は起きない。
二人はケラケラ笑い合いながら、触り合いっこを始めた。
「ヴァレリーも怖がってちゃだめだよ。将来、ずっと長い間、助け合っていく大事な大事なお友たちなんだよ」
アレクセイもヴァレリーを下ろして、二人の方へと促す。
そうしてピンク色の花びらが舞い踊る中、子どもたちは触り合いっこをして笑い合う。
両親たちはそれぞれの子ども自慢で、話に花を咲かせていく。
お昼が近くなり、シートが敷かれた場所へと、皆が集まっていった。
「ごきげんよう、サーナ」
サーナ達家族に、マーガレット・ヘイルシャムが近づく。
「こんにちは。ご一緒してもいいですか?」
マーガレットの後ろからビル・ドムドール(ビル・サマランチ)が顔を出す。
「もちろんです。それにしても、こんなところに……いえ、あの……」
ビルは、次期皇帝候補の皇女である。護衛もつけずに来ていることに少し驚いてしまった。
「大丈夫です。ここは彼女の御父上、王に護られた島ですから。リーゼロッテさんもこんにちは」
マーガレットはラトヴィッジに抱きかかえられているリーゼロッテにも微笑みかける。
「こんにちはー」
「ふふ、相変わらず仲がよろしいのですね。なによりですわ」
サーナとラトヴィッジの繋がれた手を見て、マーガレットが微笑む。
「そりゃもう。幸せ過ぎて」
娘の身体と妻のサーナの手をぎゅっとしながら、ラトヴィッジは締まりのない笑みを浮かべる。
「マーガレットさんもマテオにいたころより、ずっと健康になられてよかったです」
「あの頃よりはですけれどね」
もう長くないと言われていたのに、無理をせざるを得なかったあの頃より、本当にずいぶんと健康になった。とはいえ、病弱な体質が変わったわけではなく、次に体調を崩した時、また今ほどに回復するかどうかは、わからない。
手がけていた回顧録は、帝国に関する部分も完成した。それで暇が出来たかといえば、そうではなく。ビルの個人教師をしたり、サーナを手伝ったり……合間に、小説をこっそり書いたりと、マーガレットはそれなりに忙しい日々を送っていた。
「友人の友人は友人。できれば二人にもお友達になってもらいたいのです」
マーガレットはビルとサーナを見ながら言う。
「どちらもなかなか波乱に満ちた少女時代を過ごしたという共通点もありますし、きっといい友人になれると思うのです。いつか、私がいなくなっても……っと」
最後の言葉は口にするつもりのなかった気持ちだ。
「先生、私の結婚式に出席してくださる約束ですよね」
「リーゼロッテの結婚式にも出るって言ってたわ」
「私の子どもを抱っこしてくださるとも」
「私の孫が見たいとも」
言った覚えのない言葉が、ビルとサーナの口から楽しげに語られていく。
「随分と長生きしなければならなそうです」
マーガレットとサーナとビルは笑い合い、つられてリーゼロッテも可愛らしい笑い声をあげた。
そんな女性たちの姿を笑顔で見ていたラトヴィッジの目に、長身の男性の姿が映った。
「バートさん!!」
懐かしい先輩の姿を見つけて、ラトヴィッジは走り寄る。
「おお、ラトか!」
サーナとマーガレットも後に続いた。
「バート、元気そうでよかった」
「お久しぶりです、バート。ご兄弟と会えたのですね」
「ああ。こいつ、弟のバリ」
嬉しそうにバリの腕を引っ張って、皆の前に出すバート。
「初めまして、バリ・カスタルです……って、兄ちゃん、サーナもマーガレットさんも、俺よく知ってるって!」
「はははっ。で、妻と息子。俺の大事な家族」
バートは後方で見守っているピアとリィトの方に手を向けて、紹介をした。
「俺達も結婚したんだ。娘、サーナに似て超可愛いだろ~?」
緩みまくった顔で、ラトヴィッジはバートにリーゼロッテを紹介する。
「かっわいいなー。お父さん優しいか?」
「うん! だいしゅき」
「うっおおおおお、とうさんも、リーゼロッテとサーナが大好きだー」
娘をむぎゅーっと抱きしめるラトヴィッジの姿に、笑い声と笑みが溢れた。
「先ほどの方は?」
戻ってきたマーガレットに、ビルが尋ねた。
「バート・カスタル。私の大切な友人です」
バートはコーンウォリス公国の騎士だ。多分現在ではそれなりの立場になっているだろう。
(友人の友人は友人……そんな風になれたらいいですね)
ビルを見ながら、マーガレットは密かに思う。
「ところでビルさん、その、お召し物もとてもお似合いですわ」
「そうですか! これ、妹のダリアが選んでくれたんです」
「ああ、どうりでずいぶんとセンスのあるチョイスをされたなと思っておりました」
ビルは嬉しそうにこくりと頷く。
ビルの服装は、柄のないふんわりとしたワンピースだった。
満開の桜の中にいる彼女は、まるで妖精のように可愛らしい。
「でも、もう四年も経ったのですね」
シートの上に腰を下ろして、のんびりと桜を眺めていく。
「ビルさんの個人教師を始めた頃は、皇帝候補に、異国の女がよからぬことを吹き込んでいるとかも言われましたけど……」
「そうなのですか?」
「そういえば、サーナの家庭教師を始めた頃も、神殿の人から同じようなことを言われましたね」
「え? そんなことが?」
マーガレットの言葉に、ビルとサーナが同じ反応を示した。
「マーガレットさんの本質を見抜いていたのかもしれませんね」
「それはどういう意味ですか、サーナ」
「あいえ、本質というか本職? 家庭教師就任前の主な収入源のことです」
「執筆関係ですよね? 先生、どのようなお話を書かれているのですか?」
純粋無垢な目でビルが尋ねてくる。
皇帝候補の本棚に並んでいたら家臣が卒倒しそうな本である。
「まあそんなことも、最近はあまり言われなくなりましたね」
意味ありげな顔で、マーガレットはそう誤魔化して。
「少しは信用されたのか、単に諦めただけかもしれませんけどね」
と、サーナと笑い合った。
バートのもとに、彼と親しくしていた者達が集まっていた。
「バートさん、ちょっとだけいい?」
声をかけてきたのは、ナイト・ゲイル。バートの部下だった青年だ。
「ん……ああ、ナイトか。お前帝国の騎士になったんだって!?」
「そう。俺が護りたいのは、全てだから。それで、世界を護る活動で、世話になってる人」
ナイトの後ろから姿を現したのは、チェリア・ハルベルトだった。
「紹介しろって言われてさ」
「アルディナ帝国、近衛騎士のチェリア・ハルベルトです」
その自己紹介に、バートの顔に軽く緊張が走った。
すぐに立ち上がり、右手を差し出す。
「公国騎士、バート・カスタルだ。民救出のための支援、深く感謝している」
「残った全ての人命が一つ残らず救われるよう、私も祈っています」
握手を交わした後、チェリアはナイトに目を向けた。
「それじゃ、見回りよろしくな」
ぽんとナイトの肩を叩き、チェリアは家族のもとに向かっていった。
「……なんか凄くオーラを感じる人だったけど、何者だ?」
「継承者の一族同士で、騎士仲間? あ、公爵家の長女で跡を継ぐとか言ってたな」
「お前とじゃ、身分が違いすぎないか?」
ナイトは公国の貴族でさえなかった。帝国の騎士として認められたとはいえ、下級貴族にでさえなったわけではないだろう。
「そうか? そういうの感じないけど。バートさん、俺にはパートナーが必要だって言ってたろ」
「ん……ああ、魔術に優れた奴がな」
「それと同じようなこと彼女に言われたことがあってさ。その話をしたら、気が合うかもしれないから、挨拶しておきたいって言われて……まあ、チェリアのことはいいだろ。バートさんは人間になったんだろ、身体の調子はどう?」
「それがさ、魔力を失ってから身体がまともに動くようになってさ、今最高に調子がいい」
魔力を持たない純粋な人間になってから、バートの身体は急回復し、既に体力は完全に元に戻った。
「それとレイザの祖父さん……アゼム・インダーさんの精神も回復したぞ。まだ会ってないのなら、会って話をしてみるといい」
「そうか……そうだな」
水も地も風も、元々一族だったもので、新たな王の――神の使いとなった者がいるが、火はいない。
共に魔術の訓練をしているルルナ・ケイジを連れて、いつか訪ねてみようと思うのだった。
「よう、バート」
軽快な声が響いた――。
声の主を見たバートの目が見ひらかれる。
「ラルバ!!」
体当たりするかのようにその人物に飛びついて、肩を組んで家族のもとに引っ張ってくる。
「ピア、こいつ俺の幼馴染で、大親友のラルバ・ケイジ! ナイトにも話したことあるよな!?」
「あ……ルルナの兄貴?」
バートから聞いたことがあったかどうかは忘れたが、ルルナからは聞いている。
長身で筋肉質、かなりの使い手に見える男性だった。
「そう。ルルナから君のこと、聞いてるよ。ルルナの面倒を見てくれてありがとな」
「いや、ルルナとは教え合っている仲だから、こちらこそ世話になってます」
「バリが世話になったな、コノヤロウ!」
バートが笑いながらラルバの腹を拳で殴る。
「あーその件に関しては、あとで話がある。フフフ」
「ん? 何かあったのか?」
バートがバリに目を向けると、バリはあからさまに目を逸らして、リィトに近づいた。
「お兄ちゃんと遊ぼうなー。肩車してやろか」
「バリはおにいちゃんじゃなくて、おじちゃんでしょ!」
「う……っ、うん、いいよおじちゃんで! もう俺、子どもじゃないから」
言って、バリはリィトを両手でつかんで、高く高くあげた。
リィトが楽しそうに笑い声をあげる。
「ふふっ」
夫も息子もとても楽しそうで……。ピンク色の花々が舞うこの世界はとても優しくて、幸せで溢れていて――ピアの目頭が熱くなる。
「バートさん、今日は来れて良かったですね」
声を詰まらせてそう言うと、バートの腕が伸びてきた。
「ああ、今俺ホントに幸せ」
バートはピアと、リィトを抱きしめるバリを包み込んだ。
ナイトはバートや箱船に乗って訪れた人たちと近況を報告しあうと、いつものように見回りを始める。
帝国騎士となり、そして新たな継承者の一族となってから、ナイトは帝国の皆の安全と安心な生活を守るために危険度の高い仕事や荒事には積極的に関わってきた。それは他の人間となった騎士達に万が一のことがあったら、彼らに関わる者達が悲しむし、帝国の損失にもなるから。
そして、自分が積極的に動くことで、マテオの人達が帝国で暮らしやすくなるかもしれないという思惑もあった。
(俺が出来るのは身体能力を生かした荒事だけで……)
家族と過ごしているチェリアの姿がふと目に入った。
それ以外のことは、チェリアに助けられてばかりだった。相変わらずコミュニケーション能力は低いままだ。
「まあぶっちゃけると俺脳筋だしね! 仕方ない!!」
思わず声を出したとたん、笑い声が響いてきた。――ルルナだった。
「ナイトさんはこんな日もお仕事してるんですね」
「脳筋だからそれしか思いつかないんだよ!」
そう答えると、ルルナの顔はますます笑顔になる。
「……チェリアさん、凄く元気になりましたよね」
「うん、幸せそうだし結構なことだ」
家族と幸せそうに過ごしているチェリアを、なんとなく二人で眺めていた。
「んー……ルルナも、いい人見つけないとな。ナイトさんとは将来親戚になりたいんだけど、ナイトさんは結婚の予定は?」
「え!? あー……今後の事を考えたら、血を残すとか考えないといけないのか?」
もちろんというように、ルルナは頷いた。
火の継承者の一族となったものは少ない。
神官のジェルマン・リヴォフが国から求められ、再婚をして子供を儲けたという話は聞いているが……。
「チェリアにも家族云々言われたんだよな、サラッと流してたよ……相手いねえ」
「そんな暇ないほど、ナイトさん頑張ってるもんね!」
「頑張ってる、か……」
成果は出ているだろうか。皆を、世界を護れているだろうか。
辺りを見回せば、幸せな光景ばかり目に映る。
数年前には見られなかった、満開の笑顔の花々。
ああ、世界は回復に向かっている――うん、護れている。
少し前。
「チェリア、あとの時間は家族でのんびり楽しもうね」
自分達のもとに戻ってきた妻、チェリアの手をアレクセイが握りしめる。
息子のヴァレリーは、すぐ側で幼子たちと遊んでいる。
「チェリアが一緒じゃないと、俺……ヴァレリーの母に間違えられるんだ……」
遠い目をしてアレクセイは言う。
相変わらずアレクセイの外見、そして物腰も綺麗な女性そのものだから。
「いいじゃないか、それで私は困ることはない。女性に言い寄られることもないだろうし」
笑いながらチェリアはそう言うが、アレクセイとしてはやはり男として、チェリアの夫として見られないのは嫌なのだ。
「ヴァレリー、他の子と普通に遊べているようでよかった」
チェリアの言葉に頷き、アレクセイは彼女の横顔を見る。
「チェリア、俺は今、最高に幸せだよ」
手をぎゅっと握りしめて言うと、チェリアは少し恥ずかしそうな顔を向けてきた。
「突然、何を」
「……ふふ。伝えておかなくちゃと思って」
「家のことも息子のことも、アレクセイに任せっぱなしですまない」
「確かに、一緒にいられる時間が少ないのは残念だけれど。それでも、こんな時間がすっごく幸せだから」
チェリアが謝る必要なんてなにもないと言い、アレクセイは言葉を続ける。
「俺はチェリアが大好きだ」
アレクセイはヴァレリーの方に優しい目を向けて、再びチェリアへと戻す。
「二人を心から愛してる」
「私も、アレクセイとヴァレリーが大切だ。愛してるよ」
途端、アレクセイは子ども達とチェリアの間に回り、彼女とキスを交わす。
そして、少し照れくさそうに微笑み合った。
「……さて、そろそろご飯にしょう、ヴァレリー!」
息子を呼んで、満開の桜の木の下に。
「今日は、二人の好きなものをいっぱい作ってきたよ。――さあ、召し上がれ」
お弁当と、飲み物を並べて両手を広げてチェリアとヴァレリーに勧める。
ヴァレリーはまだ普通食が食べられるようになったばかり。
二人で穏やかに見守りながら、家族で過ごす大切な時間を楽しんでいく。
友人のウィリアムがウィリアムがッウィリアムがががッ魔石と共に消えてから四年の間、ロスティン・システィックは主に怒りのはけ口とされていた。
調整役として、多方面の主張を聞き、挟み撃ちになりながら、ヘラヘラ笑って躱して、双方が感情的にぶつかりあわないよう、矢面に立ち続けていた。
(まあ、とりあえず。魔石も船も帝国に接収されてマテオ民溺死という最悪の事態はならなかったし。その裏で親父達やサーナさんが折衝頑張っているだろうけど、それはそれ、適材適所でいかないと)
そんな考えのもと、サンドバックになってきた四年間だった。
帝国は帝国が魔石を管理すべきだと考えているが、新たな世界の魔力を統べる王となったランガスの考えと帝国の考えは必ずしも全て一致しているわけではない。
なぜなら、ランガスは帝国の民以外も、自らの使い――継承者の一族として認めているからだ。
その一人、地の継承者の一族となったクラムジー・カープは、帝国に仕え、宮廷で働いている。公務を真面目に確実にこなすことの見返りとして、マテオ・テーペに残る人々の速やかな救出を王や帝国に働きかけ、求め続けて、帝国側を動かしているようだ。
アトラ・ハシス島にいる者の中にも、リモス村で暮らす民の中にも、帝国に属せず、一族となったものが複数いる。
魔石は帝国皇帝家に限らず、その人物たちが管理していくだろうし、魔力を還した者や、手放したものたちが無駄に争い合うことではない……だろう。
「まだ残っている諸々のことは時間をかけながら解消していくしかない。どうせ1000年2000年後には国も何もかも変わっているだろ」
そして、ロスティンは自分の隣にいる、大切な妻、エルザナ・システィックに目を向ける。
「だから、今はとりあえず一時の平和を噛み締めながら生きていこうな。多くの人の頑張りと犠牲の上で成りったているのだから」
彼の言葉に、エルザナは穏やかな顔で頷いて、身を寄せる。
「残った俺達が幸せにならないと怒られるよな」
「そうですね」
二人の視界に、子どもたちの姿が映る。
幼子たちが、舞い落ちる花びらの中、楽しそうに遊んでいる姿が。
「次は俺たちも子供も生んで、一緒に来ような」
「はい」
手を繋ぎ合って、幸せそうな人々の姿を眺めていく。
「しかしなんだ、あの女の子を見てると、アイツの姿が思い浮かぶ」
黒髪の目立たない印象の女の子が、同世代の男の子たちを従えている。
何故かその子を見ていると、友――ウィリアムの姿が思い浮かんだ。
「そのうちウィリアムに会って、あっちの魔石の確認と、こっちに苦労かけやがった罰として関節技かけないとな!」
「ふふ、体格が違いすぎますし、逆にかけられてしまいますよー。二人がかりでやりますか? 私、彼に襲われたふりでもしましょうか。関節技よりもあの二人にダメージを与えることが出来そうですよ。うふふふふふふ……」
「それは……俺もダメージ受けそうだからやめて! 一人でやれるさ。魔力無くなってから、その分の訓練をトレーニングに回してきたんだ。もうひ弱とは言わせない体になったし。よく知ってるだろ?」
腕まくりをして、腕を見せるロスティン。
「……まあまだ一般から見れば普通ぐらいかもしれないが」
「一般の方よりは引き締まっていますよ」
ただ、訓練を積んだ騎士と比べると、特に目立ちはしないのだけれど……。
「あと10年したらガチムチ体型でポージングするぞ!」
「期待してます」
意気込むロスティンの腕に、エルザナはぎゅっと抱き着いた。
アトラ・ハシス島から訪れた人々が集まっている場所に、ヴィーダ・ナ・パリドは夫のセゥ・ナ・パリドと息子のアズル・ナ・パリドと共に腰をおろした。
「子ども、沢山集まっているな」
アズルと同じ年齢くらいの子どもも少なくなく、花びらを集めたり、楽しそうに遊んでいる。
「このクッキー配りながら、挨拶してこいよ」
ヴィーダは作ってきたクッキーを取り出すと、アズルに持たせる。
慣れ親しんでいる部族の人達だけではなく、息子には様々な人達と関わり、社交性を身につけていってほしいと思う。……夫のセゥは生立ちにより、社交性があるとは言えないし、彼に関してはこのままでもいいとは思っているのだけれど。
ヴィーダは息子を「よく食べてよく寝てよく遊べ」という方針で育ててきた。
同時に『いつか大切な人が出来た時、守れるように、後悔しないように』と、体術や知識をセゥや村中の人たちと関わらせ、得るよう導いている。
ここでの交流も、アズルの成長の糧になるだろう。
アズルを見守りながら、セゥと二人でクッキーをつまんでいく。
「この間、あいつ大きくなったら俺とシャナを嫁にするって言ってたんだけど、どう思う?」
「……むしろ、それにヴィーダがどう答えたのかが気になる」
そういうセゥの口調から、軽い嫉妬を感じ取って、ヴィーダは思わず笑みをこぼす。
「俺はセゥのモノだからダメだって言ってあるよ」
「子どもの夢を壊さなくても……」
「なら、プロポーズ受けた方がよかったか」
悪戯気にそう言うと、セゥは何ともいえない表情で口をつぐむ。
嫌なんだ。だけど、息子の事も大切。そんな彼のジレンマを感じて、ヴィーダはますますおかしくなってしまう。
すこしして、アズルが二人の元に戻ってきた。
「ちゃんと挨拶できたか?」
「うん、クッキーおいしいってみんないってた!」
「そうか、よかったな。これはおまえの分だ」
アズルを撫でてあげて、彼の分のクッキーを差し出した。
ちなみにヴィーダの料理の腕は随分と上がっており、味はもちろん、見た目も悪くはないできだ。
「お前の名前はセゥが付けたんだ。今度は、セゥと二人でこの子の名前を考えてくれよ」
クッキーを嬉しそうに食べるアズルに、自分のお腹を指差し、語りかけるヴィーダ。
突然のその言葉に、きょとんとするアズル。
「それって……」
セゥが驚きの目を向けている。
「そういうことだ」
にやりと笑うヴィーダ。
「あかちゃんのなまえ、きめていいの? やったー」
アズルにも伝えてなかったのだけれど、すんなりと受け入れ、喜んでいた。
「そうか。家族が増えるな。いっそう、頑張らないと」
家族を、幸せにするために。
そんなセゥの想いが、短い言葉からヴィーダに伝わってきた。
「俺も……あ、妊娠中は無茶しないぜ?」
ヴィーダの言葉に、セゥは口元に笑みを浮かべて頷いた。
そして彼は、感謝の言葉の代わりに、ヴィーダの肩を軽く抱いた。
「俺もまた剣以外の知識、深めないとな」
息子を妊娠中、ヴィーダは薬学の知識を深めていた。
人が魔力を無くしたこの世界で、人間として、大切な人たちと生きていくために。
「お兄ちゃんだな」
セゥがアズルの頭を、愛しげに撫でた。
そして、夫婦で微笑み合う。
こんな風に生きる日々が、幸せだった。
継承者の一族となった、レイニ・ルワールが航海士を務める船旅で、幾つかの島が発見されていた。
ただ、人が暮らせるような島は今のところ発見されてはいない。
その船に乗り、旅をしている家族――ウィリアムとアーリー・オサードも、二人の間に授かった娘を連れて、この地に降り立っていた。
ウィリアムは髪を短髪にし、身なりも整え、四年前とかなり印象を変えている。
立場上、来るつもりはなかったのだけれど、娘の可能性を広げる為、広い世界を見て貰おうと、夫婦で話し合って決めた。
(考えたくないものだが、愛する者を見つけてほしいし、俺等の影響で、隠れて過ごす生活を全てにしちゃいかんだろう。それに、ダチも沢山作って欲しいしな)
少し不安を感じながらも、ウィリアムは娘の背を押す。
「まぁ遊んで知り合い作ってきな」
気が済んだら呼んで知らせてくれ。そして、気に行った奴がいたら、教えてくれ。
そう言って、ウィリアムは娘を送りだす。
色眼鏡で見ず、自分の感じたまま考えて、この世界を楽しみ、愛する方法を探したら幸せになれるという理念のもと、友達増やしてみろと教えてはいる、が。
「さてどうなるか。図々しいからなあいつ」
傍らにいる、アーリーに目を向ける。
「俺等の娘だしなんとかすんだろ」
「そうね……」
アーリーはかなり心配そうだった。
「けどここは、マリオのおっさんに護られた、争いが起きない島なんだろ?」
はじめての一人行動に適した場所ともいえる。
人の少ない場所で立ったまま、娘が向った方向や、集まった人達の姿を眺めていく。
「しかし四年かぁ……アッと言う間だったけど、いろんな苦労がございましたね」
ウィリアムはアトラ・ハシス島に渡ってからの四年間を思い浮かべる……。
まずは山の一族の信頼を得て、資料を見せてもらおうと色々な手伝いに明け暮れた。
子供相手にウィリアムが剣を教え、アーリーが字を教え、それぞれ手品、学問、サイバイバル技術――は山の一族の方が長けていて教わる事も多く、親の威厳を護りながらの四年間。
「そういえば、手製メイド服、好評だったな」
「それを作るために、私の妊娠中、難民の村におりて、浮気してまわったのよね、あなた」
「してないだろ!? 山の一族の原始的な方法じゃ、命の危険が、だな。冬は栄養のつく食材手に入りにくいし、難民村の女性に助けてもらったり、色々売買する必要があってな」
特に冬は、山の一族の住処と難民たちの村との行き来にはかなり時間がかかり、夜中に出かけて、翌日の夜帰ってくるなどということが多かった。
ウィリアムからすれば、危険な山道を寝ずに歩いていたのだが、アーリーからすれば、妊娠中で精神的にも不安定な時に、唯一の頼れる存在が、泊まりで不在だったということで、帰ってからは随分と問い詰められたものだ。
(なんかモテて、ハート型の菓子や、手紙なんかも持ち帰って、修羅場になってしまったこともあったわけだが)
「真偽はともかくとして、こんな日が訪れるなんて、思いもしなかったし、今も夢みたい」
アーリーの方から、手を繋いできた。
その浮気疑惑の頃からか。アーリーは随分と積極的にウィリアムを求めるようになった。
「そうだな。俺も不思議な気分だ。あんな歴史が繰り返されないように、石版に記していかないとな」
ちなみに、山の一族の資料を見せてもらおうとして奮闘してきたが、何もなかったということが、既に判明している。現在はきちんと儀式の間に残すために、奮闘中だ。
「山の一族に伝わっていることや、アーリーから聞いた火の一族のことは、かなり重要な部分だからな、出来るだけ中立に残さないとな」
ウィリアムの言葉に、こくりとアーリーは頷く。
「ところで、サーナに会わなくていいのか? 来ているらしいが」
「資料作成のため?」
「いや、そうではなく」
「……私から話すことなんて、何もないわよ」
「そうか」
満開の桜と、人々の姿を見ながら二人きりで並んで、穏やかな時を過ごしていると……。
「モーブー!!」
大きな声が響いた。娘の声だ。
「モブじゃなくて、ロブだって」
ウィリアムは今、ロブという偽名を使っている。娘にその名を呼ぶように言ってあったのだが。
「いいじゃない、目立たなそうな名前で」
くすくすアーリーは笑っている。
「まあいいか」
と、ウィリアムは娘を迎えに行く。
そして、娘の小さな手を引いて、アーリーのもとへ戻ってきた。
「なんか、子分ができたらしいぞ」
「あなたに似て、腕っぷしが強いから……」
(アーリーに似て、気が強いしな)
と思ったが、ウィリアムは口にはせず、アーリーと苦笑する。
今、アーリーの身体には、もう一つ小さな命が宿っている。
また一つ、幸せが増えるのだ。
幸せを失ったひと、得られなかったひと、知らずに消えた命。
心に刻まれた人々の姿を忘れずに、未来に繋げていこう。
柔らかな風が吹いた。
舞い落ちる桜の花びらを掌で受けて、マシュー・ラムズギルは傍らの女性、リッカ・シリンダーに向けた。
「綺麗ですね」
「……はい」
リッカは人付き合いは得意ではないものの、自然を観ることは嫌いではなようで、美しいものを、美しいと感じる心を持っていた。
マシューは今回、人の輪の中に誘うことなく、隅の方で彼女と花を観賞していた。
「あの……どうして、お誘いくださったのですか?」
会話が途切れた時に、リッカがマシューに尋ねた。
『ただ貴女と一緒に花を愛でたいからです。それが理由ではいけませんか?』
そんな言葉で、マシューはリッカを誘った。
表向きは「研究の息抜き」としての誘いで、その誘いに応じて訪れたわけだけれど。
二人共息抜きなど必要ない程、熱心に研究に勤しんでいるから。
最近では、議論を交わせるようになり、それによりアイディアが生まれたり、成果につながることもあり、日々充実していた。
マシュー自身については、魔力研究家として世間的にも認知される存在になっていた。
リッカの真意はわからなかったが、ただ疑問に思っての問いではないことは、わかる。
四年の間、マシューは自らを律し研究に打ち込むためにリッカには指一本触れることなく過ごしてきた。
「実は開発されたばかり魔法の具がありまして、ぜひ貴女に感想を聞かせていただきたいのです」
「はい……?」
「これは魔力を持ってない人にも有効な特殊な魔法具で、装備すれば永遠に効力が失われることはないのです」
リッカを伴侶として迎えたいという気持ちを、抑えられなくなっていた。
「少々お手を拝借します」
不思議そうな顔をするリッカの左手をとって、その薬指にマシューは指輪を嵌めた。
「……」
指に嵌められた、魔法鉱石が使われているとは思えない指輪を、黙ってリッカは見つめていた。
「永遠に効力が失われないもの、それは貴女への愛です」
顔を上げると、マシューの真剣で、それでいて優しい瞳があった。
「貴女も誓っていただけますか? 永遠の愛を」
確信、があったわけではない。
多少の不安もあったが、リッカは自分の気持ちを受け入れてくれると、マシューは信じていた。
「はい……っ」
迷うことなく声を詰まらせて、リッカが返事をした。
マシューの心が、熱い感情で満ちていく。
「ずっとこの日を夢に見ていました……」
「私も……待っていましたよ」
少し咎めるような目で言うリッカ。
「お待たせして申し訳ありません」
そして、マシューはリッカの肩を抱いた。
「では、誓いの口づけを」
目を閉じた彼女の唇に、自分の唇を重ねた。
「こんな人の多い場所で、恥ずかしいです」
キスを終えると、リッカは赤くなって俯く。
「美しい花々が私たちを隠してくれています。貴女は私だけを、私は貴女だけを見ていればいい」
そして、そっと抱き締め合った。
「ちちうえーーーーー!!」
ごぎげんな大声に、エクトル・アジャーニが振り向く。
息子のチェーザレが別居中の妻、リンダの頭、もとい肩の上でとても嬉しそうに手を振っている。
「こんな時にも仕事か」
「そっちも平常運転だろ」
エクトルは騎士服、リンダは普段通りの甲冑姿。
「ちちうえとははうえはなかがおよろしいのですね」
無邪気なチェーザレの言葉に、エクトルは苦笑する。
「そうです、ちちうえ。さっき、ははうえにはみえないひとにあいました!」
「見えない人?」
「ああ、誰もいない方向に向かって話しかけてた。チェーザレだけではなく、公爵家の息子や、水の娘も一緒だ」
リンダがその時のことをエクトルに説明していく。
ラトヴィッジとサーナの子どもや、アレクセイとチェリアの子どもたちと遊んでいたチェーザレは、誰もいない方向に向かって度々話しかけたり、遊びに誘うしぐさを見せることがあった。
「誰だったか……水の継承者の母は『精霊さんね』と言っていたが」
「そうか……」
エクトルはチェーザレの目を見て、語りかける。
「彼らは大人には見えないんだ。お前にとって大切な仲間であり、悪い人から護らなければならない存在だ。悪い人にはないしょにしておかないと駄目だぞ」
エクトルの言葉に、チェーザレは不思議そうに首をかしげる。
「それでどんな人だった」
「んーと、つまらなそうにしているおにいさんとか、おねえさんとか……いっしょにあそびたそうにしていたちいさなこもいました」
「仲良くなれるといいな」
「はい!」
友達いっぱい作りますー! とリンダの頭を掴んではしゃぎまくるチェーザレを、落ちないようリンダは両の手で支える。
「それで、リンダ」
吐息をついて、エクトルがリンダに目を向ける。
「なんだ」
「家臣たちに結婚を勧められている」
「……離婚はしていないはずだが」
「子孫を残すために、別に正妻を娶った方がいいという話だ」
風の継承者の一族となった者は少なくはないのだが、帝国への愛国心、忠誠心を持っているのはアジャーニ家だけだ。
今のエクトルは、多数の女性を妻とすることを勧められる立場にある。
「僕はそれを望まないが、あと一人は子を儲ける使命があると思う」
愛息子、チェーザレに会うために、彼の母親でありつづけるだけのために、リンダが離婚をしないというのなら、彼が新たに妻を娶ることを阻む理由はない、のだが……。
リンダはエクトルのことを、憎からず思っている。だから複雑な心中だった。
「僕も仕事で街の家に帰れる日は少ない。宮殿の部屋は同室でもいいと思うんだが、どうだ?」
考えておいてくれ。
そう言うと、エクトルは家臣たちが作った花見の席へと、リンダたちを誘った。
* * *
花々の香りを胸いっぱいに吸い込む。
「夢みたいなところだね……」
感動したリック・ソリアーノは、妻のイリス・ソリアーノ(イリス・リーネルト)に微笑みかけた。
イリスは、その中にわずかな切なさがあることに気づいたが、何も言わずに頷いた。
彼女の腕の中には、まだ一歳に満たない幼子が抱かれている。
二人の子でアステルという名の男の子だ。
「ちょっと待ってて。用意するから」
リックは持って来た荷物を下ろすと、中から大きな布を取り出す。
お花見の準備をする彼を眺めているイリスの視界の端を、花びらが舞った。
アステルが手を伸ばしてそれを掴もうとする。
一生懸命に花びらを追う我が子の様子に、イリスは微笑んだ。
「この子も花が好きみたい」
花びらのほうにそっと身を寄せると、アステルの手のひらにふわりと舞い降りた。
「あー、あう」
「あ、花びらを食べちゃダメ」
イリスがフゥッと花びらに軽く息を吹きかけると、アステルの手から離れて、他の花びらとは違った不規則な動きで飛んでいく。
それがおもしろかったのか、アステルはキャッキャと笑った。
リックも横目でそれを見て笑う。
「――はい、座っていいよ」
お弁当の準備が整ったリックに呼ばれて、イリスはやわらかな布の上に腰を下ろした。
綺麗な花々に囲まれて食べたお弁当は、特別においしく感じられた。
食後に淹れた紅茶のカップを手に、イリスは空を見上げる。
人工ではない青空に、心も体も芯から元気にしてくれるような暖かい陽射し、花の香りを運ぶやわらかな風。
アステルに外の世界を見せられてよかったと、イリスは心から思った。
アステルは今、気持ち良さそうに眠っている。
「さっき、ちょっと聞こえてきたんだけどね」
そう前置きしたイリスの顔は、何かに期待するような色があった。
「アルザラ港から出港した避難船の一つが帝国にたどり着いて、乗っていた人達は保護されてたんだって。今、その人達はレイニさんがアトラ・ハシス島に連れて行って、そこで暮らしてるんだって」
レイニさんという人は、リルダの親戚らしいとイリスは言い足した。
アルザラ港を出た船は何隻もあるが、存在が確認されたのはアトラ島に着いた船と帝国に保護された船のみである。
リックは、イリスが何を言おうとしているのかに気づき、息を飲んだ。
「それじゃあ、もしかしたら……」
「うん、お母さんと弟はアトラ・ハシス島にいるかもしれない」
「そうだね。きっと――きっと、いるよ! 今度、レイニさんに聞いてみようよ」
リックも、イリスの家族がアトラ島で生きていることを強く願った。
「いつか二人に会って、リックとアステルのことを紹介したい」
「僕も、イリスの家族に会いたいな」
わたしが結婚して子供がいると知ったら驚くだろうな、とその時の母と弟の顔を想像してイリスは小さく笑う。
そして、隣のリックの手に自分の手を重ねた。
あれからリックはだいぶ背が伸びた。イリスも少し。
まだあどけなさが残っていた顔立ちも、成長とともに大人のものになっていった。
二人は今も、マテオ・テーペの人達のためにできることを考え、力を尽くしている。
「リック、わたし幸せだよ」
重ねた手に想いを込めて微笑むと、その手はリックにすっぽりと包み込まれた。
「僕だって。……改めて口にすると、何か照れるね」
そう返したリックの頬は、うっすらと赤い。
「……マテオ・テーペの人達の救出は、もうすぐ終わりだね。ここまで来れたのは、あそこにいる人達、救出に携わる人達、みんなでがんばったからだよね。――きっと、みんな助かる。マテオ・テーペに戻ったら、わたし達も最後までがんばろうね」
「うん、もちろん。本当に、イリスが一緒で良かった」
リックの目は、過酷な毎日を共にいてくれるイリスへの愛情と信頼に満ちていた。
イリスはリックに寄り添い、これからもずっと一緒にと誓った。
イリス達からさほど離れていないところで、リュネ・モルとフレン・ソリアーノ男爵による攻防が繰り広げられていた。フレンはリックの父である。
「はーい、おくちあーんですよ、おくちあーんをしたい、いや、する」
「しねぇよ! そういうのは姫さん達にやってやれ」
イチゴを手に迫るリュネをかわし、フレンは仲良くおつまみを食べているルース・ツィーグラーとベルティルデ・バイエルを指す。
二人が食べているおつまみは、ポワソン商会からの差し入れだ。漁業が軌道に乗って来たこの商会から、花見客へ海産物から作った肴や酒類が提供されたのである。
リュネとフレンの視線に気づいたルースは、呆れたようにため息を吐いて言った。
「バカなことやってないで食べたら? せっかくもらったんだから」
「とてもおいしいですよ」
ルースとは反対に微笑むベルティルデ。
「くいしんぼさんですね、ふふふっ」
「あんたね……。そういえば、あの時のヘベレケ……」
「あ、今の姫様はおこりんぼさんですね~。ウフフ~♪」
ルースの言葉を遮っておどけるリュネだが、その目は何かを訴えていた。
そのことは言わないで、だろうか。
仕方ないといった顔で、ルースは言いかけた先を飲み込んだ。
ところが、差し入れのワインが入って調子が良くなったフレンが、話の続きを聞きたがった。
「ヘベレケって何だよ、何かあったのか?」
「いえ……芸達者と思っていたピエロが、実は酔っ払っていただけというどうしようもない話が……。それより男爵さまには聞いていただきたいことがっ」
リュネは無理矢理話題を変えた。
話の内容は、主にリュネが本土の街でどんなことをしてきたかというものだった。ヘベレケになったことは割愛して。
フレンは一つ一つ頷きながら耳を傾けている。
「――なるほど、ガーディアン・スヴェルか。何て言うか、魔物と戦ったり武装勢力と戦ったり……人間てのは、滅亡しかけても二人以上いると喧嘩しちまうんだなぁ」
フレンはそう言って、悲し気に目を伏せた。
「姫様にも、宮廷で一人でご苦労をおかけしてしまいました」
「肝が据わった姫さんだ。くじけたりはしなかっただろうよ」
ルースとベルティルデは、今度はリュネがバスケットいっぱいに持って来たイチゴを食べながら、目の前で咲く花々を指さしては楽しそうにおしゃべりしている。
ところで、とフレンも分けてもらったイチゴを一つ摘まんで問いかけた。
「すごい量のイチゴだな。しかも甘さと酸味のバランスもいい。帝国の土はなかなか良いのか?」
「いえ、帝国の気候はイチゴを育てるのにはあまり向いていません。ですがこのリュネ・モル、謎の帳簿力(ちょうぼぢから)や調達力、話術などをもって困難を達成しました」
「おいおい……犯罪に手ェ出してねぇだろうな?」
潔白です、とリュネは胸を張る。
「相変わらずだな。その力で平民宰相にもなれそうか?」
「それが、帝国は城壁の守りが固くてですね、その夢はじりじりとじわじわと一生かけて、あるいは次の世代、その次の……というつもりで、まずは実績を積み上げていきます。私は皆が働けて満たされる世を作りたい!」
「ほうほう。じゃあ、長生きしねぇとな」
そこからは帝国の女性達の話になった。
フレンは、美女はいるかと興味津々だった。
「そういや、あの花壇。みんなで大事にしてるぜ。ま、食いモンの事情で食えるモンができるものがほとんどになっちまったがな! いろんな奴が世話しに来るから、俺が出る幕がねぇよ」
そう言って、フレンは陽気に笑った。
マテオ・テーペには温泉がある。
その地熱を利用した花壇には、観賞用の花が植えられていたのだ。
二人の会話が聞こえたのか、ベルティルデもその花壇を思い出して懐かしそうに微笑んだ。
行ったことがないルースに、リュネが説明した。
「そんなものがあったの。いいわね、温泉で温まって、綺麗な花があって。リモス村には温泉はないけど花壇はあったわね」
花が好きなルースにとっては、村のお気に入りの場所だ。
「花ってのはかわいいよなぁ」
フレンもしみじみと言った。
「リュネさんも、イチゴを召し上がってください。本当においしいです」
「それはよかった。何ならあーんしますか?」
「ちょっと、変なこと言ってんじゃないわよ!」
イチゴを摘まんでベルティルデに迫ろうとするリュネを、ルースが阻止しようとする。その手にはフォークが光っていた。
流血はごめんだ、とフレンとベルティルデで止めに入り、四人はワイワイと騒ぎながらこの時間を楽しんだのだった。
ベルティルデ・バイエルは、すぐに見つかった。
名前を呼ぶと、彼女はルース達に断りを入れてコタロウ・サンフィールドのところへ足早にやって来た。
「こんにちは、コタロウさん。一つ、持ちますね」
ベルティルデはコタロウの手から、お弁当の箱を持ち上げた。
花見ということもあり、本土からは弁当売りや屋台なども訪れている。
二人はルース達の近くに腰を下ろした。
おいしいワインで乾杯した後、コタロウはしみじみとした声で言った。
「マテオ・テーペの人々の救出も終わりが見えてきたね。みんなにはお世話になったから、少しでも恩返しできていたら嬉しいよ」
「コタロウさんには、どれだけ感謝しても足りません」
ベルティルデは、心からそう言った。
「技師長のコタロウさんがいるから、皆さんは安心して長い船旅に出られます。コタロウさん自身の目標もあるのに、何年もマテオ・テーペの人達に尽くしてくださって。わたくしは公国の民ではありませんが……」
「ベルティルデちゃん」
だんだんと申し訳なさそうな顔になっていくベルティルデの言葉を、コタロウは途中でそっと遮った。
「俺は、あの状況で外国人の自分によくしてくれたマテオ・テーペの人達に感謝しているんだ。ここまで来たら、みんなの平穏な生活を見守ってからじゃないと落ち着かないよ」
だから気にしないで、とコタロウは微笑んだ。
そして、話題を切り替える。
「最近はどう? 何かおもしろいエピソードとかある?」
ベルティルデは、コタロウの気遣いに感謝してリモス村でのことを話し始めた。
「前に、マテオ・テーペの子供達とジョギングしようとお話ししたのを覚えていますか?」
儀式に向かう箱船の中で、二人で未来の話をしたことがあった。
「始めています。皆さんとてもお元気で、いつもわたくしは置いて行かれてしまうのです」
子供達に、遅いよとからかわれることさえも楽しいというふうに、ベルティルデはクスクスと笑った。
マテオ・テーペから箱船で人々を送り出すたびに誰かが死んでしまっても、生まれてくる命もあった。
その子達がリモス村に着いて成長し、朝、ベルティルデと走る。
「あの子達と一緒にいると、わたくしにもできることがまだあるはずと勇気が湧いてきます。コタロウさんは、最近は何かありましたか? 確か、魔王軍から造船の依頼があったと聞きましたが」
「うん……いろいろと希望を聞きながら設計から始めてね。実はその後『船長』に誘われたんだ」
ベルティルデは目を丸くさせた。
「まあ、さっきも言った通りマテオ・テーペのみんなが幸せに暮らすのを見守りたいから、とりあえずは相談役のポジションで、旅路への同行は辞退したんだけどね」
「そんなことがあったのですか……」
「そういえばベルティルデちゃんは『なんか頭使う担当部長』とかいう役職らしいよね。――いつか。ずっと、先のいつか。一緒にヴォルクの船で航海できる日が来るとおもしろいよね!」
にっこりして言ったコタロウに、ベルティルデもそんな未来を思い描いて、楽しそうな笑顔になった。
「きっと、そういう日が来るはずです。陸ももっと増えて、新しい命も増えて……その時は皆さんと楽しい船旅ができるに違いありません」
希望に満ちたおしゃべりに顔を輝かせる二人を応援するように、花々がそよ風に揺られていた。
コタロウに魔王軍専用の船を依頼したヴォルク・ガムザトハノフは、ジスレーヌ・メイユールや軍団員達と花見を楽しんでいた。
ジスレーヌは救出されてくるマテオ民をまとめる傍ら、あまり上手くなかった料理の勉強もしていた。料理が上手いヴォルクに刺激されたのである。
料理が得意な人にいろいろと教えてもらいながらがんばってきたが、彼女の味付けはどうにも大味であった。
その大味な弁当とポワソン商会の酒や肴を飲み食いしながら、軍団員は久しぶりに羽を伸ばすことができて大はしゃぎだった。
今日を除き、日々の修行は一日たりとも欠かしたことはないからだ。
また、向こう見ずな若者の集まりのわりには意外にも品行方正な魔王軍に、ならず者にはなりたくないが街は居心地が悪いという人が、仲間になりたいと言って加わってきていたため、この四年間でけっこう人数が増えていた。
笑い合う彼らをジスレーヌも楽しそうに見てから、ヴォルクに造船について話し始めた。
実のところ魔王軍専用船は、設計図が完成した段階で足踏みしている。
「――リモス島には、船を造るだけの木材がありません。もともと木材にできる木がありませんでしたから、どうしても帝国に頼ることになります」
事実、家具などに使われる木材は帝国から仕入れるか、帝国の大工や家具店に製作を依頼している。
「リモス村もまだまだ食料に余裕があるとは言えませんから、木を植えるなら食べられる実がなる木を優先します。なので、帝国から必要な木材を買うとしても……お金がありません……」
ジスレーヌも、個人的にはヴォルクの船旅を応援したいし、一緒に行けるなら休暇を取って行ってみたいと思っている。
「ヴォルク君、島の周りの渦を越えられる船を、自分達だけで造るのは難しいと思います」
残念そうに言ったジスレーヌに、ヴォルクは小さく唸って考えた。
例えば今、帝国に協力することで船を借りたとして。
ヴォルクは遠い未来には、帝国と対決することになるだろうと見ている。
その時に。借りた船で戦うことなどできるわけがなかった。
そのことを考えながら告げると、ジスレーヌは対決する理由を尋ねてきた。
「可能性の話だ。帝国が腐敗したら、魔王軍が成敗する」
「そういう未来のお話しでしたか……。それなら今のうちに帝国に力を貸して、操船技術を学んだり報酬を得たりしながら、魔王軍の技術力と資金面を強化するのはどうでしょうか? この二点は魔王軍の弱点だと思うのです」
ジスレーヌは身を乗り出すようにして言った。
そして、さらに続ける。
「そうやって、いつか専用船を持てたら冒険に出ましょう! 私達が知らない島が、きっとどこかに現れていると思うのです。動物はいると思いますか? 想像するとワクワクします!」
頬を上気させて楽しそうに話すジスレーヌ。
ふと、ヴォルクは彼女の傍らに空になったジョッキが転がっていることに気が付いた。
仲間達と乾杯したのはつい先ほどであるから、ジスレーヌはほとんど間隔をあけずに飲み干したことになる。
ジスレーヌはヴォルクを押し倒す勢いで肩を掴み、まだ見ぬ島に想いを馳せている。
「植物や虫も、見たことないのがいるかもしれませんね。魔王軍に生き物に詳しい方はいますか? もしいるなら、必ず連れていきましょう!」
酔ったジスレーヌは、夢を見ているように目をキラキラさせて、うっとりと空を見上げる。
つられてヴォルクも見上げた空は、花びらが舞いとても美しかった。
この花見には、本土の商会や各店舗の従業員なども多く参加している。
酒類やつまみになりそうな海産物から作った肴を、試飲試食の名目で振る舞っているポワソン商会はもちろん、ビールの屋台を出しているパルトゥーシュ商会や慰労として訪れたハオマ亭の従業員などなど……。
「ここ数年で、魚介類がずい分多く市場に出るようになったわよね。リキュールさんの努力が報われましたね!」
リキュール・ラミルの手料理に舌鼓を打ちながら、パルミラ・ガランテがにっこりして言った。
すると、フランシス・パルトゥーシュがニヤリとして混ぜっ返す。
「あの大盤振る舞いも、後々のことを考えてのことなんだろ?」
リキュールは笑顔だけを返した。
パルミラとフランシスに出したのは、リキュール自らが腕を振るった手料理だ。
食した二人の顔を見れば、喜んでくれたことがわかる。
食通家として知られる彼の面目躍如である。
そしてフランシスが言う『あの大盤振る舞い』とは、花見客のために試飲試食の名目で大量に提供した酒や海産物から作った肴のことだ。
「それで喜んでる奴が大勢いるんだ、けっこうなことじゃねぇか。酒もうまい、料理もうまい、文句なしだ!」
「フランシスさん、かなり酔ってますね?」
「今日くらいは羽目を外したっていいだろ? ほら、パルミラも飲めよ。リキュールのとこの酒もうまいけど、うちのビールもうまいぜ」
そう言って、フランシスは近くのビール樽からジョッキにビールを注ぎ、パルミラに手渡した。
国が安定したおかげか、農産物の収穫量も上がりビールの原料も多く獲れるようになったのだ。
酒の製造も細々と行っていたパルトゥーシュ商会は、それを機にビール製造にも力を入れるようになったのである。
ビールをおいしそうに飲んだパルミラは、リキュールを向いて言った。
「漁業が再開してから、ポワソン商会も一気に大所帯になったと聞きました」
「ええ。多くが元スラムの住民の方々でございますが、皆様とても熱心でして手前共の良い刺激となっております。ハオマ亭でも新人をお雇いになったそうでございますね」
「そうなんです。たまーに、酔ったお客さんと喧嘩しちゃいますけど、素直ないい子ですよ」
兄弟が多く、少しでも食い扶持を稼ぐために働いている家族思いの少年だ。
ところで、とパルミラは声を潜めてリキュールに聞いた。
「フランシスさんとはどうなってるんですか?」
「……」
パルミラは、フランシスへのリキュールの想いに気づいている。
しかし肝心のフランシスはその手のことには鈍いのか、気づいている様子は見られない。
「なかなか人の気持ちというものはままならないものでございまして……手前のアピールが足りないのか、あるいは秘めたままにと思ったことの因果でございましょうか……」
「つまり、進展してないんですね」
「こればかりは、如何ともしがたく」
リキュールは諦観のため息を吐く。
追い打ちをかけるように、リキュールの腐れ縁が電撃結婚したという知らせを受けて仰天したこともあった。子供もいるらしい。
しかしリキュールには、それさえもおもしろいと思えるだけの柔軟さがあった。
その時、従業員達に呼ばれて騒いでいたフランシスが、リキュールに呼びかけてきた。
「おーい、こっちで一緒に飲もうぜ!」
リキュールが返事をする前に、パルトゥーシュ商会の従業員らに輪の中に引き込まれていく。
手にはワインが注がれたカップを持たされた。
「これからも、いいもの作ってがんばっていこう! 明るい未来にカンパーイ!」
フランシスの音頭で、今日何度目かの乾杯に沸き立った。
後日、ポワソン商会に海産物に関する相談が多く寄せられた。
いずれも花見の場で試飲試食として振る舞った酒類や海産物から作った肴を食した者や、その噂を聞いた者達である。
利益を還元せよという家訓を真面目に守り続けている成果だ。
リキュールは、街が苦しい時も収益を顧みず惜しまず尽くしてきた。
積み重ねてきた信頼もある。
彼が誠実である限り、街の人達も誠実であるだろう。
キージェ・イングラムとリィンフィア・ラストールは、今もスヴェル団員として街に尽くしている。二人とももうすっかり古株である。
今日も花見に参加と言いつつ、緊急時への備えは忘れていない。
「……特に異常はなさそうだね。ジェイ、ちょっとだけ席外すね。ダリアちゃんのこと、よろしくね」
「ああ、わかった」
その時、リィンフィアとダリア・サマランチが目配せをしたことにキージェは気づいていなかった。
しばらくして戻って来たリィンフィアに、キージェは目を見開き固まってしまった。
「リィン、お前……」
「えっと……どうかな」
いつも通りの動きやすい服装だったリィンフィアは、今は春らしい服を着ている。
言葉に詰まったキージェが横から来る強烈な視線にそちらを見やると、ダリアにじっと見つめられていた。
どうやらリィンフィアへの反応を待っているようだ。
「……もしかして、ダリアのデザインか?」
期待する言葉ではなかったようで、ダリアは少し口をへの字に曲げた。
けれど、そう聞かれたリィンフィアは気にしていないのか、笑顔で頷く。
「うん。デザインと縫製もね。私が風属性だったから、風をイメージしてくれたんだって」
「とても勉強になりました。ありがとうございます」
ダリアはやわらかい表情でリィンフィアに礼を言った。
実は、リィンフィアがおしゃれな服のデザインをダリアに相談したのには理由がある。
スヴェルでの活動が生活の中心にあると、どうしても動きやすい服装が多くなってしまう。
彼女の母はそれを悪いとは言わないが、もう少し女の子らしい服を着たらと、視線とため息で訴えかけてくるのだ。
そこで花見を良い機会にダリアに持ち掛けたのである。
服飾の勉強中であるダリアにとっても、良い話だった。
リィンフィアはこのことをキージェには秘密にしていたので、彼はいつも通りの服装だ。
もっとも、リィンフィアはキージェがどんな服装でも、想いは変わらない自信がある。
「そろそろお弁当にしようか。あの辺りはどうかな?」
リィンフィアがちょうどいいスペースを見つけて、小走りにそこへ向かう。
スカートが軽やかに揺れていた。
綺麗なところで気の合う人達とする食事ほど楽しいものはない。
最近身の回りで起こったことなどを話しているうちに、多めのお弁当も食べ終わってしまいそうだった。
そんな時に、マリオ・サマランチがダリアの前に現れた。
ダリアは飲みかけの果汁水を置き、父のもとへ駆け出した。
「お父様……!」
「ダリア、大きくなったね。元気そうでよかった」
「お父様は元気?」
「ああ、元気だよ。ビルから聞いたけど、服飾関係の勉強をしてるんだって?」
「うん、あのね……」
親子の会話が一段落着くのを見計らい、キージェとリィンフィアが挨拶に立った。
マリオは二人に向けて柔和に微笑んだ。
「今日はダリアと一緒にいてくれてありがとう。リィンフィアさんは、勉強相手にもなってくれたとか」
ダリアからリィンフィアの服のことを聞いたマリオは、感謝を告げた。
「いえ、私が相談したんです。ダリアちゃんが、それを引き受けてくれました」
「親バカに聞こえるかもしれないけど、とても似合ってるよ。二人とも、よかったらこれからもこの子の友人でいてくれると嬉しい」
ダリアの頭を撫でながらマリオは言った。
その後、リィンフィアの勧めで親子は花見の散歩に出かけていった。
父親へ微笑みかけるダリアの横顔を見送りながら、キージェは隣のリィンフィアのことを思った。
彼女が亡くなった父親を慕う様子と重なってみえたのだ。あるいは、マリオがダリアを思う気持ちと。
キージェの思いは、そこから自身の母親のことに移り、そしてイクリールとの会話に至った。
――お前の母親は、継承者の一族の力を持つ可能性がある子供を、その力を利用するであろう一族から隠して、その定めから自由にしてやりたかったんじゃないのか?
死を目前にした彼に、キージェはそう言った。
その言葉はキージェの希望でもあったし、イクリールの魂に少しでも救いがもたらされて欲しいと思ったからでもあった。
「……なぁ、リィン」
気づけば、キージェはリィンフィアに呼びかけていた。
「俺達もあんなふうに、子供を慈しめると思うか?」
少しの間首を傾げたリィンフィアは、次の瞬間に頬を真っ赤に染めた。
つられるように、キージェにも照れが押し寄せる。
「……ん、いや、まあ……」
言葉にならない声をこぼしながら、キージェは少し前に手折った花をリィンフィアの髪に挿した。
ハッとして顔を上げた彼女から、目が離せなくなる。
周り中酔って騒いでいる中、おそらく誰もこの二人に注目なんてしていないだろう。
けれど、キージェは人前でこのようなことをするのは非常に稀であったし、彼自身、自分の行動に驚いていた。
(酔ってる……んだろうな、きっとそうだ)
キージェはこれを先ほど飲んだワインのせいにすることにした。
あるいは花の香りか、いつもと違うリィンフィアのせいか。
幸いなのは、無粋者が現れなかったことだ。
キージェは万が一に備えて、外からはわからないようにナイフや短刀を隠し持って来ていた。
おしゃれしたリィンフィアの傍に、武器は似合わない。
「ジェイ、あの……」
言いかけたリィンフィアの手を取ったキージェは、彼女を連れて弁当を食べていた場所に戻った。
それからダリアが帰って来るまで、二人は手をつないだまま花を眺めていた。
オアシス島の沖に一艘の船がある。
エンリケ・エストラーダの海賊船だ。
見張りの者からオアシス島が変だと聞き、甲板へ出たエンリケは額に手をかざして目を凝らす。
「遠くてよくは見えねぇが、花見をやってるのか? 平和なもんだな」
花見かぁ、と仲間達が集まってくる。
スラム街が整備され就業率も上がってきた本土だが、とりこぼされる人というのはどうしても出てきてしまう。
そういう人達の一部がエンリケのもとに集まり、それなりの集団になっていた。
「あっちにはうまい食い物や酒もたらふくあるに違いねぇ」
「ボス、俺らも行くか?」
軽い調子で言った男を、馬鹿野郎とエンリケは叱った。
「あの中には一般人も混じってるだろうが。俺達みたいなクズがどのツラ提げて仲間に入るってんだよ。堅気の衆には迷惑をかけねぇ。エンリケファミリーの掟を忘れたとは言わせねぇぜ」
「わ、わかってるって。言ってみただけだよ」
男は肩を竦めた後、それじゃあと懲りずに口を開く。
「派手に乗り込むってのは?」
エンリケは短く笑った。
「まぁ、俺もあのど真ん中に火球をぶち込んでやったら、さぞかしおもしれぇとは思うぜ。やらねぇけどな」
「何で?」
「やっても無駄だからだよ、あの島は」
忘れたのかとエンリケは呆れの目を向ける。
その時の間抜けな男の顔から、忘れていたことが明らかとなった。
オアシス島は王に守られた島で、人を害する類の魔法が発動できず、また魔力の影響も受けないという聖域のような場所なのである。
歪んだ魔力の影響に晒され続けているエンリケにとって、立ち寄るには都合の良い島でもあった。
エンリケは睨むように島を見つめてフンと鼻を鳴らすと、花見に浮かれているだろう人達を嘲るように言った。
「せいぜい束の間の平和ってやつを楽しんでくれや」
その言葉に仲間達の目が好戦的に光る。
「やるのか……?」
しかし、エンリケは手を挙げてそれを制した。
「焦るな。確かに今の本土は手薄だが、空っぽってわけじゃねぇだろう」
事実、本土には騎士団長やルーマがいる。何か起こってもすぐに対処できる。
「攻めるなら、ちゃんと機を見ねぇと」
獲物は確実に仕留めるといった気迫あるエンリケの眼差しに、仲間達は戦いに向けた炎をいったん静めた。
エンリケの海賊団は仲間も増え、船の武装も強化されてきている。
しかしそれは帝国にも言えることだった。
今後帝国と戦をするなら、しっかりした策と準備がないとたちまち潰されてしまうだろう。
「その時が来るまで、きっちり牙を研いでおこうぜ」
ニヤリとして言ったエンリケに仲間達は頷くと、本土へ向けてあらん限りの悪口を叫んだのだった。
何年振りかの再会に胸がいっぱいになり、かえってぎこちない空気になってしまったのを、あの時と変わらない岩神あづまの微笑みがほぐした。
「さぁさ、堅苦しいご挨拶はお終いにして、みんなで仲良くお花見を楽しみましょう」
「そうだね。実はさっきからその大荷物の中身が気になってたんだ!」
メリッサ・ガードナーは、あづまの後ろにいるアンセル・アリンガムが運んで来た大きな布袋に視線を送る。
アンセルは苦笑した。
「ずい分張り切って作ってたんだ」
あづまとアンセルで手際よく花見の準備が整えられていった。
大きな布の上に広げられた豪華なお弁当の数々に、メリッサは目を輝かせる。
「見てるだけで幸せになるお弁当だね」
「そう言ってくれると、作ったかいがありますね」
マテオ・テーペの食糧事情は厳しいが、あづまはそんな中でもできる限りの食材を集めて、見た目にも癒されるような特製お花見弁当を作り上げた。『真砂』で評判だった特製ハンバーグもある。
お酒を飲む人も飲まない人も、大人も子供も楽しめる内容だ。
乾杯が済むと、あづまがメリッサが抱いている子供のことを尋ねた。
「そう、ミモザという名前ですか」
「確か向こうのほうにミモザが咲いていたな」
ミモザに微笑みかけるあづまに続き、アンセルは見かけたというほうを指さした。
メリッサがそちらを見やるが、花見の人々が壁になって何も見えない。
「黄色? 白?」
「黄色だった。白も私が見ていないだけでどこかにあるかもしれないな」
「白ミモザ、見せてあげたいなー」
「ミモザの花言葉は知ってますか?」
と、あづまがメリッサに聞いた。
「ううん、よく知らないの」
「いくつかありますが、あたしが好きなのは『感受性』『思いやり』です。――どうか人の痛みがわかる心優しい女性に育ってくださいね」
後半は弁当に夢中になっているミモザに、やさしく語りかけるあづま。
ミモザは、口の周りにソースをいっぱい付けながら元気よく返事をした。
「はーい。ねえ、おばちゃん。ハンバーグ、すごくおいしーよ!」
瞬間、あづまの笑顔が凍り付いた……ような気配がした。
しかし、瞬きの間にその気配は霧散し、あづまはミモザの口の周りのソースを布で拭い取ってやった。
そして、言い聞かせる。
「おばちゃんじゃありません。お・ね・ぇ・ち・ゃ・んです」
「はーい。おねーちゃん」
素直に言い直すミモザ。
アンセルはそっぽを向いて笑いを堪えていた。
あづまは知らないふりをして、ミモザの頭を撫でた。
親友であり実の姉のように慕っているメリッサの娘を、あづまは姪ができたように会えたことを喜んでいた。
それから話題は、メリッサがマテオを出た後のことに移った。
彼女が見たこと感じたこと、それからミモザを授かった経緯などを、あづまとアンセルは相槌を打ちながら聞き入った。
聞き終えたアンセルは、そうか、と静かに受け止めた。
あづまは改めてメリッサに伝えた。
「お帰りなさい、そしてお疲れ様。メリッサさんと会うことができて、今日は本当に幸せです」
「私も、また会えて嬉しい」
メリッサも喜びを噛みしめて微笑んだ。
その後、アンセルはジスレーヌに挨拶に行くと言って席を抜けた。
遠くなっていくその後ろ姿を見送りながら、メリッサはあづまに彼との関係はどうなっているのか尋ねた。
「結婚は、していませんよ」
「え……そうなの?」
「いいんですよ、あたしはこのままで」
アンセルは間違いなくあづまに好意を寄せている。
そのことはあづまも感じているが、彼の中には亡くなった妻への愛情やいまだに消えることのない想いがあることにも気づいていた。
そこに割り込むようなことは、あづまにはできなかった。
メリッサの気遣う視線に、あづまは微笑みを返した。
その時、二人の前に立つ人があった。
長い黒髪の背の高い女性だ。
「……久しぶりだな。ちょっと面貸せよ」
彼女の琥珀色の目は、メリッサに向けられている。
堅気ではない雰囲気の彼女にあづまは少し警戒するが、メリッサとの次のやり取りにそれを緩めた。
「バルバ……!」
その女性の名を呼びかけたメリッサの口は、立てられた指に封じられた。
「……生きてたんだな」
安心したように言われて、コクコクと首を縦に動かすメリッサ。
「まぁ……お前、しぶとそうだもんな」
薄く笑って軽口を叩く女性にメリッサも笑う。
それからメリッサは、あづまにミモザのことを頼んだ。
「ごめんね、ちょっとだけお願いしていい?」
「ええ。お花でも見に行ってましょうか」
あづまはミモザを抱っこすると、先ほどアンセルがミモザの花を見かけたと指さした方へ歩いて行った。
バルバロはメリッサの横に腰を下ろすと、あづま達へ目を向けたまま言った。
「あの小っこいの……お前の子供か?」
「うん。あのね……」
メリッサは、出産の経緯を話して聞かせた。
「――信じるかどうかは任せる」
それに対するバルバロの反応は、
「ふーん。そっか」
と、あっさり信じたものだった。
逆にメリッサのほうが拍子抜けしてしまうほどだ。
バルバロは、クッと喉の奥で笑った。
「それ、マテオのマグマの中の話をした時も、そんなふうに言ったな。……それに、あれだけのことがあって、今さらお前を疑う理由があるかよ」
「ありがとう」
メリッサは温かく微笑んだ。
その顔を見つめながらバルバロは聞いた。
「いろいろあったけどよ……お前、今、幸せか?」
「うーん、幸せ……かなぁ? わかんない!」
あっけらかんと笑って言ったメリッサに、バルバロはやや呆れたように苦笑した。
「わかんないって……。でもまぁ、そんなふうに笑えるなら、悪くはねぇんじゃねぇの」
「うん……わかんないけど、レイザく……あ、ミモザが嬉しいならそれでいいかなって。私にできることは、ちゃんとやれてるのかなって」
ミモザが笑っていてくれるなら、メリッサも嬉しい。
リモス村でも、同じくらいの年の子供達と元気に駆け回っている。
バルバロはメリッサと娘が笑顔で毎日を送っているならそれでいい、と頷いた。
「そろそろ行くわ。……元気でな」
バルバロは立ち上がると、メリッサの顔を記憶に焼き付けるように見つめる。
そして、サッと身を翻して歩き出した。
メリッサから焦ったような声で呼び止められたが、振り向かなかった。
「また会おうね!」
という声には、代わりに手だけ軽く振って返事とした。
人々の賑わいの中に紛れていって見えなくなったバルバロの後ろ姿を、メリッサは少し不安を感じながら見送った。
どうしてか、もう会えないような予感がしたのだ。
寂しさを抱えたままバルバロが去っていったほうを見つめていると、あづまとミモザが帰って来た。
「ありましたよ、白いミモザ。後でご一緒にどうです? ……メリッサさん、何かありましたか?」
少しぼんやりしているメリッサの顔を、あづまが心配そうに覗き込む。
メリッサはハッとして笑顔を作った。
「ううん、何でもないの。えっと、白ミモザ、見つかったんだってね。よかったね、ミモザ。同じお名前だよ」
メリッサに何かがあったのは明らかだったが、あづまはそれ以上は聞かずに屋台で買ってきた飴をそっと差し出す。
「甘くておいしいですよ」
「ありがとう、一つもらうね」
メリッサの口の中に素朴な甘さが広がった。
「酒は飲めるのか?」
そう聞いたアルファルドに、イフは「酒豪ではありませんけれど」と微笑んだ。
適当なところに腰を下ろした二人は、ワインを味わいながら咲き誇る花々を眺めた。
イフは研究に夢中になると根を詰めそうだとアルファルドは思っていたが、それは正しかった。
野菜や穀物の改良研究をしていたイフは、一週間以上一歩も研究室から出ずに研究に明け暮れていたということがあった。
そこで息抜きにと花見に誘ったのである。
ところで、地下牢に潜んでいた頃は薄暗いこともありイフの年齢はよくわからなかったが、外に出てみれば四十代半ばくらいであることがわかった。
「あれから四年か……早いもんだな」
「リモス村もだいぶ安定してきましたわね。まだまだ充分とは言えませんけれど」
土中の塩分もかなり抜けて、作物の収穫量も増えた。
「インガリーサやサク達は元気か?」
「ええ、皆さん変わりありませんわ。インガリーサさんはすっかり村での暮らしが気に入ってしまったようでして、何度か本土への帰還のお話が来ましたが、すべて断っていましたね」
流刑地もいまだにリモス村であるが、今はマテオ民の居住区とは区別されている。
「サクさんも流刑囚の監督を続けていますよ。それと、たまにニールさんの護衛として調査船に乗っています」
ニール――ナサニエルは、もともと考古学者である。そのため、帝国の調査船に乗り、新しい島の調査員に加わることもあった。船には帝国騎士もいるが、ニールが個人的にサクに同行を頼むこともあるという。
「……あら。アルファルドさん、あちらをご覧になって」
何かに気づいたらしいイフが示したほうに目を向けると、バリ・カスタルが面立ちが似た年上の男性と楽しそうに会話していた。
「もしかして、バリの兄か?」
「たぶん、そうだと思います」
「そうか……」
バリがとても喜んでいる様子は、二人が兄弟であると確信させるには充分だった。
それを見ていたアルファルドも胸が熱くなり、思わず目頭を押さえた。
「バリさんも、村でがんばっていますわ。今度、声をかけてあげてくださいね」
イフは、空になっていたアルファルドのカップにワインを注いだ。
それから話題は、準備も大詰めになった学校開設のことに移った。学校は、ジスレーヌの要望もあってリモス村に創られることになった。
「教室と教材はほぼ整いました。最初の生徒さんは、村の子供達がほとんどでしょう。インガリーサさんやニールさんが本土でも生徒募集に力を貸して下さるそうです」
「いよいよだな」
「忙しくなりますね。カッターの研究も続けていくのでしょう?」
カサンドラと彼女の魔力を切り離した魔法具のことで、イフが開発した物である。
アルファルドはイフからその技術を買い取り、遠い未来の人達のために改良と保存に励んでいる。
ただ、その買い取り金額は途方もないものだったため、細々と支払いを続けている状態であった。
「そうだな。けどまぁ、退屈よりはいい。……いかんな、息抜きに誘ったはずなのに仕事の話になってる」
「私達らしいと思いますわ」
イフは微笑んでそう言った。
「まぁ、借金返しきるまで時間かかりそうだし、まだまだよろしく頼むな」
「こちらこそ。ところで、借金には利子があるのをご存知ですか?」
「……!」
愕然としたアルファルドを見て、イフはクスクスと笑い出す。
「冗談です」
ホッと胸を撫で下ろすアルファルドであった。
四年の間に、マルティア・ランツの環境もだいぶ変わった。
あれから彼女はリモス村で病人の診察などを行う傍ら、本土の街にお茶やハーブもある小さな薬屋を開いた。
開店時にはインガリーサ・ド・ロスチャイルド子爵やジスレーヌ達の他に、本土で大工をしているハイン・ジマーマンも知らせを聞いて祝いに駆け付けてきた。
そんな彼らと、今日は花見を楽しんでいる。
料理や飲み物は各々で持ち寄り、マルティアもお茶やお菓子を持ってきた。
集まりの中にはクラムジー・カープもいる。
彼は今、宮廷で仕事をすることが多い。
「ねぇ」
と、インガリーサがマルティアに身を寄せてヒソヒソと言った。
「最近はクラムジーさんと会ってるの?」
マルティアはドキッとした。
「ええ……会ってお話をしたり、お茶やお食事をする機会はありま……す」
「そうなの? そのわりには……」
マルティアの気持ちに何となく気づいているインガリーサは、あれからだいぶ経つのにあまり変化が見られない二人の関係に首を傾げた。
「私が出しゃばるのもどうかと思ったからお節介はしないようにしてたけれど……おかしいわねぇ」
二人がお互いを大切に思っていることは、インガリーサは見ていてわかった。
「思い切って聞いてみたらどう? ちょうどお酒もあるしね」
「え、ええ!? お、お酒の勢いで……という意味ですか?」
「弾みをつけるのよ」
確かに街で会った時にインガリーサが言う『良いムード』になっているのかわからないけれど、とマルティアはあたふたする。
ちらりとクラムジーを見やれば、ハインと何やら話していた。
口にしているのは、マルティアが用意した焼き菓子だ。
(おいしいって、思ってくれてるのかな?)
とても気になってしまうマルティアだった。
そこに、アンセルを連れてジスレーヌが合流した。
ジスレーヌがクラムジーに声をかける。
「クラムジーさん、それから皆さん。こちらマテオ・テーペからいらしたアンセル・アリンガム男爵です」
察して席を譲ったハインに変わり、アンセルが腰を下ろした。
かつてはマテオ・テーペを統治していたアシル・メイユール伯爵と対立していたが、和解した後はマテオのために力を尽くしている。今ではアシルを補佐してマテオを支えている。
「お久しぶりです。アシルからもあなたのことは窺っています」
アンセルはそう始めた。
帝国とマテオ・テーペのことは、宮殿にいるサーナとマテオ・テーペにいる継承者一族の力を持った水の魔術師の間でやり取りされている。
しかし今回、アンセルがオアシス島へ赴くというので、アシルはクラムジーに会って彼の話も聞いてきてほしいと頼んだのである。
クラムジーがこの島のどこにいるのかわからなかったアンセルは、ジスレーヌなら知っているかもしれないと考え、一緒に探してもらったという次第だ。いずれ彼女にも聞いてもらわねばならない内容でもある。
「そうですね……」
クラムジーは、自分が直接体験して感じたことなどを話した。
それから、同席しているインガリーサとカサンドラのことを紹介した。
「リモス村のマテオの方々はお元気ですよ。伯爵にも、ご安心くださいとお伝えしてくださいね」
インガリーサは、マテオ民が支援の手を必要としなくなるまで助力する考えでいる。
「何か不足しているものはありますか?」
クラムジーが尋ねると、アンセルは静かに首を横に振る。
「言えば切りがありませんから。住民達の救出が続けられていることが一番です。あなた方の努力のおかげです」
「そう言っていただけるとありがたいです。私は、変わり身の早い裏切り者と思われても仕方ありませんので……」
自嘲するように言ったクラムジーに、アンセルは首を傾げた。
マテオ・テーペにいた頃、クラムジーは平民でありながら伯爵の下に出仕していた。そのため、一部の平民からはやっかみもあり敵視された。その後、帝国では継承者の一族になることを選び、宮廷に仕えている。
今のところ、冷たい目を向けられることはないが、人の心などわからない。
多少なりとも気になっていた。
それに対し、ジスレーヌが憤慨したように言った。
「そんなこと、誰にも言わせません! クラムジーさんは、堂々としていればいいのです!」
「私も、あなたを裏切り者だとは思いません。アシルもそうでしょう。今の成果を思えば、よくやったと感謝するはずです」
アンセルもジスレーヌに同意する。
カサンドラも、何度も頷いていた。
これからも頼みます、とクラムジーやインガリーサ達に挨拶をして、アンセルはあづま達がいるところに戻って行った。
一息吐いたクラムジーの袖を、カサンドラが控えめに引いた。
「お茶とお菓子、おいしいね。マルティアさんと同じ、やさしい味」
「……」
「インガリーサさん、少し、席外します」
カサンドラは会釈して行ってしまった。
すると、他のメンバーも友人知人の顔を見に、それぞれ散って行った。
気づけばその場は、クラムジーとマルティアだけになっていた。
カサンドラは発破をかけたのだろうかと、クラムジーが考えていると、マルティアが声をかけてきた。
「お茶とお菓子は、口に合ったかな? 甘さが足りないとか……」
「いえ、ちょうどいい具合でした。お互いが喧嘩しないように、バランスも良く」
「よかった。クラムジーさん、何だかソワソワした感じだったから、もしかして忙しいのに無理して来てくれたのかな、なんて思ってて……」
「そんなことはないです。マテオの様子も知れて、来てよかったと思っています」
「うん……あの、お花見は楽しかった? 私は、クラムジーさんとこうしていられて楽しいから、もし同じ気持ちだったらいいなって。そうだったら、嬉しい」
クラムジーを見るマルティアの頬は、ほんのり赤かった。
つられてクラムジーの顔も熱くなっていく。
クラムジーは、軽く咳払いをしてから口を開いた。
「今日はとてもいい天気で、陽射しを浴びた花も海も綺麗に輝いています。こんな日を一緒に過ごせて、私も嬉しいと」
「そっか。同じ、だね」
マルティアは心から嬉しそうな笑顔になると、ようやく確信できた想いを告げた。
瞬間、クラムジーは、言葉では表現できないような気持ちでいっぱいになった。
マテオ・テーペにいた頃から秘めていた想いが叶ったのだ。
拒否するなどという選択肢はない。
返事を、と口を開けたが何故か言葉が出てこない。
宮廷で説明を求められた時は、きちんと論理立てて話せるのに。
ただ一言、自分も好きだというそれだけなのに、舌が動いてくれない。声を出そうとすると、胸の奥や喉がキュッと狭くなったように詰まってしまう。
マルティアの顔が不安そうに曇った。
クラムジーは、とっさに彼女の手を握った。
両手で包み込み、ようやく何とか一言だけ絞り出した。
「私も、です」
安心したマルティアが喜びの笑顔になると、すっかり強張っていたクラムジーの全身から力が抜けていき、穏やかな満ち足りた思いが満ちていった。
きっと今の自分も、マルティアと同じように笑顔なのだろうと彼は思った。
振る舞われているお酒を一口飲み、きらめく花々を眺める。
ほぅ、と息を吐き、アウロラ・メルクリアスは今日までの日々を振り返った。
あれから四年間、アウロラはリモス村の発展に力を尽くしてきた。
始めは本土で仕事を探すのがいいかと思ったが、その前に救出されたマテオ民が最初に着く場所を安心して暮らせるようにしようと考えるようになった。
思い返してみると、帝国に来たのもそんな思いがあったからだった。
ずっと走り続けてきたから、今日くらいはゆっくりしようかと思い、この島を訪れた。
やさしい花の香りとそよ風に癒されていると、カサンドラ・ハルベルトの姿を見つけた。
「おーい、カサンドラちゃん!」
と、手を振って呼ぶと、彼女もアウロラに気づいて笑顔になり駆け寄ってきた。
「アウロラさん、やっぱり来てた、ね」
カサンドラもこの四年間で変化があった。
前は言葉に詰まるようなたどたどしい話し方だったが、今はだいぶ改善されてきたのだ。
本土に戻ってから、いろいろなことに積極的に取り組むようになったからだろう。
カサンドラはアウロラの隣に腰を下ろすと、彼女が飲んでいるのがお酒であることに気が付いた。
「去年から飲める年になったからね」
「そういえば、そうだったね。私は、あと少し。成人したら、一緒に飲みたいな……」
「いいね。朝まで呑んじゃう?」
「え、えぇ?」
目を丸くするカサンドラに、アウロラはクスクスと笑った。
「街はどう?」
「うん……この前、お兄様と一緒に、チャリティーイベントを企画したの。スヴェルの人達も、協力してくれて……少しは、街のみんなの役に立てた、かな。そうだったら、嬉しい」
四年で街もだいぶ発展して人口が増えた分、足りない物も増えた。生活が不安定な人も、職が定まらない人もまだまだいる。そういった人達の支援のために、カサンドラは兄と協力して何度かチャリティーイベントを催してきた。
「アウロラさんは? リモス村も、賑やかになったって、ジスレーヌさんのお手紙にあった」
「うん。不作の年とか喧嘩とかもあったけど、畑も大きくなったし他のいろんなことも工夫してみんなで乗り越えてきたよ」
「今度、遊びに行く、ね」
「ぜひ来て」
笑顔を交わし合った時、少し強く風が吹き花びらが舞った。
美しい光景に、二人は魅入った。
「ところで……」
と、これまでの調子とは違った声音になったアウロラが、ニヤニヤと探るような笑みを浮かべてカサンドラの顔を覗き込む。
「彼……ユリアス君とは最近どうなの?」
カサンドラはピクッと肩を揺らすと、みるみる顔を赤く染めていった。
「え、えと……お仕事が、お休みの日とか……休憩時間の時、とか……」
すっかり照れてしまったカサンドラは、まるで四年前のようなしどろもどろな口調になり、最後のほうはもごもごと尻すぼみになっていた。
アウロラはやさしく微笑みかけ、頭を撫でた。
「ちゃんと会ってるんだね」
カサンドラは真っ赤になったまま頷いた。
カサンドラの顔の火照りが落ち着くのを見ると、あまり長いこと時間をとらせても悪いからと、アウロラは彼女を送り出した。
幸せそうでよかったと、小さなその背を見送る。
それから、
――私もそろそろいい人探そうかなぁ。
と、花びらが舞う青空を見上げるのだった。
兄がハルベルト家に婿入りしてからは、タチヤナ・アイヒマンがアイヒマン家の当主となった。
また、スヴェルでの活動も継続している。
四年前はまだ不安定だったグレアム・ハルベルトの精神もだいぶ安定し、周囲の後押しもあってスヴェルの団長に復帰していた。
タチヤナの彼への想いは残っているけれど、友として頼ってもらえたらそれで嬉しいと今は思っている。
これから先も、何が起こってもグレアムを大事に想う気持ちは変わらないからだ。
スヴェルに花見の話が来た時に団員達を送り出そうとしたグレアムも誘い、タチヤナはオアシス島に立った。
やさしい色の花々が咲く眺めに、二人はしばらく見惚れた。
それからタチヤナは顔を輝かせて言った。
「グレアム団長、今日はお仕事のこととか全部忘れて、思い切り楽しみましょう!」
「そうしましょうか。では、さっそく何か飲みますか? 確かポワソン商会がお酒や肴を出しているはずです」
おいしいお酒と海産物で作られた肴、そして美しい花々に、二人は心身共に癒されていった。
のんびり食事をした後は、島に咲くさまざまな花を見て回った。やわらかい日差しを浴びて、キラキラと輝いて見える。
途中、ちょっとした広場で子供達が駆けまわっているのを見かけた。
「かわいいなぁ! よーし……子供達と一緒に、童心に戻って遊びましょう!」
「え、タチヤナ?」
グイグイと腕を引っ張られて、戸惑いの声をあげるグレアム。
「みんなー、お姉さん達も混ぜて~♪」
タチヤナの声に子供達が振り返り、二人はあっという間に囲まれた。
そして定番と言うべきか、タチヤナは『お兄さん』に間違われるのである。
「おねーちゃんは、どこー?」
「かくれんぼか~?」
「それとも、おにーちゃんがおねーちゃんかー?」
たしかめろー、と子供達がタチヤナの服を引っ張り始める。
「その人は、ちゃんとお姉さんですよ……あぁっ、そんなに引っ張ったら伸びてしまいますから……」
慌てたグレアムが止めに入るが、すると今度は彼が標的にされてしまった。
きゃあきゃあと笑いながら、グレアムの背中に飛び乗ろうとする子もいる。
花が綺麗な島へのお出かけで、子供達はかなりはしゃいでいるようだ。
グレアムはすっかり子供達に翻弄されていた。
滅多に見ることのない慌てる様子に、タチヤナはクスクスと笑う。かわいいと思ってしまったのは内緒だ。
集まってきた子供達の中には、タチヤナの兄であるアレクセイの息子、ヴァレリーもいた。
タチヤナがその子の前にかがんで手を挙げると、二人て仲良くハイタッチを交わす。
「今日も元気でよろしい!」
タチヤナがヴァレリーの頭をわしゃわしゃと撫で回すと、彼はキャラキャラと楽しそうに笑った。
ようやく子供達から解放された時には、グレアムはすっかり遊び疲れた顔になっていた。
それを目にしたタチヤナは、また笑みをこぼしてしまった。
「子供のパワーって凄いですよね! 兄様の子と過ごしていて、常々感じているんです。その無垢な明るさに救われることも本当に多くて……」
だからグレアムも子供達と触れ合って童心に戻って、それでパワーを充填できたらいいと、タチヤナは思ったのである。
はたして彼はどうだっただろうかと、顔を覗き込むと、グレアムは晴れ晴れとした顔をしていた。
「何だかとても、すっきりした気分です。タチヤナの言う通り、あの子達から元気をもらったようですね」
「それならよかったです!」
タチヤナは嬉しくなり、心からの純粋な笑顔になるのだった。
子供達の輪から外れて、一人でしゃがみこんで何かを熱心に観察している子がいた。
名前はベリル・スオウ。
四年前の氷の大地の決戦で命を落としたリベル・オウスの生まれ変わりである。
偶然か何かの悪戯か、目つきの悪さはリベルによく似ており、また植物には特に関心が強いところも同様であった。
もっとも、ベリル自身も両親も魂の事情など知るところではないので、これも個性と親達は我が子を見守っている。
ふと我に返ったように顔を上げたベリルは、一緒にいたはずの父と母の姿が見えないことに気づいた。
目に入る草花を追ってうろちょろしているうちに、はぐれてしまったようだ。
しばらく呆然としていたベリルだったが、まあいいや、と軽く流し、それよりももっとおもしろそうな植物を求めて探検に出るのだった。
その時、植物ではない――なぜかとても心惹かれる人を見かけた。
吸い寄せられるようにその人の前に回り込み、じっと見上げる。
知っている人ではない。
それなのに。
「あ、あ、うあああ~ん!」
どうしてか胸が震えて、大きな声をあげて泣いてしまった。
目の前のその人――ベルティルデ・バイエルは、びっくりした顔をして腰を落とし、ベリルと目線を合わせた。
「どうしましたか? もしかして、お父様やお母様が見えなくなってしまいましたか?」
ベルティルデはベリルを泣きやませようと、ハンカチで涙を拭う。
「わたくしと一緒に探しに行きましょうか。きっと、すぐ近くにいるはずですよ」
ベルティルデはやさしく微笑みかけると、ベリルを抱き上げた。
そして歩き始めてたいして時間もかからないうちに、ベリルの両親は見つかった。
向こうもいなくなったベリルを探していて、無事だったとわかると母親は安堵して我が子を抱きしめた。
「見つかってよかったですね、ベリルさん」
頭を撫でて立ち去ろうとしたベルティルデを、ベリルは追いかける。
母の止める声が聞こえたが、足は止まらなかった。
とてとてと、まだ覚束ない足取りで追うと、気づいたベルティルデが振り向いた。
ベリル自身、どうして泣いてしまったのか、どうしてこんなにも気になって仕方ないのか、理由はさっぱりわからない。
わからないからこそもっと一緒にいたいと思い、離れがたくなっていた。
「あの、しばらくご一緒させてくださいませんか?」
ベリルの一生懸命な目に負けたのか、ベルティルデが両親に申し出た。
両親も頷いたので、ベリルはもう少しの間、ベルティルデと遊べることになったのだった。
今度は二人で草花を観察する。
ベルティルデは、花や草木の名前をいろいろ知っていた。
「植物にとても詳しい方がいらしたのです」
そう言って、少し寂しそうに笑った。
それからどれくらいの間、一緒に花や草木を見て回っただろうか。
ついに家に帰る時間が来てしまった。
やっぱりベリルは、ベルティルデともっと一緒にいたくて、その場に立ち尽くしてしまう。
けれど、彼女を困らせたくはないので渋々今日の別れを受け入れた。
「また今度、お話ししたい」
『次』を求めると、ベルティルデは喜んで約束をしてくれた。
「ええ。また一緒に遊びましょう。わたくしはリモス村にいます。よかったらお手紙くださいね」
ベリルは嬉しくなって手を振ってお別れした。
両親と手を繋いで歩くベリルの足取りは、まるで下手くそなダンスのステップのようだったとか。
「何だか少し……似ていましたね」
小さな後ろ姿を見送りながら、ベルティルデは懐かしそうに呟いた。
オアシス島の花の景色は、ユリアス・ローレンに過去の思い出を彷彿とさせた。
「綺麗ですね。昔、リモス村でもお花見をしましたよね。懐かしいです」
やわらかな表情でそう言ったユリアスの隣で、カサンドラ・ハルベルトもその時を思い出していた。
「あの時の木、だいぶ大きく、なったのかな」
「背は伸びたと思いますよ」
二人とも今は本土で暮らしているため、美しい花をつけていた当時の木がどうなったのかは知らない。
しばらく目の前の美しさをただ感じた後、ユリアスが口を開いた。
「前に、誰かの役に立てるような、誰かを笑顔にできるような、そういう人になりたいと言っていたことを覚えていますか?」
カサンドラは静かに頷く。
その目標は、今も変わらない。
兄のグレアムと共にチャリティーイベントなどを企画してきたが、カサンドラはまだまだだと思っている。
表情をやや硬くした彼女を見て、ユリウスはカサンドラの思いを察した。
けれど、彼にとっては。
「カサンドラさんは、ずっと前から誰かを笑顔にできる人になれてますよ」
そう告げると、案の定カサンドラは「それはないと思う」と首を横に振る。
だからユリアスは、ゆっくりとした口調で自分の思いを伝えることにした。
「僕は、あなたの笑顔を見ると心が温かくなります。こうして一緒にいると、嬉しくて幸せです」
そう言って、ユリアスは本当に幸せそうに微笑む。
まっすぐに褒められたカサンドラの頬は、みるみる赤くなっていった。
ユリアスは、彼女には幸せになってほしいとずっと願ってきた。
その願いはいつしか、ユリアス自身でカサンドラを幸せにしたい、彼女と一緒に幸せになりたいという強い思いに変わっていた。
カサンドラと付き合い始めてから――もうそろそろ、いいだろうか。
「カサンドラさん、愛しています。僕と結婚してください」
カサンドラは大きく目を見開いた。
ユリアスは、彼女の手を取ると『約束の証』を薬指に嵌めた。
「あなたと一緒に生きていきたい。公爵に認めてもらえるようにがんばります」
「私で、いいの……? ユリアス君のこと、私も、好き……とても、大切。でも……」
「僕が幸せにしたくて、一緒に幸せになりたいと思っているのはあなたです」
はっきりと言ったユリアスに、カサンドラは安心と喜びで涙で目を潤ませた。
指輪が光る左手を、大事そうに右手で包む。
「ありがとう、ユリアス君。私も、一緒に幸せに、なりたい」
花のように微笑んだカサンドラを、ユリアスはそっと抱き締める。
そして、やさしくキスをした。
「あの、ちゃんとした指輪は後で贈りますね」
「ありがとう。でも、この指輪も、大切にする、ね。それで……その、今度、お父様に会ってくれる……? ユリアス君とのこと、お父様に伝えてあるけど、まだ、会ったことない、よね」
カサンドラはユリアスには言っていないが、付き合い始めた頃にはもう公爵に彼とのことを話していた。
カサンドラの予想通り、公爵は渋い顔のまま黙り込んでしまい、その話はそれきりになってしまった。
けれど、付き合いをやめろとは言わなかったし、ユリアスに対して何らかの手段に出ることもしなかった。
今、カサンドラがこう言ったのは、公爵が最近のユリアスの評判を耳にしたからである。
ユリアスは、町医者のもとでずっと手伝いと勉強を続けてきた。
誠実な人柄もあり、けっこう評判が良いのだ。
だから、公爵も会ってみようという気になったのだろう。
ところでユリアスは少し前に、師事していた町医者からそろそろ独立してもいいと言われている。
結婚が叶う日はまだ先と思われるが、家族になれる未来は確実に近づいていた。
かつてスラム街と呼ばれて皇帝暗殺を企てた武装勢力や海賊の温床となっていた区画は、この四年間ですっかり再開発され、集合住宅やさまざまな店舗が立ち並ぶ明るい場所へと変貌を遂げた。
そのスラム街の住民達の支援を初期の頃から積極的に行い、その後も中心となって活動を続けてきたのがルティア・ダズンフラワーである。
帝国騎士としての任務やスヴェル団員としての依頼をこなす多忙な日々の彼女だが、今日だけはグレアム・ハルベルトと花見をしてのんびり過ごすことにした。
実はルティアにはもう一つ目的がある。
それは――。
「あ、いらっしゃいましたね」
少し向こうに、マリオ・サマランチの姿があった。
ビルやダリアと楽しそうに笑い合っている。
「陛下に用事が?」
「ええ……けれど、親子水入らずのところに割り込むのは気が引けますね」
「大丈夫だと思いますよ」
グレアムはそう言うと、ルティアの前に立って歩きマリオに声をかけた。
顔を向けたマリオは、笑顔で二人を迎えた。
魔力を統べる王となった今のマリオは、セラミスの精神と一つになったマリオである。
「何となく会える気がしていたよ。久しぶりだね」
「お久しぶりです、陛下。ビル様もダリア様も。ご家族で歓談中のところ失礼いたしま……」
「堅苦しい挨拶は抜きにしよう。それより、グレアムを連れて来てくれたんだね」
嬉しそうにするマリオを、グレアムは呆然とした顔で見ていた。
見た目はマリオなのだが、その中に確かにセラミスを感じたからだ。
彼はセラミスに関する記憶が欠落してしまっていて、そのことをひどく悩んでいたものの、この四年の間に少しずつ思い出してきていた。
しかし、あと少しのところがどうしても思い出せずにいたのだが……。
「姉様……ですか?」
グレアムの様子から最後の記憶のかけらを取り戻したのだと、ルティアはわかった。
そのことは同時にグレアムの中にある罪悪感を刺激することになった。
顔色を青くし強張ったグレアムの額を、マリオは軽く叩いた。
「何て顔をしているんだい。いつまで後ろを向いている? 君が見るべきものは、前にしかないよ。……それとも、実は後ろに目があるのかな」
「そんなわけないでしょう……」
後頭部を確かめようとするマリオに、グレアムは苦笑した。
それからグレアムは、とても穏やかな笑みでマリオを見ると、
「もう、大丈夫です」
それだけ伝えた。
マリオも満足そうに微笑んだ。
その笑顔の向こうに、グレアムは慕っていた姉の微笑みを確かに見た。
そして今、サマランチ親子とグレアムは、ルティアが拵えた果実入りパウンドケーキで花見をしている。
実はルティアは四年前の支援活動の時に、自分には料理のセンスがないことがわかってしまった。その後、特訓を続け今日に至る。
「まだまだ練習が必要です……お恥ずかしい」
広げてみたはいいものの、ルティアはとたんに顔を赤くした。
「いいえ、とてもおいしいよ。君に指導した人も喜んでいるだろう」
マリオがにっこりして褒めた。
ビルとダリアも「おいしい」と頷いている。
もちろんグレアムも。
「捕まえておかなければと思われるくらいの女になれそうですか?」
軽い口調でそんなことを言うルティアに、グレアムは目を丸くする。
それから表情を改めて、ルティアは願いを口にした。
「グレアム様がお嫌でなければ、これからもお傍にいさせてください。貴方が嬉しい時は一緒に笑いたい……苦しい時は羽を休める木陰になりたいのです。どうか負担に思わないで……貴方の力になりたいのは、私の心からの願いです」
言ってからルティアはハッとした。
ここにはマリオ達もいるのだ。
マリオはおもしろそうに見ているし、ビルは真っ赤になっており、ダリアは何となく尊敬の目をしていた。
そして、グレアムは――固まっていた。
少ししてやっと口を開いて出てきた言葉は、いまいち要領を得ないものだった。
「すみません、姉様のことを思い出してから……実は少し変な感じになっていまして……あ、悪い方向ではないです。こういうの、何て言うのでしょうか……浮かれている、と言ったらいいのか……ふわふわしているというか……」
グレアムは、ようやく動き出した心の時間に戸惑っていた。
ルティアはそんな変化をやさしく見守るように微笑んだ。
他の島に行くのが初めてで、その島が綺麗な花でいっぱいだったことにフェリシアは大はしゃぎであった。
「あれは何? これは?」
と、目に入るものすべてに興味を示し、顔を輝かせて父と母に聞いている。
「ちゃんと前を見てないと転んで……あ」
父親のセルジオ・ラーゲルレーヴが言った傍から、フェリシアはペシャッと転んでしまった。
「大丈夫?」
慌てて母親のミコナ・ラーゲルレーヴ(ミコナ・ケイジ)が駆け寄って抱き起こすと、フェリシアはけろっとして笑っていた。
その顔はミコナによく似ている。
そしてミコナのお腹には二人目の子が宿っていた。
セルジオとミコナはあれからリモス村に開いた食堂兼弁当屋を営む傍ら、アトラ島との交易にも携わっていた。
前々から果樹園を作りたいと望んでいたジスレーヌからは、積極的に種や苗の仕入れを依頼された。
本土とも交易は行われ、環境が違う土地にも根付くように手伝いをしている。
今日は親子だけではなく、セルジオの親友ともう一人と合流する予定だ。
二人はすぐに見つかった。
「よぅ」
と、手を挙げるマティアス・リングホルムの隣には、彼を通じて交流するようになったルース・ツィーグラーが立っていた。
フェリシアが体当たりをするようにマティアスにくっついた。
ミコナが慌てて離そうとしたが、フェリシアは遊んでいる感覚なのか、笑いながらマティアスを盾にして母の手から逃れている。
ミコナは困り顔でマティアスに謝った。
「ごめんなさい、マティアスさん。ここに着いてから、ちょっと興奮気味なんです」
「いいよ。この子は見てるから、準備のほう頼む」
笑って言ったマティアスに、ミコナも安堵した。
手伝うわ、とルースが花見の準備に加わった。
三人でやればあっという間に場は整い、ミコナが作ってきた弁当がいくつも並べられて、彼らの目を楽しませた。
「そういや、おじさんは来なかったんだな」
「村でのんびりしてると言ってました」
聞いてきたマティアスに、セルジオは苦笑して答えた。
セルジオの両親はマテオ・テーペにいて、ここ数年の間に救出されたのだが、再会したのは父親一人だけだった。
母は体力がもたずに亡くなっていたのである。
マテオ・テーペにいた頃、セルジオの父親とは折り合いが良くなかったものの、マティアスは彼の両親のもとに身を寄せていた。
「リモス村も、人が増えてどうなることかと気がかりもあったが、お前のとりなしでだいぶ助けられてる……さすがだ」
「何ですか急に。何か欲しいものでも?」
「いや、そうじゃなくて。お前のとこの食堂、少し手狭になったと思ってな」
マティアスにルースも頷いた。
「マテオの人達が増えたものね。流刑囚も変わらず来てるみたいだし」
マテオ民と流刑囚の居住区は分かれているが、往来に厳しい制限はない。
もし流刑囚側がマテオ民に危害を加えるなど問題を起こした場合、重い刑罰が科せられることを流刑囚達は充分心得ているからでもある。
また、流刑囚の顔ぶれが変わっても、彼らとマテオ民はもともと共同で生活をしてきたという基盤があった。
双方をまとめているインガリーサやジスレーヌの仲が良好であることも影響している。
「店を拡張する気はねぇか?」
「そうですねぇ」
セルジオとしては、ゆくゆくはどこかに自分の土地を持ち、そこで育てた野菜や果物を使った食堂のようなものを経営したいと思っている。
また、リモス村や燃える島の開拓で生きていく人達が暮らしやすい環境を作っていく活動も、続けていきたい。
とはいえ、目の前の問題として、今の店が手狭になってきたのは事実だった。
うーん、と考えていた時、フェリシアがにゅっと二人の間に顔を出した。
「あのね、パパはもう結婚してるからフィアとできないみたいなの。だから、まだ結婚してないマティアスと結婚してあげるね」
と、ニコニコしながらマティアスに言った。
ルースとおしゃべりをしていたミコナは慌てている。
「お前が大きくなっても俺が一人だったらな」
と、マティアスがフェリシアの頭を撫でながら返せば、彼女は嬉しそうに笑った。
「へぇ、やさしいのね、マティアス」
と、ルースがからかった。
ところで、マティアスとルースの関係はこの四年間であまり変化はしていない。
ルースがやりたい計画があると言うと、マティアスが力を貸すという感じでリモス村で働いてきた。
しかし、今日はその関係が変わるかもしれない。
おいしい弁当を存分に味わった後、セルジオ達は島の散策に出掛けていった。
残ったマティアスとルースは、眠気を誘うような暖かさの中でゆったりと花を眺めている。
風に舞う花びらを目で追いながら、マティアスは考えていた。
ルースとベルティルデはどちらも魔力を手放し、人間になることを選んだ。
そして、入れ替えていた名前も返し合い、主従だった関係も解消した。
今では家族のような関係だ。
だからこそ、マティアスは一歩踏み出す気持ちになれた。
村へ戻れば二人きりになれる機会はあまりない。
行動に出るなら今だ。
「なあ」
「何?」
「俺と一緒に暮らさないか?」
「!?」
言ってから、一歩どころじゃなく踏み込んでしまったことに気づくマティアス。
しかし、今さらやり直すこともできず。
隣のルースを見れば、表現しがたい顔になっていた。
ぎこちない空気が流れた後、突然、ルースが吹き出した。
「まさか、いきなりそう来るとは思わなかったわ」
「いや、まあ……」
「私から言おうかなって思ってた。そうしないと、一生このままじゃないかと思ったし……フェリシアに先越されちゃうかなとか」
ルースは先ほどのフェリシアの発言を思い出して、クスッと笑った。
「今までありがとね。それと、これからもよろしくね」
照れて少し赤くなったルースの手が重ねられた。
「珍しい素直なルース……いや、ベルと呼ぶべきか?」
「そこなのよね。入れ替えてた名前のほうが通りがいいのよ」
「じゃあ、二人だけの時は元の名前で」
マティアスの提案をルースは受け入れた。
二人は重ねた手の温かさに心を和ませながら、微笑みを交わし合った。
船で待機していたレイニ・ルワールを、一人の女性が訪ねてきた。
マテオ・テーペで港町の住民達のまとめ役の立場にある、リルダ・サラインだ。
「来ていたのね。話は聞いているわ。そちらのこと直接助けられなくてごめんなさい。ありがとね」
「とんでもない。いつも助けてもらっているわ」
甲板で花見をしているレイニにリルダが近づき、巻いた紙を差し出した。
「これ、どうしても私の手であなたに渡したくて」
紙を広げてみると……そこには、世界の図が描かれていた。大洪水前のものだ。
港町から出航した船にももちろん地図はあったが、それよりも克明に、情報が記された地図。
「高地で、早めに確保しなければいけない場所――鉱山」
「炭坑」
二人の言葉が重なり、頷き合い、話し合っていく。
「それから……謝りたいことが。娘さんのこと、ごめんなさい。私が別の船に行くように仕向けたようなもの」
リルダの言葉を、そんなことはないとレイニは否定しなかった。強い瞳で「うん」と受け入れた。
「私たち凄いでしょう。世界中が水に飲まれたというのに、生き延びたんだもの。もちろん私は私だけの力で成し得たわけじゃないし、あの子がどれだけ貢献したかも定かではないけど」
それでも、多くの人の命を救い、導く力となったことは事実。
レイニと娘が同じ船に乗っていたら、その船に乗っていた人しか助からなかったかもしれない。
「あなたもね。相当無理をしてるでしょう? 次の船には乗るのよね」
「支えてくれる人がいるから」
リルダは側で力になってくれている大切な人――トモシ・ファーロのことを思い浮かべた。
「残っている町の人全てと、そして彼と一緒に乗るわ」
「そう、大切な人がいるのね。私にもいるの。夫と、息子」
「そうなのね」
顔を合わせて、弱く微笑み合った。
そして……。
「またこの、温かな光と、幸せがあるれるこの地で会いましょう」
二人は握手と抱擁を交わして、別れた。
セラミスと同化し、全ての魔力を統べる王となったランガスもまた、つかの間の再会を喜び、一時の交わりを楽しんだ後。
世界の魔力を調整し、人間と精霊が生きれる世界を造りに旅立った。
人と精霊の共存。人は魔力と自然を畏れ敬い、平和と繁栄を目指していく。
そんな、理想の未来を築くために。
●個別連絡
ラトヴィッジ・オールウィンさん
サーナと結婚してくださり、ありがとうございます。
姓はサーナの姓で良かったでしょうか? あと、なったとは本文に書いてないのですが、一族になったと考えていただいて大丈夫です。
アレクセイ・アイヒマンさん
チェリアですが、あれからすぐに子供をとはならないと思うので、子どもは1歳児(単語が喋れるくらい)くらいをイメージして書きました。
小さな頃は昔のチェリアに似て、人見知りをする子とさせていただいたのですが、気丈な男性に成長していくものと思います。
チェーザレ・アジャーニ(コルネリア・クレメンティ)さん
父と似たところがないと、家臣にホントにエクトルの子? と疑われそうなので、成長するにつれ父親に似てきたとかそんな感じでお願いしますー。
将来はどこかの土地を治める領主となること確定ですが、場合によっては山の一族のところへ婿入りさせられる可能性も!?
ナイト・ゲイルさん
ナイトさんのシーンで、アゼムについて書かせていただいていますが、こちらシナリオ等で彼と接触してほしいという意味ではございません。
ダウンロード企画用のシナリオにご参加いただける際には、気にせずナイトさんのやりたいことをされてください。
本当に色々とありがとうございました。
トモシ・ファーロさん
箱船の行き来に必要なエネルギーの問題は解決できているような気がします。
トモシさんの未来も、続いていくものと思われます!
お名前だけとなりましたが、ご参加ありがとうございました。
お陰で大切なシーンを1つ書かせていただけました。
●マスターより
【川岸満里亜】
***より上と、最後の船のシーンを書かせていただきました。
状況説明等の必要と思われるシーンのために、関連PCにつきましてはアクション外の描写が入っていますが、お許しください。
小さな子いっぱいで、ほんわかしました。イラストもとっても楽しみです!
マテオ・テーペの状況ですが、「最終回後にエクトルが箱船に乗船し、その際技術交換等のやりとりがあったかもしれない」「魔石がレイニの手に渡っている」そして四年間のクラムジーさんの働きかけもあり、箱船が行き来する際のエネルギーの問題までは解決できているのではないかと思われます。
つまりその方法で箱船の行き来が行われるようになってからは、命を落とす人が激減しており、神殿で最後の箱船を送り出す水の魔術師たち以外は助かる見込み、と思われます。
他にも地上にいる人々との協力で神殿の魔法具に関する開発や、神殿そのものを浮上させる計画など……何か行われている可能性もあるとは思います。
カナロ・ペレアのファイナルの書(仮タイトル)の制作の計画をしており、こちらで本編に沿った不確定な未来シナリオを行わせていただく予定です。
こちらはカナロ・ペレアに登録しているPCのみ、ご参加いただけるシナリオとなりますが、ノベルのご注文は後日談以降のシナリオに参加してくださったPCもご注文いただけるようにしたいと思っています。是非最後まで楽しんでいただけましたら幸いです!
※イラスト公開後
成長した皆様の姿、花見や親しい人たちとの歓談を楽しむ姿に、ホント感動しきりでした。
素敵なイラストへのご協力、ご参加誠にありがとうございました!
【冷泉みのり】
こんにちは、冷泉です。
後日談へのご参加ありがとうございました。
これから花の季節が近づいて来て、一年の内でとても綺麗な時期になりますね。
一足早いオアシス島のお花見をお楽しみいただけたなら嬉しく思います。
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から