ワールドシナリオ前編
『深淵の眼差し かげろうの蒼』第4回
第1章 ゴーレム試作機、起動! と、これからの開発
ゴーレムの試作機を見上げるマーガレット・ヘイルシャムの表情は、周りにいる製作関係者達とは違っていた。
(一体造るのにこれだけ人員と時間とコストがかかっていると、量産までは遠そうですね)
どこか愛嬌のあるずんぐりした体型のゴーレムをぼんやりと見上げていると、研究者の一人に声をかけられた。
「何か気になることでもあったか?」
「いえ……ゴレームに関しては何も。他のことを考えておりました」
「他のこと?」
頷いたマーガレットは、物資運搬に特化したゴーレムの案を話した。
「一体で多目的に使える人型ゴーレムは確かに理想ですが、それ故に構造が複雑になってしまいます。そこから無駄も生まれましょう。そこでもし、目的を物資運搬に限定するならば、腕や頭はいりませんよね。移動も車輪で充分かもしれません」
「できることは減るが、その分いろいろと浮くわけだね」
「ええ。関節の数を減らすだけでも必要な魔法具の数も減り、製作時間とコストを大きく下げられると思いますわ」
「ふむ……まあ、そうだね。たとえばとても重い物を運べる台車とか。台車そのものはたいして時間もかからない。魔法具にかかる時間は変わらんがね。いいね。重い物を運ぶ機会などたくさんあるだろう」
研究者は、次の製作計画項目に『台車』を加えた。
と、そこにマーガレットとはまた違った色白の指先が、にゅっと割り込んできた。
少し驚いて顔を上げた研究者に、リュネ・モルが笑いかけていた。
「重い物関連で私からも一つ」
「どうぞ」
「崖で行われた魔導船などの昇降を、風車にクレーンとウィンチを付けた設備で代用しませんか? 軽い漁船くらいなら、人力でいけると思いますよ」
「……重たい物は?」
「魔法や魔法具でしょうね」
研究者は宙に視線をさまよわせて考え始めた。
「ふむ、人力で動かすならそんなに時間はかからずに出来上がりそうだ」
「4基もあれば、箱船の上げ下ろしも可能でしょう」
「箱船ね……マテオの人達は、あの船を戦場に出すのは嫌なんじゃないのかい? あ、いや、私の想像だけどね」
研究者の発言に、リュネは曖昧な微笑だけを返した。
「……つまらないことを言ったね。設備の設計の話をしようか」
研究者は苦笑して話題を変えた。
と、そこに「ちょっと待って」とフィラ・タイラーが加わってきた。
「わたしからも、一つ」
「どうぞ」
「魔導船の改造です。舵やマストでの作業の一部をゴーレム化することで、船員達の負担を軽減できますし、人員削減も可能かと」
「ああ、マストね。帆の上げ下げを自動化できたら助かるだろうね。操作はやはり人の手になるだろうけど」
「幽霊船とか海賊とか、帝国の魔導船も強化が必要と思ったんです」
「そうだね。……よし、これも加えよう。う~ん、忙しくなるぞ」
セリフとは逆に、研究者は楽しそうだ。
(結局、マテオ・テーペの人達も最終的には自国の都合を優先するだろうし、いざという時に、箱船に対抗できる戦力は保持しておかないとね)
フィラがこのようなことを考えていたなど、誰も知らない。
その後、ゴーレム試作機の試運転準備が整ったという知らせが来た。
「もうできたのか。ここにいると運び出しの邪魔になるね」
こうして搬出されていく試作機を見送った後、彼らは各案の設計などの詳細を話し合ったのだった。
試作機は荷馬車で運ばれた。
外からは見えないように帆布で覆い何頭もの馬で引いていく様は、街の人達から注目された。
崖上に到着し、その姿がお披露目されると騎士達やボランティアから感心と称賛が上がった。
そんな中、同行してきたリサ・アルマは冷静に研究者に話しかける。
「まずは何をさせるんだ?」
「移動だ。製作所内より広いここで、指示通りに動けるかを試す。やってみるか?」
研究者はリサに、試作機を動かすための魔法具を渡した。
手の中に収まるくらいの円盤状の魔法具である。
リサが指示を出すと、試作機は浮き上がり滑るように移動した。
移動に問題はなさそうだ。
その様子を研究者が観察し、結果を紙に書き込んでいった。
それから腕の動作の確認の後、地面の掘削を試した。
「悪くないな」
この時、崖の下では海獣との戦闘が行われていたのだが、研究者はまるで関心を示さなかった。
見物していた騎士からは、加勢を、という声もあったが、
「今日の計画にない」
と、にべもなく断っていた。
その時、リサがわずかな異変に気付いた。
「ぎこちないな」
「腕の関節だ」
「……ふむ。やはり関節は問題が出やすいか。いったん止めてくれ」
動作を止めた後、二人は試作機の点検をした。
わかる範囲で意見を出し合った後、試運転はここまでにすることに決まった。
「関節部の調整とパーツの重量も計算し直そう」
「敵に気づかれる前に撤収する。手伝ってくれ」
リサに頼まれた騎士達が手伝ったため、撤収作業は早くに終えることができた。
二人の見立てでは、重大な問題は発生していない。
後は製作所で調整を繰り返せば、来月には完成するだろう。
拠点がある崖上から海岸を見下ろすリキュール・ラミルは、カエルに似たのどかな容貌の裏で漁業再開までの算段をつけていた。
(まだ海賊や海獣がおりますね……。クレーンが完成し、舟や荷の昇降ができたとして……)
「せいぜいが準備といったところでございますな。本格的な漁はまだ先……」
もどかしいが、焦ってはすべてを仕損じる。
クレーンの完成は漁業再開への貴重な一歩だ。
さらに人力で動かす仕様のクレーンは、失業中の元漁師達への対策にも繋がるはずだ。
それからリキュールは、クレーン設置に伴う拠点周辺のインフラ整備について考えた。
これは後ほど、しかるべきところへの提案が必要な案件だ。
後で漁師達に不便がないように、リキュールは慎重に図面を仕上げていった。
と、そこに子供が呼びかけてきた。
「おっちゃん、そこどいて!」
顔を上げると、一輪車にゴミを積んだ子供がいた。よく働いているのか、顔も服も真っ黒になっている。
マシュー・ラムズギルがボランティアに誘ったスラムの子供で、彼の私塾の生徒でもある。
「お手伝いとは、感心でございますな」
リキュールが子供の進路を開けた時、どこからか子供を咎める声がした。
「道を開けてください、でしょう」
子供と視線を合わせて言葉遣いを正すマシュー。
彼もゴミの収集をしているのか、動きやすい服はあちこち黒くなっている。
バツが悪そうに言い直すと、子供は小走りに行ってしまった。
「ご迷惑をおかけしました」
「いえいえ、お気になさらず。元気の良い子でございましたな」
「まあ、それが取柄といいますか」
少し世間話をした後、マシューは作業に戻った。
リキュールのような態度は特殊な例だが、最近は騎士からの監視するような視線が少しはやわらいだように感じる。
連れてきた子供達が、ケンカも盗みも一度もしていないからか。
「センセー、遅いよー!」
「手伝ってあげるねっ」
マシューの周りに子供達が集まり、グイグイとその背を押す。
「疲れたなら休めばー?」
「いいえ、まだまだやれますよ」
「明日は筋肉痛かぁ?」
明るく笑う声に、マシューの口元にも笑みが浮かんだ。
第2章 幽霊船の戦い
波が舳先に当たって砕け、散った小さな水しぶきたちが、エンリケ・エストラーダをしっとりと濡らした。
「てめえら!」
エンリケは大声を挙げて、海賊の残党たちを一瞥する。
「このままでいいわけねえよなあ、やられっぱなしでよぉ」
張り詰めた空気。誰もが「YES」の答えを持ちながら、あえてそれを言うまでもないとする、熱い視線がある。
「ここに、海賊団の再結集を誓う!」
彼がそう言い放った瞬間、船体が引き裂けるほどの絶叫が響き渡った。
「俺が、頭になる。俺たちの底力、見せつけてやろうぜぇ!」
往時、50名ほどはいた海賊たちだったが、捕虜になったもの、投降したもの、そして海に散っていったものなどがいて、今やその人数は10名前後。燃える島に残っている4名と、今船に乗っている、エンリケを含めた6名。そして、『幽霊船』と化した元海賊船に1人で乗っている、バルバロ。
「数は少ねえが、少数精鋭だ! やってやんぞ!」
海賊たちは雄たけびを上げると、エンリケの指示通り、小舟に分散して乗り込み、帝国軍が襲来するのを待ち受けていた。
幽霊船の甲板で、バルバロは腕を組んで待っている。船は海岸の近くまで来たが、まだ接岸の機会を伺っている。いざとなったらどうとでもできる。一陣の風が吹き、バルバロの髪がなびく。口元に、怪しげな笑みが浮かんでいた。
帝国は、前回同様の小型魔導船で、幽霊船をめがけて進軍していた。帯同している箱船も同様である。
「ん~、あれかな~」
懲戒部隊として幽霊船に乗り込むことになっているトゥーニャ・ルムナ。だが、その表情は真剣でこそあれ、怯えているような素振りはない。眉の上に手をかざし、日の光を避けるように遠くを見つめる。
「あれって……」
よく見ると、見覚えのある格好の人間が、幽霊船の上から降りようとしていた。海の上には、海獣らしきものの背が見える。
「……」
トゥーニャはちらりと後ろを見る。あの格好は、おそらくバルバロだろう。どういうつもりかは分からないが、懲戒部隊としてやるべき行動は「相手の行動を阻害し、こちらの作戦を通しやすくすること」。
五指に意識を集中するトゥーニャ。頭の中に、ヴォルク・ガムザトハノフの声が聞こえてくる。その声に重ね合わせるように、技の名前を絶唱した。
「魔王流交殺法・風牙ッ!」
トゥーニャの指先からレーザーのように放たれた圧縮空気は、バルバロが乗ろうとしていた海獣を弾き飛ばす。バルバロは態勢を整えるために、幽霊船へと引き上げざるを得なかったようだ。
「わお、すごい威力~」
口ではそう言うが、バルバロに攻撃が直撃しなかったことを、トゥーニャは心の内で安堵した。小型魔導船は、いよいよ幽霊船に近付いている。
トゥーニャと数名が懲戒部隊として幽霊船に飛び乗った。が、海賊の姿はないらしい。全身に薄い風の層を纏ったトゥーニャは、注意深くあたりを見渡す。気配も感じられない。小型魔導船に目で合図をすると、突入部隊が準備を始めた。すぐに飛び出していったのは、ジェザ・ラ・ヴィッシュだった。
「大人しく投降せよ、海賊共!」
右手に帝国旗を持ち、勇ましい声を上げながら甲板を歩く。だが、人の気配はない。先ほどトゥーニャが引き上げさせたバルバロがどこかにいるはずだが、その気配も感じ取れない。
「帝国に恐れをなして隠れているのか! いっそ負けを認めてしまえば楽になるものを」
鼻で笑い、かつて海賊船旗が掲揚されていたであろうマストに、帝国旗を掲揚する。高々と上がり、風に揺れる旗。ジェザは余りのあっけなさに「ふん」と誇ったあと、腕を組んでさらに甲板を歩いていく。
「所詮賊は賊、正義の前に屈するほかないのだ」
突如、物陰から鋭く割れた金属片が、ジェザめがけて飛んでくる。ジェザは驚いて避けたが、服の一部が切り裂けている。肉体に傷はなかったようだが、布地の隙間から素肌が見えている。
「誰が正義だって?」
ゆらりと暗がりから姿を現したのは、バルバロだ。
「それじゃあ、私が帝国をぶっ潰して、こっちが正義だってことを証明してやるよ」
「敵発見! 突撃ぃぃッ!!」
ジェザは大声を張り上げながら、戦闘準備のために一度物陰へと入った。
慌てたのは、船内調査を行おうとしていたエルゼリオ・レイノーラと、船体保全を行おうとしていたルティア・ダズンフラワーだ。船室の奥に漂う黒いもやを払いながら進むが、どんどんと瘴気のような霧は濃くなっている。どう考えてもここから先に人間は進めないはずだ。だが、この闇に乗じて何かが出てきたときには、対処しきれない。
「進行方向、何か聞こえる?」
「いいえ。船内に敵の気配はないわ」
口元を布で覆ったルティアだが、エルゼリオの風の魔法で、霧を吸うことはほとんどない。2人が感知している通り、甲板の上では激しい争いの音がし始めていたが、行く手からは何も聞こえない。むしろ、深海のような冷たい静寂が広がっている。
「……あ、あれは……?」
ルティアが指差した先を、エルゼリオは風で払う。薄明りの中で、船室の壁の一部だけが、異なった色になっているのが見える。周りはすべて木で出来ているようだが、そこだけは、薄灰色の、何か柔らかそうなもので塞がれていた。
「穴が開いて、何かで塞いでいるみたいだね」
エルゼリオはそれを凝視する。表面が、びくんと動いた。
「ッ……!?」
2人は思わず身構え、それぞれ武器に手をかけた。だが、こちらに向かって攻撃してくるような意図はないらしい。
「……もしかして、海獣が穴を塞いでいるのでしょうか……?」
「そんな、そんなことが」
2人は少しずつその穴に近づいていき、海獣を刺激しないように、周りにある布や木材で、穴をできる限りふさいでいく。もちろん、海獣が少しでも離れていけば、数分もしないうちに浸水して、沈没の危機に直面するだろう。だが、その数分でも時間稼ぎが出来ればいいのだ。
「動力源らしきものも見当たらなかった、ということは」
エルゼリオが呟く。
「この船は、海獣によって沈没を免れて、海獣によって航行していた、というのか?」
どうん、と大きく船体が揺れた。
黒い霧が、2人の影を覆っていく。
甲板では、いよいよ戦闘が本格的になり始めていた。海の上には、さっきまでいなかった海獣が姿を現していた。
「なんだよこの数は! 聞いてねえぞ!」
ウィリアムは、水面に顔を出して水弾を放つ海獣に悪態をついた。負傷している彼は、投げナイフを中心とした後衛部隊にいるが、これでは先に武器の数が尽きてしまう。1体1体の大きさはこれまでに比べて小さいものの、数が相当多い。小さいおかげで1撃当てれば沈黙してくれるが、これほどは想定外だ。
「もっと持ってくりゃ良かったか?」
ナイフを握る手に汗がにじむ。
「さっさと片付きそうか!」
バルバロと対峙している一団に声をかけたが、返ってくるのは波の音だけ。
「チッ」
ウィリアムは小さく舌打ちをし、「無理すんじゃねえぞ」と、彼らに聞こえるかどうかのギリギリの声で言った。
「大人しく投降してほしい」
アレクセイ・アイヒマンは、バルバロに剣先を向けていた。バルバロは何も答えず、じっとその剣先の行方を見ている。
「無視か。……そのつもりなら、こちらから」
「兄様危ないっ!」
タチヤナ・アイヒマンが声を掛け、アレクセイは間一髪後ろにのけぞってそれをかわす。甲板の一部がはぎとられ、海の藻屑になる。アレクセイは眉間にしわを寄せたまま、「オーディエンスが先だね」と言った。
バルバロは計略の失敗にも関わらず、悔しがる様子を見せるわけでも、また不敵な笑みを浮かべるわけでもない。ただ表情を暗くして、ぼんやりと、帝国の兵士たちを見ているだけだ。
アレクセイとタチヤナは、互いに背を合わせた状態で船のマスト付近までじりじりと下がる。
「行くよ」
「ええ」
アレクセイが火の魔法で海獣、さらには襲い来る海鳥の表面を焼き、タチヤナがそれでも生き残っているものを片手剣で薙ぎ払う。ウィリアムの言った通り数は多いが、広範囲に攻撃が可能な火の魔法は大物を仕留めるよりも多数の小物を追い払うのに向いている。
「兄様大丈夫?」
「ああ、ターニャは」
「大丈夫だよ」
2つの息を整えて、再び飛び出し始めた海獣たちを焼き払い、斬り倒す。
船の上への水弾攻撃は3人の海獣討伐が功を奏し、ほとんど止まっていた。
だが、海獣もただやられ続けているわけではない。幽霊船の上の掃討が不可能なら、小型魔導船や箱船を襲うまで。
ヴィスナー・マリートヴァは、小型魔導船、そして箱船に向かって迫りくる海鳥の群れを見て、警鐘を打ち鳴らした。「警鐘は『敵襲に備えよ』の合図」と、あらかじめ連携をとってある。飛んでくる敵の様子を見れば警戒が必須なのは明らかだが、念のためだ。箱船側からの返事に使えるものはないが、海鳥の鳴き声や波しぶきとは全く違う機械的な音があれば十分に届くはずだろう。
ヴィスナーは、飛来する海鳥を弓で1羽1羽確実に撃ち落としていく。幽霊船付近で多くが討伐されていたのと、敵が2手に分かれていることで、魔導船への海鳥の数自体はそれほどでもない。問題は海中の敵だが――。
「こんな数が攻めて来るとは、嫌われたもんだな!」
ロスティン・マイカンは額に脂汗をにじませながら、海の中で水流を操り、圧力の高い槍状の水弾を作って海獣へと飛ばす。貫いた水弾は消滅し、代わりに深手を負った彼らは暴れて海面に顔を出す。
「そこッ!」
コタロウ・サンフィールドは、帝国軍から借りてきたカタパルトで、その海獣の頭部めがけて銛を投げる。暴れる前に完全に仕留め、被害を出さないようにする二段構えだ。ロスティンの作った水弾は、箱船のみならず、小型魔導船に迫っていた海獣にも突き刺さる。
「まだまだッ……!」
ロスティンの豊富な魔力量をもってしても、ここまで数多くの敵を貫くほどの水弾を作るのは、容易ではない。呼吸が荒れ、気力で立っているようにさえ見える。それでも彼は、戦闘の手を休めない。箱船を傷つけさせない、その一心で、必死に海獣を追い払う。
コタロウもまた、ロスティンと同じように、箱船を傷つけさせまいと戦いを続ける。先ほど使ったカタパルトを駆使し、海獣と海鳥を落としていく。武器をセッティングしながら残弾を見る。
まだある、大丈夫だ。だが――。
力いっぱい引き、銛を突き立てる。
「まだ減らないのか……!」
倒しても倒しても、どこかから湧き出てくる敵。数は減っているはずなのに、その実感が得られない。
「ここでキッチリ止めないと……!」
コタロウは祈るようにそうつぶやいた。
「海鳥は俺に任せろ……!」
病床のヴォルクは唸るように言ったが、タウラス・ルワールがその体を優しく押さえつける。
「静養しては……いただけないですよね」
「ううッ……!」
諦めにも近い言葉だが、その悲しげな表情がヴォルクの胸に突き刺さる。
「俺は……!」
ヴォルクはぐっと奥歯を噛み締めた。
「このまま療養しよう、すまない」
諦めとわずかな怒りをまとったヴォルク。だが、タウラスの言う通り、ヴォルクは静養している必要があった。今の彼が戦いに参加しては、怪我が悪化することは明白だ。
「そのために、彼女に『あの技』を伝授したのだったな」
自らが戦える状態でないことを知っていたヴォルクは、トゥーニャがバルバロの下船を阻止した、あの『魔王流交殺法・風牙』を伝えていたのだ。彼は目をつぶり仰向けになると、「すまなかった」と詫びた。
「分かってもらえたらいいのです。安静にしていれば、それだけで回復は早まります」
タウラスは隣に付き添っていたメリッサ・ガードナーに向かい合いうなずくと、甲板へと歩き出した。
甲板には、数人の負傷した騎士団員たちが引き上げられている。彼らは幽霊船で戦っていたものの、海鳥や海獣の攻撃で海へと投げ出され、箱船まで命からがらたどり着いたものたちのようだ。海獣たちは墜落した人間には興味がないらしく、襲ったりはしない。あくまでも命令は「戦闘状態にある敵の排除」や「小型魔導船への攻撃」、あるいは「箱船への攻撃」なのだろう。
「傷は浅いようですが」
「そうだな」
既に救護にあたっていたリベル・オウスは、傷口を消毒しながら辺りの様子を伺った。
「箱船への攻撃は?」
「落ち着いてきたようです。彼らを治療するなら、攻撃の手が止んでいる今のうちに」
「ああ」
リベルは鞄から鎮痛剤を取り出して、騎士団員に飲ませる。苦痛に歪んでいた彼らの顔が、少し穏やかになる。その隙に、傷口に包帯を巻き、次の負傷者へ。薬師とはいえ、治療の手つきは慣れたものだ。
それに負けじと、タウラスも負傷者の手当てを行う。多くは軽い擦り傷か打撲で済んでいるようだ。緊急性を要する、命の危機に瀕した怪我人がいないことに安堵し、目を上げて遠く幽霊船を見た。
「これ以上負傷者が増え続けなければいいのですが」
そうつぶやいて、今度は海の上を見る。人間のような影はない。踏ん張って戦闘を続けているのか、もしくはここまでたどりつけずに――。そこまで考えて、タウラスは目の前の負傷者に目を落とした。今は、救える命を先に救うべきだ。そう考えたのである。
「……海賊は、いないか」
箱船の上に並んでいる負傷者たちを見回して、リベルはぼそりとつぶやく。念のため持ってきていた壊血病対策のアイテムたちは、温存しておいて問題ないらしい。
リベルが気付いた通り、エンリケが率いる新生海賊団は、戦闘に加われずにいた。というのも、彼らが率いているのは小舟の艦隊。幽霊船に近付く同程度の規模の舟を狙って攻撃する予定だったのだが、幽霊船に近付いたのは帝国の小型魔導船だけだ。魔導船は「小型」と言ってもエンリケの船よりはかなり大きいし、箱船は少し離れたところにいる。迂闊に近付けば自分たちが海獣の攻撃を受けかねない。機会を伺ったまま、エンリケはやり切れない怒りを押し殺していた。
箱船へ波状攻撃を仕掛けていた海獣たちは、今度は海岸線を襲おうとしていた。だが、こちらも対策が既に取られていた。
リィンフィア・ラストールは海岸線、その波打ち際付近に、腰の高さほどの糸を張っている。釣りにも使える高強度の糸だ。これまでの調査で、海獣は海底洞窟から飛び出してくるという報告があった。それに、海岸線に待機していた部隊を襲った時、海獣たちは一度陸に上がって戦っていた。この糸は、彼らが上陸しようとする際の足止めだ。もちろん、何十体もが一気に攻めてくれば、糸自体は持たないだろう。だが、数瞬の時間稼ぎにはなる。それだけで十分期待できる効果がある。
キャロル・バーンは、リィンフィアと一緒に、海の様子をじっと伺っている。波打ち際、迎撃するためのラインが見えやすいようにと、彼女は水を少しだけ沖に引かせている。風の音、遠くで鳴く海鳥の声。不気味なほどの静寂さがあたりを覆ったが、やがてその緊張の糸が切られた。水面にいきなり、無数の気泡が立ったのだ。
「敵襲ですっ!」
リィンフィアは大きく声を張り、全員の意識を海面に向けさせる。飛び出してきた1体の海獣が糸に引っ掛かり転んだ隙に、リィンフィアの風の力で飛ばされた小石が正面から襲い掛かる。さらに、キャロルの水弾が、海獣の横っ腹を貫き風穴を開ける。糸に弾き返されるように、海獣が海へと押し戻される。その屍を乗り越えて、別の海獣が海岸線を踏み越えた。
「次から次へとしつこいよ!」
シャオ・ジーランは怒りに満ちた表情で、両手に出刃包丁を構えている。そして、気合を入れて海獣の懐に忍び込むと、陸上生物で言えば頸動脈に該当するであろう部分めがけて、右手を振り下ろす。――だが。
「んー?」
鋭くとがれた出刃包丁とはいえ、あくまでも料理用の道具。人間の指くらいまでなら落とせるが、生きた動物、ましてや荒れ狂う海獣ともなると、話は全く別だ。首尾よく懐まで潜り込めたのは幸いだったが、出刃包丁は致命傷を与えるどころか、少しの切り傷を残したのみであった。海獣はシャオの胴に胸びれで一撃食らわせる。あっけなくシャオの体は吹き飛ばされて、辺りの岩場に投げ捨てられた。
「だっ、大丈夫ですか!?」
ユリアス・ローレンがシャオに駆け寄り、「こちらへ」と肩を貸す。
「うーん、甘く見過ぎだったアル」
出刃包丁を見て、「研ぎなおさなきゃ」とつぶやくと、それらを片手にまとめて、ユリアスに半分くらい体を預けた。
「内臓にダメージがなきゃいいけど……」
ユリアスは心配そうにシャオの顔を見た。彼の心配をよそに、シャオは「ま、時間稼ぎくらいにはなったかな」と、どこか満足そうな表情だ。
野戦病院は、まだそこまで混み合っていない。戦いが始まって間もないということもあるが、これまでの戦闘に比べれば、海岸線に押し寄せている海獣のサイズが小さいこともその要因だろう。ユリアスはシャオを寝そべらせると、回復魔法を施す。
ふと、テーブルの上を見ると、ユリアスが作っておいたドリンク剤が数本空いている。疲労回復効果のある成分が配合され、そこに地の魔力を込めたものだ。さっき準備していた時にいたはずの海賊の捕虜たちがいない、ということは……脱走? いや、彼らは――。
「温かくて気持ちいい……」
ユリアスの小さな動揺を知る由もないシャオは、回復魔法の心地よさに酔いしれていた。
海獣の猛攻を避けながら、ジン・ゲッショウは、なるべく海岸線の際に立っていた。彼の目標はただ1つ。敵の大将の首を取る。もちろんこの距離から自らの力で仕留められないのであれば、それの援護だ。海獣は、あくまで首領の指示に従っているに過ぎない。
「なるほどなるほど」
ジンは臨戦態勢を崩さず、目を凝らしてバルバロの顔を凝視する。
「確かに、悪そうな顔をしているでござるよ」
どこが、と言われると困る。全体的に、悪い奴の人相、そんな感じがする、という話である。彼は拳に意識を集中して、バルバロめがけて火の塊を放つ。
ジンが火弾を放つだが、その攻撃をバルバロはひらりと交わした。火弾が向かった先は、ジェザが打ち立てた帝国旗のマストの先端だった。
「おぉいッ! 何やってるんだっ!」
それなりに離れているはずなのに聞こえてくるジェザの怒号。
「申し訳ないでござる! そんなつもりでは! 決してそっちを狙ったわけではないのでござるが!」
ジンは額にうっすらかいた汗を拭い、ひとまず自身の安全を確保するために1度波打ち際から身を引いた。
へし折れたマストだが、海の底から引き上げられて乾燥が不十分だったためだろう、火はつかずに甲板に落ちている。だが、そのことにさえ気付かないほど、緊迫する戦闘が続いてた。
リンダ・キューブリックは無言のまま、何撃、何十撃と繰り返しバルバロにヘビーメイスを振り下ろしている。彼女が目指しているのは、文字通り「殲滅」である。それ以外に、彼女は何も求めていなかった。だが、この場にいる海賊はバルバロ1人。ならば、この体躯は絶対に砕かねばならない。
バルバロもまた、短剣を構えたまま、リンダの気迫に負けずにそれを丁寧にかわしていく。1発もらえば確実に死ぬ。それが分かっているだろうに、彼女の表情は、どこか楽しそうにさえ見える。
「ちょっとあなた! 船まで壊さないで下さいまし!」
コルネリア・クレメンティはリンダの近くから援護のすきを窺っている。だが、リンダの怒りに満ちた攻撃がすさまじ過ぎて、不用意に近付くと自分まで巻き添えを食らう。第一、彼女の言う通り、振り下ろしたメイスが甲板にボコボコ穴を開けているのだ。
「やりすぎるとあなたのせいでこのボロ船が沈みますわ!」
コルネリアが言った瞬間、リンダのメイスは一際大きな穴を甲板に空けた。木の残骸に引っかかって、メイスが抜けない。
バルバロが飛び上がり、リンダの首元目掛けて飛び掛かる――!
「だからッ!」
コルネリアが駆けて、馬鞭でバルバロの手から短剣を弾き飛ばした。
「――!」
「帝国のため、皇帝陛下のために死ぬのは騎士の誇りかもしれませんが、今のような無様な死に方、私が認めませんわ」
リンダのヘビーメイスが、抜ける。だが、彼女は何も言わない。
「あらあら」
コルネリアの目が、じろりとバルバロをにらみつけた。
「あなた方、幽霊よりも怖い『生者』の逆鱗に触れちゃってるみたいね」
リンダはメイスを掲げ、目を離そうとしない。

「バルバローッ!!」
船の上に、遠くから声が聞こえた。自身の名を呼ぶ声に、バルバロは横目で海岸線を見た。
「俺たちだー! 聞こえるかーッ!」
キージェ・イングラムは、海岸線に海賊の捕虜たちを連れてきていた。波をかぶりそうなところまで近付いている彼らは、必死にバルバロに向かって声を掛ける。それは、キージェが無理にそうさせたわけではない。キージェの要請に、海賊たち自身が協力的になってくれてのことだった。
「俺たち、おかしくなってたんだよ!」
海賊たちの多くは、歪んだ魔力に侵されていた。
「ボスもだ! みんな、どうかしてたんだ!」
バルバロの表情は変わらない。冷たく、殺意に満ちている。
「私は正気だ」
彼女の小さな言葉で、海獣たちがさらに勢力を増して海岸線を襲っていく。
「あっ、あーッ!?」
「うわぁぁっ!!」
幽霊船の上からでも、大きな悲鳴が聞こえてくる。
「バルバロ! 目を覚ましてくれ!」
「うるさいッ! 私は私だ!」
目を見開くバルバロ。
「正気、私は普通、海賊、これが――私――!」
「いだっ、うぎゃーっ!」
「私は正気、これでいいんだ、これが望み、唯一の道、私は」
「バルバロ、頼むーっ、もうこんなことはっ……いででッ!」
「ああああああああ!!!!」
バルバロは頭を掻きむしり、絶叫する。
「違う、やめてくれ! あいつらは仲間なんだ! もういいだろ! もう、いい、もういいッ!」
異様な光景に、騎士たちは息を呑む。そして、誰からとなく、剣を握りなおす音が聞こえた。海獣の動きも、また海鳥の動きもなりを潜め、静寂の中に、小さな金属の音だけが響いている。
「やめて、もうやめてくれ……違う、そんな、そんなこと――いや、そうじゃない……大丈夫、私は、正気だ……」
バルバロの表情が、少し前のそれに戻る。彼女の周りを、目には見えないどす黒いオーラが覆う。空気が、凍り付いた。
「黙れ。全員殺す」
彼女はそう言うと、海岸線に向かって魔力の塊を放った。小さくまとまった弾は、猛スピードで海賊たちへと向かって飛んでいき、彼らの目の前で大地をえぐった。バルバロの持つ魔力からは、考えられないほど強力なエネルギー。彼女は、自分の放ったエネルギー弾の結末を見ずに、騎士たちに淀んだまなざしを向けた。
「次は、誰が死にたい?」
言い切る直前、ナイト・ゲイルが飛び出し、バルバロに斬りかかる。不意を突いたはずが、かわされる。もう一撃。
武器を持っていないバルバロは、これまでにないほど身軽だ。まるで、肉体の限界を無視したような動きをする。ナイトが浅く斬り込んだ胴にも、思い切り背をのけぞらせてかわす。反撃の速度は上がるが、人体の構造上大きな負荷がかかっているはずだ。だが、彼女はそれをものともしない。それどころか、起き上がって一発、彼の顔面に頭突きをかました。
「ぐッ……!」
逆に不意打ちをもらった形になったナイトだが、もう一度剣を構えて意識を集中する。
死ななければ大丈夫。
それよりも、今こいつをここできっちり捕縛することで、帝国が優位に立てる――そしてマテオの民のためになるのだ。
「おらァッ!」
気迫を込めて叩き込んだ一撃が、バルバロの右腕を――。
「ちょっと待ってーっ!」
バルバロの腕まで、あとほんの数ミリ。彼女は目を見開き、少しこらえたが、その場に膝をついた。魂が抜けたように呆然としているが、うっすらと、一筋の血が流れている。
「な……」
ざわつく幽霊船の上に、メリッサが飛び乗った。ヴォルクがこっそり、風の魔法で彼女を幽霊船まで送り届けたのだ。
「バルバロちゃん……」
メリッサの声に、バルバロは少しだけ反応した。だが、その表情はかつてメリッサがよく知っていた、あのバルバロのものではない。
「やっぱり変……」
彼女はゆっくりとバルバロの前まで歩み寄る。船上は、さらにざわ付いていく。
「メリッサ、危ないぞ」
「大丈夫」
彼女は、そう確信していた。
だって、バルバロちゃんは、そんな子じゃないから。
手を握る。冷たいが、手入れを雑にしがちなバルバロの、いつもの手だ。彼女を、取り戻さなくちゃ。
魔力を、右手に集中していく。自分の持てるありったけの魔力を増幅して、バルバロの中にある負の魔力、瘴気の根源を押し出す。彼女は首にかけている指輪――魔力増幅装置を握りしめ、自身の持つ魔力を増幅した。
「バルバロちゃん、ごめんっ!」
そう言うと、思い切り彼女の腹目掛けて、魔力の籠った一撃を加える。
「ッ――!」
バルバロの体は思い切り吹き飛び、船の一部にぶつかって、そのまま力無く甲板へと崩れ落ちた。
「……ぜんぶ、出せたかどうか……分からない、けど……」
メリッサは沈黙したバルバロを見てうっすら微笑むと、そのままその場に崩れ落ちた。
海獣たちが、去っていく。海鳥も、まったくそれまで関係なかったもののようにどこかへと飛んで行った。
船室の奥から慌てた様子でエルゼリオとルティアが戻ってくる。
「何かあったのか!? 船室の瘴気が一気に晴れていったよ。それに、さっきまで船の穴を塞いでいた海獣が急に離れたんだ」
「このまま行くと、十数分以内には沈没してしまいます。幸いこの辺りは浅瀬なので沈むといっても大したことはないでしょうが、念のため魔導船に避難を!」
その号令に、帝国騎士たちが引き上げていく。もちろん、気を失っているバルバロも捕縛して連行されていく。
海岸線でその様子を見ていたキージェは、安堵から、その場に膝をついた。想定外の海獣強襲に多くの捕虜たちを後ろへ下げようとしたが、彼らがあまりにも前に出て叫ぶことで、危うく大切な命を落とさせてしまうところだったからだ。
生きたいはずの命を、そのまま無にしてしまうところだったから。
「大丈夫ー!?」
ローデリト・ウェールが崖の上から大きな声で、海賊たちとキージェを呼ぶ。
「上で、治療しよー!」
声は届かなかったが、呼ばれているようだ。キージェはうなずいてようやく立ち上がると、海賊たちを連れて崖の上へと向かっていった。
「いだっ! 染みる染みるッ!」
暴れる元海賊たちに容赦なく消毒液をお見舞いするローデリト。
「無茶するからだよ。痛くしておくねー」
「おい、わざとかよ! あでっ!」
ローデリトは彼らの怒りに答えることなく、会話を続けた。
「でもさ、海賊のボスって、何がしたいのかちょっとギモン」
「知らねーよ。俺らが……っていうか、自分が生きやすい世の中を作りたかったんじゃねえの?」
「でも、強いヒトだけが生きていける世界とかもねー。赤ちゃんがいなくなっちゃったら未来なくて終わっちゃうし」
「だから知らねえって」
乱暴な口を利いた男に、消毒液を追加するローデリト。男は鼻の穴を広げ奥歯を食いしばりながら、「ヘンなのに憑かれてたせいでそんな考えになっちまったんだろッ」と続けた。
戦闘は、無事終わった。幽霊船はもぬけの殻。機会を逸したエンリケ一行は殲滅される前に燃える島へと向かって退避している。海獣も姿を消した、穏やかな海。
だが、残された仕事はある。それは、海底調査。箱船による本格調査の前に、海岸沿いから下調べを行う必要があった。何せ、1度崩した洞窟だ。
カーレ・ペロナは海岸沿いに腰を下ろし、海底洞窟の土壁を探っていた。
「壁は意外と丈夫そうだね」
念のため、と、外壁を強固に固めていくカーレ。抜け道として、奥にもう1つ穴をあけようかとも思ったが、どうもこの海底洞窟はどんどん地中深くと潜っていくように出来ているようなのだ。どこかにもう1つの出入り口になるような穴があるのかは分からないが、途中で脱出口をこじ開けようとすると、かなりの分厚さの海底を削ることになる。
カーレはあきらめて、徹底的に外壁を固めることに神経を注いだ。
第3章 海底洞窟調査
戦いが終わった海に、箱船が進み出た。
海底洞窟の調査に向かうためだ。
前に海底洞窟の入口を見つけたという波が荒れているところの手前で、箱船に乗る水の魔術師達が海水を操り、海底洞窟の入口を覗かせた。
何があるかわからないその場所に踏み入るのは、アウロラ・メルクリアスにクラムジー・カープそれとマルティア・ランツの三人である。
箱船から小舟が下ろされた。
小舟に乗る三人の表情は硬い。
それは決して未知の洞窟に対する緊張によるものだけではなかった。
マテオ・テーペの民としては、大事な箱船をもう危険な海域には出したくないという思いがある。
しかし、彼らが置かれた状況がそれを許さない。
帝国の要請を拒否したら、どんな報いがあるかわからない不安と恐怖。
「皇帝のたった一言で一方的に潰され得るマテオ民……けれど、その一方で帝国だけでは解決できない問題もある、と」
「だからって、こういうのは正直言ってしたくないよ。海底で待っているみんなのことを考えるとなおさら、ね」
クラムジーの呟きに、アウロラが返す。
「情報も条件もなるべく開示してくれれば、くだらぬ腹の探り合いで消耗せずに済むのですが」
クラムジーのぼやきは、波音にさらわれていった。
斜めに切り出した入口付近に小舟を寄せ、三人は周辺を観察したり奥に目をこらしたりした。
「これといって、変わったものはないね」
アウロラの言う通り、目を引くものは何もない。
奥のほうは闇が濃く何も見えないが、海水が流れ込んでいるため小舟を降りることができないことはわかった。
また、洞窟は下のほうに向かって続いているようだ。箱船が入り込むだけの広さは充分にあるので、潜水すれば調査を進められるだろう。
念のため水の魔術師達にもっと海水を引かせることができるか聞いてみたが、これ以上は無理だと返された。
三人は箱船に戻り、箱船は潜水態勢に移った。
水の膜を張り、暗い洞窟に潜っていく。
明かりを灯し、海獣の影が潜んでいないかと警戒する。
「あそこ……!」
鋭く声を発したアウロラが下のほうを指さす。
海獣だ。
マルティアと二人で魔法による迎撃態勢をとるが、大小さまざまな海獣は箱船に関心を示さなかった。
ただ、悠々と泳いでいるだけだ。
さらに海底に下りて行くと、小型の海獣と魚が見えた。大型の海獣の姿はない。
そこで箱船は止まった。
行き止まりになってしまったのだ。
「穴があるわね。右と左に。どこに続いているのかしら」
マルティアは目を凝らすが何も見えない。
現在地はおそらく本島ま中心近くだろう。
「羅針盤は、リモスのほうと燃える島のほうを指してるんだって」
船長に確認したアウロラがマルティアとクラムジーに教えた。
「南北じゃなくて、東西を指してるの?」
「うん……」
マルティアは首を傾げるが、アウロラにもよくわからないので答えようがない。
「とりあえず、あの穴に箱船では入れないでしょうね。大きすぎます」
クラムジーの指摘の通りなので、調査はここまでにして引き上げることになった。
第4章 エピローグ
トゥーニャ・ルムナは幽霊船を取り巻く瘴気への対策として、薄い風の層を全身に纏っていた。
そして、伝授された技を行使し……。
今、彼女はとても気分良く空を飛んでいた。
どういうわけか、どれだけ長時間飛んでいても疲れを感じない。
「わー、すごい~。いつもより体が軽く感じるよ~」
鳥のように自由に宙を旋回するトゥーニャの周りには、黒く変色した魔力がなびいている。
幽霊船を取り巻いていたものと同じものだ。
魔法で身にまとっていた風の層が、歪んだ魔力に侵されていたのである。
本人が自覚しないうちに魔力を、意識を、狂わせていっていた。
風を受けるトゥーニャに、囁きかけてくる声があった。
──あなたは、私達の仲間。人より私達に近い。
──私達は、人に殺された。
──悲しい、つらい、苦しい……。
──世界に人はいらないの。
──悲しみは、もう生まれない。
──全部、全部なくしてしまいましょう。
誰の声かもわからない。
囁きかけてくるようでいて、実は自分の心の中の声かもしれない。
トゥーニャは判断力を失いつつあった。
「よし、それじゃ大地を全部なくしちゃおう~」
歌うように言ってクルリと一回転すると、ゴゥッと凄まじい勢いで風が回転を始めた。
それは竜巻となり地上に襲いかかっているが、起こした本人は事態を理解していない。
「これでいいかな~?」
──もっとつよく、もっとおおきく。
「これくらいかな~?」
──もっと多く、もっとはげしく。
「うん、がんばるよ~」
自分が何をしているのかもわからないまま、トゥーニャは無邪気に笑いながらいくつも竜巻を起こしていた。
報告のため、宮殿の広間に来た騎士団副団長は硬い表情をしていた。
それを見た皇帝は、何か良くないことが起こったのだと察した。
敬礼の後、副団長が口を開く。
「幽霊船を操っていた海賊は捕え、他の海賊共々特別収容所に入れてあります。また、船の確保に成功しました。まだ残党はいますが、彼らは燃える島へ退却したようです。……ただ、懲戒部隊に加わった傭兵騎士が行方不明になりました」
「行方不明?」
「はい。その傭兵騎士は風魔法の異常なほどの使い手です。おそらく捕らえた海賊から弾き出された歪んだ魔力に、とり憑かれてしまったものかと」
皇帝の表情が険しくなった。
重臣の一人が裏切りの可能性を示唆したが、副団長は否定した。
「今さら裏切ったところで孤立するだけ。何の意味もないでしょう。それともう一つ、気になる報告が」
「なんだ?」
「燃える島近郊で複数の竜巻が発生したという報告が入ってきています。その傭兵騎士が起こしている可能性があります」
「そうか……。まずはご苦労だった」
副団長は敬礼し、広間から下がった。
重臣達も下がらせた皇帝は、沈鬱な気持ちで私室のドアを開けた。
「次から次へと……」
口をついた言葉は独り言ではなく、そこに誰かがいることをわかっている口ぶりだ。
だが、返ってきたのは労いではなく、ため息のような応答だった。
見ると、ソファにはラダがぐったりと横たわり、傍の椅子では応答の主が自ら腕の治療をしている。
何よりも、室内の様子が明らかに争いがあったことを物語っていた。
皇帝の顔に、サッと緊張が走った。
「何があった?」
「ラダに襲われただけだよ。掠り傷だ」
治療道具を乗せたテーブルの隅には、鞘に収まったラダの短剣があった。
「そうか。ラダもか……」
「ハーフは、歪んだ魔力の影響を受けやすいようだ」
「歪んだ魔力と自身の魔力が触れ合うことで、侵されていくのか?」
「おそらく。特別収容所に海賊達を収容しただろう。その多くも歪んだ魔力の影響を受けていて、地の高位魔術師達が弾き出したんだ。けれど、弾き出されたそれは消えるわけではなく、また別の生物の中に入っていくようだ」
「厄介だな」
皇帝の声に苛立ちがにじむ。
「ところで、こんな報告もある。──各属性の継承者の一族は、影響を受けないらしい」
このことが歪んた魔力に対抗する術となるかはわからないが、皇帝は頭の中に入れておいた。
「嫌いだ……こんな街もみんなも、騎士も陛下もお前もッ。みんな、みんな大嫌いだッ!」
そう叫び、スラムの子供達が暴れ出した。武器になりそうな廃材などを拾って人を襲ったり、建物の窓ガラスを端から割ったりし始めたのだ。
血相を変えた大人達が止めようしたが、いつの間にかその大人達も手あたり次第に破壊を始める。
スラムのあちこちから火の手が上がり、人々は混乱した。
我を見失った人達と正気の人達とで争いになる。
このことはすぐに騎士団に通報され、皇帝の耳にも届いた──。
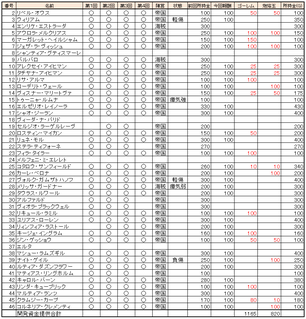
連絡事項
トゥーニャ・ルムナさん
おめでとうございます! 貴女がラスボスです!!
……お、怒らないでくださいッ。
能力値や状況等すべてが揃ってしまったので致し方ありません。
意図的に目指したわけではないことはよく分かっており、現在のトゥーニャさんには数か月間に渡るスヴェル協力の実績がありますため、やむを得ない状況に陥らない限り討伐という方向には進まないと思われます。
次回はシナリオにご参加いただかなくても、リアクションに若干登場いたします。
●スタッフより
【川岸満里亜】
構成、データー処理担当の川岸です。
今回懲戒部隊に志願された方のうち、懲戒部隊の任務と記載されていた行動が一致していなかった方につきましては、別の場所で書かせていただいております。
さて、次回は前編最終回です。
どんな結末を迎えるのか、楽しみにしております!
【冷泉みのり】
こんにちは。リアクションの一部とエピローグを担当しました冷泉です。
担当の一部に開発パートがあるのですが、いつもアクションを楽しみにしています。
お手柔らかに~! と、思いつつも楽しみです。
今回もシナリオへのご参加ありがとうございました!
【東谷駿吾】
ご参加下さり、ありがとうございました。
幽霊船での戦闘シーンを中心に書かせていただきました。
次回でワールドシナリオはひと段落ということらしいのですが、「ここからどうなるんだろう?」と、私もワクワクしています!
次回も、どうぞよろしくお願いいたします!
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から
