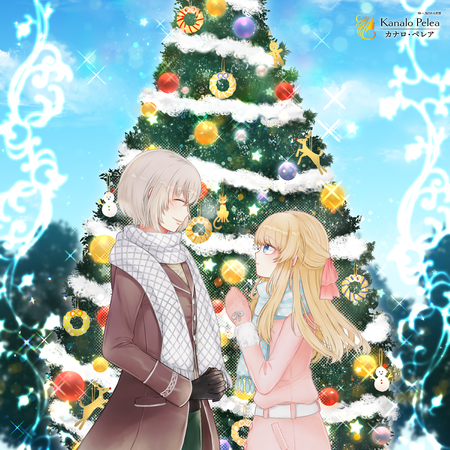聖なる特別な日
●祝祭初日
二日間におよぶ聖なる日の祝祭に、事件続きの街も明るさを取り戻していた。
祝祭中くらいは、嫌なことは忘れようといった雰囲気だ。
街の巡回をするリンダ・キューブリックは、楽しそうに笑う人々と何度もすれ違ってきた。
いつもの全身鎧で完全武装の彼女は、晴れの空気に満ちた街で浮いていた。
他にも巡回警備にあたっている騎士はいるのだが、その風貌からリンダはどうしても目立ってしまう。
時々、ご苦労様です、と街の人から労いの言葉をもらいながら、羽目を外し過ぎたお馬鹿さんが暴れていないかと目を配る。
ふと、リンダは気まぐれでパルトゥーシュ商会へ足を運んだ。
リンダの姿を見かけると、すぐに番頭が出てきた。
「これはリンダさん、巡回ですか? ご苦労様でございます」
その声を聞きつけて、店内から顔なじみの用心棒達や商会長のフランシス・パルトゥーシュがぞろぞろと出てきた。
「なんだお前、こんな日にも仕事か? 実は仕事人間か?」
と、用心棒の一人が笑う。
「上官からの指名だ。致し方ない」
「どうせ独り身だから変わってやれとか言われたんだろ」
「む……」
「オイオイ、マジかよ……」
やや剣呑な目つきになったリンダに、用心棒達も笑いよりも同情に傾いた。
「こういう時に独身者にしわ寄せが行くのは仕方ないだろ。特別手当、がっつり分捕っておきなよ」
当然の権利だとフランシスはリンダに言った。
「……ま、悪いことばかりではない。煩わしい『世間のしがらみ』から解放されたと思えば」
「たくましいねぇ」
大洪水で天涯孤独の身になった人は大勢いる。
リンダもその一人だ。
彼女は名門キューブリック家の末娘だが、そのいかつい外見から鬼子と疎まれ家に馴染めなかった。
大洪水でそれらを失うことにより、家という鎖から解放されたのだ。
それからいまだに恋人や家族を持つこともなく、気楽な独り身でやってきた。
「あたしも、それくらいスッキリ言えればいいんだけどね」
と、フランシスは苦笑する。
彼女も大洪水で家族を失った。
けれど、その時共にいた従業員数人が一緒に生き残ったから、一人ではなかった。
同時に、商会の跡継ぎとしての責任を否応なしに負うことになった。
大洪水後の混乱を力を合わせて乗り越えた今、彼らとは家族のような関係だ。
「そういや、神殿や広場には行ったかい? 広場にはうちも店を出してるんだ。子供向けのおもちゃを売ってるんだよ。よかったら覗いてみてくれ」
「どちらもこの後の巡回ルートに入ってるな」
「こういう日は、みんなけっこう不思議な気持ちになるもんでさ……ひょっとしたら、いい出会いがあるかもしれないよ」
そう言ったフランシスに、リンダは短く笑って仕事に戻った。
聖なる日の祝祭による広場の賑わいは、想像以上だった。
ふだんリモス村のような寂れたところで暮らしているので、余計に人の多さを感じた。
「すごい人、だね……」
「はぐれるといけないので手を繋ぎましょう」
そう言って差し出したユリアス・ローレンの手を取るカサンドラ。
二人は人混みに揉まれながら、ほとんど方角もわからず進んだ。
縦にも横にも大きい人の向こうに、ユリアスは射的の出店を見つけた。
「射的がありますよ。カサンドラさん、一緒にやってみましょうか」
「うん。射的……初めて」
人の間を縫って店の前に出ると、二段になった景品棚には小さい物から大きい物まで様々な品がずらりと並んでいた。
おもちゃの弓矢で棚から落とした景品をもらえるのだという。矢の先端には、矢じりではなく丸められた布が取り付けられている。
さっそく弓矢を持ったユリアスがカサンドラに聞いた。
「何か欲しい物はありますか?」
カサンドラは、きょろきょろと棚に目を走らせると、一つの品で目を留めた。
「……あのキャンディ。取れたら、一緒に食べよう……」
カサンドラは、カラフルなキャンディがいくつか詰まった小さな箱を指さした。
「綺麗なキャンディですね。がんばってみますね……!」
カサンドラが見守る傍で、ユリアスは弓に矢を番えて狙いを定めた。
ここだ、と矢を放った直後、ポコンと軽く音を立ててキャンディの箱に当たる。箱はころんと棚から落ちた。
「ユリアス君、すごい……!」
「よかった……」
無事に景品を取れたユリアスは、ホッと肩の力を抜いた。
もらった景品をさっそく開けて、二人はカラフルなキャンディを口に入れた。
めったに食べられない甘さに、自然と笑顔になった。
人混みの歩き方にも少し慣れた頃、周囲の出店から明らかに浮いている濃い紫色のテントを見つけた。
占いのテントだ。
長い行列ができていたが、甘いキャンディと楽しいおしゃべりで、あっという間に順番が来た。
黒いヴェールで素顔を隠した占い師は、とても神秘的だ。大きな水晶玉がいかにもそれっぽい。
カサンドラは特に占ってほしいことはなかったので、ユリアスは二人の相性を視てもらうことにした。
しばらく水晶玉を覗き込んでいた占い師は、やがて囁くような声で結果を告げた。
「相性は良いですが……障害が多い、という印が視えました。これからも共にいるつもりなら、覚悟が必要でしょう」
カサンドラは、納得した顔で小さく頷いていた。
テントの中は時間の経過を忘れさせるような場所だったことが、外に出た時にわかった。
二人が占い師と向き合っていたのは、ほんの少しの時間だったようだ。
カサンドラが少し疲れているように見えたユリアスは、食事に行くことにした。
聖なる日特有の飾りつけがされた店に入り、ランチメニューを選ぶ。
二人が選んだのは、もちろん聖なる日の二日間だけの特別メニューだ。
いくつかあったのでそれぞれ違うものを注文し、分け合って食べることにした。
「こんなに人がいっぱいのところ……初めて見た。遠くからも、来てるのかな……」
「そうだと思います。みんな楽しみにしていたに違いありません」
「うん……そうだよね。私も……とても楽しみ、だったから」
運ばれてきたのは、肉料理と卵料理だ。どちらも香辛料を贅沢に使っていて、香りだけで幸せな気分にさせてくれる。
パンもスープもおいしくて、二人の食はとても進んだしおしゃべりも弾んだ。
食事の後は、再び広場へ。
今度は祝福の木を見に行った。
日の光を反射して、オーナメントがキラキラと輝いている。
「夜になるともっと綺麗でしょうね……。今度は夜に一緒に見たいですね」
「うん……見に来よう、ね」
カサンドラは、控えめだけれど明るく微笑んだ。
神殿には多くの人が集まり、ジェルマン・リヴォフ神官の話を聞き祈りを捧げていた。
ジェルマンが語る救世主誕生の伝説は、一日に何回かに分けて話されている。
祈る人々の中に、カーレ・ペロナとグレアム・ハルベルトの姿もあった。
カーレは、神殿に行くというグレアムの付き添いだ。
外の賑やかさとは打って変わって静謐なこの場で祈っていると、カーレの心にはたくさんのことがまとまりなく浮かんでは消えていった。
中でも、帝国と皇帝に関する奇禍のことや、亡くなった家族のこと、団長やスヴェルのことなどが、答えが出ないまま渦巻いている。
ふと、周囲の静けさが緩んだ。
それぞれ祈りを終えたようだ。
外に出て行く人達を見送るジェルマンのもとに、グレアムが近づいていく。
神殿に入る前、祈り終えたらジェルマンに挨拶をしていくとグレアムは言っていた。
カーレもそれに続いていくと、二人に気づいたジェルマンが目礼した。
「この二日間は、神殿も人の出入りが多くなりますね」
「国民の心が少しでも安らかになればいいのですが」
「救世主の伝説を久しぶりに聞きました」
まだグレアムが子供の頃から、彼はこの伝説を家庭教師から聞かされてきた。
大洪水後は目の前の問題に追われ、思い出すことはほとんどなかった。
そのため、彼は懐かしい気持ちでジェルマンの話に耳を傾けていたのだった。
「あの頃は、あまりピンと来ないまま聞いていましたが、今となっては伝説の救世主を望んでしまいそうになります」
グレアムの口ぶりは、まるで救世主に遠慮しているような感じだった。
なぜそのような言い方をしたのか、グレアムは話さない。
ジェルマンも真意を尋ねなかった。
カーレは、黙って二人の会話を聞いていた。
……と、思ったら、不意に振り向いたグレアムに聞かれた。
「カーレは、この伝説のことをどう思いますか?」
と。
「え、えぇと……そうですね……」
どう答えたものか、カーレは返事に迷う。
ジェルマンもじっとカーレを見て返答を待っている。
祈っていた時に頭の中を駆け巡っていたあれこれが、また回り始めた。
「伝説のことは、私からは何とも……。ですが、来年はもっと頑張ります」
そうですか、とグレアムは微笑んだ。
「若い人が頑張ってくれるのは、とても頼もしいです」
「ほとんど変わらないはずですが……」
二人のやり取りを見るジェルマンはいつもと変わらず気難し気な顔をしているが、雰囲気はやわらかかった。
ぽかぽかと温まった体に、寒さが心地よい。
ホットワインを少々飲み過ぎてしまったアルファルドは、酔い冷ましに歩いている。
特に行き先は決めていなかったが、人の流れに任せた先は、まだ明るかった時に立ち寄った神殿前だった。
もう頭上には星が瞬いている時間のため、この日のバザーは終わっていた。
今は神殿へ出入りする人がいるだけだ。
もう少しすれば蝋燭の時間になるため、訪れる人は増えるだろう。
足を止めてぼんやりしていると、知っている人が前方から歩いてきた。
向こうもこちらに気づき、親し気に微笑む。
「こんばんは、アルファルドさん。お一人?」
「ああ。そっちもか?」
「ええ。たまには気ままにね。出店とかを回っていたの?」
「出店というか……ああ、そうだ。ちょうどいいな、これやるよ」
と、アルファルドは小さな紙の包みをインガリーサ・ド・ロスチャイルドに手渡した。
「バザーで買わされたんだ。願いを叶えるマスコットだそうだ」
売り子をしていた子供達がしきりに勧めてきた品だった。
アルファルドは断ったはずだが、気づいたら袋に入っていたのだ。
その時にはすでに飲んでいて、酔いが回り始めていたので記憶はやや曖昧である。
そのことを話すと、インガリーサはクスクスと笑った。
「アルファルドさんは、年下に弱いのかしら」
「さあな。だが、さすがにこれはいい歳したじじいが持つような代物じゃないだろ」
インガリーサが開けた包みの中には、女の子が好みそうなかわいらしいマスコットが収まっていた。
「いらないならバリにでも押し付けるさ」
彼も彼で思い切りイヤな顔をするだろう、とアルファルドは想像した。
あるいは困り果てた顔になるか。
「デザインはともかく、お願いが叶うのでしょう? 手放してもいいのかしら」
「……俺の願いは叶わなかったから、もう必要ないんだ。いつか来ると待っていたが、時間切れってやつだな。……後悔はしてないさ。自分で決めたことだから。だから、他の連中は……叶えば、いいな」
独り言のように話しているうちに胸に広がった切なさに、アルファルドはそっと息を吐いた。
ふと、アルファルドは寒さでくしゃみをした。
そして、隣にあるぬくもりに気づく。
「だいぶ飲んでいたようね。こんなところで眠ったら死んでしまうわよ」
困ったように微笑むインガリーサ。
彼女の話では、立ち話の途中でふらついたアルファルドを、神殿入口の階段に座らせたのだという。
そしてほどなくして彼はうたた寝を始めたそうだ。
「悪い……迷惑かけたな」
「いいえ。ねえ、あのマスコットだけれど、しばらく預かっておくわね。それで、お節介かもしれないけれど、あなたの分もお願い事をしておくわ」
もう路上で眠ったらダメよ、とやさしく言ってインガリーサは去って行った。
それから少しして、蝋燭の時間を過ごすために人々が集まって来たのだった。
ポコン、と軽快な音を立てて射的の矢が人形に当たった。
矢に弾かれて、人形は景品棚から落下した。
「当たりましたね、コタロウさん!」
射的用のおもちゃの弓矢を下ろしたコタロウ・サンフィールドの傍で、ベルティルデ・バイエルがパチンと手を叩いて喜んだ。
「ほいよ、兄ちゃん。こいつは幸運の人形だ。いいことあるといいな」
出店の主の壮年の男性が、コタロウに人形を手渡した。
手のひらに乗るくらいの大きさの、かわいい女の子の人形だ。
出店を後にして楽隊のほうを見ると、アップテンポな曲に合わせて見事なタップダンスを見せる芸人がいた。
「あの足の動き、すごいね」
「音楽とぴったりです」
もっと近くで見てみようと、二人は集まりつつある人だかりの中に入って行く。
貴族の社交パーティでのダンスとは全然違うステップは、見る人を刺激し気分を盛り上げた。
終わるとたくさんの硬貨が器に投げ込まれた。
「……あ、そうだ。占いの店に行ってもいいかな?」
「ええ。何を占ってもらうのですか?」
「実は……最近のことなんだけど、帽子をなくしちゃったんだ。見つかるかなと思って」
そして占いの結果は、思いがけないところから見つかる、であった。どこにあるかまでは、占い師には読めなかった。
「思いがけないところ……どこだろう」
「探し物は、探している時にはなかなか見つからないことですし、気長に待ってみるのも手かもしれませんよ。ですが、わたくしも気にかけておきますね」
「ありがとう」
「飲み物でもどうですか? あそこでフルーツジュースを売っていますよ」
「そうだね。喉渇いてきたし。それにしても、フルーツジュースなんて珍しいね」
「ええ。それだけこの二日間は特別な日なのでしょう」
「さっき食事した店も特別メニュー出してたからね」
「とてもおいしかったですね」
二人が早めの夕食をとったのは少し前のことだったが、めったに食べることのできないラム肉の凝った料理や甘いデザートの味は、しばらく忘れられないだろう。
買ったフルーツジュースは、ブドウをベースにした爽やかな味だった。
人混みではぐれないように注意しながら、祝福の木の近くまで歩く。
広場でひときわ輝いているこの木を見るために、たくさんの人々が囲んでいた。
キラキラと色とりどりに点滅する魔法具の輝きが、祝福の木をいっそう特別なものに見せていた。
「綺麗ですね。おとぎ話に出てきそうな木を、そっくり持って来たのではないかと思ってしまいます」
「明かりがなかった昼間も綺麗だったけど、夜のもいいね」
穏やかな気持ちで眺めていると、蝋燭の時間がやって来た。
コタロウとベルティルデも小さな蝋燭台が付いた蝋燭をもらい、美しく輝く祝福の木の近くで祈りを捧げた。
(多くの加護を受けて『この場所』にいられることに感謝を。それから、マテオ・テーペのみんながどうか無事であるように)
コタロウは、目を閉じて海底の人達に思いを馳せた。
ゆっくり目を開けて隣のベルティルデを見ると、彼女もちょうど祈りを終えたところだった。
祝福の木の輝きを受けた彼女の横顔は、神秘的で儚く見えた。
「ベルティルデちゃん、今夜は楽しめた?」
「はい。とても楽しい一日でした。連れて来てくださってありがとうございます」
「それは良かった!」
楽しそうなベルティルデの微笑みに、コタロウは心底嬉しそうに笑った。
* * *
祝祭初日。
ナイト・ゲイルは、チェリア・ハルベルトを連れて、街に出ていた。
2人とも、こういった時期に街で遊んだ経験に乏しく、何をすればいいのかよく分からず……。
「まあ、見回りしながら飲み食いしたり、楽しそうなところ一緒に見て回ればいいだろ」
と、広場へと続く道を歩いていく。
「温かいものでも、飲むか」
チェリアがホットドリンクを提供している出店の列に並んだ時だった。
「兄ちゃん、兄ちゃん」
隣の露天の男性が、ナイトに声をかけてきた。
「連れの姉ちゃん、綺麗だね。プレゼントに如何?」
男性の露天は、手作りのアクセサリーを扱っている店だった。
「プレゼントか……」
贈り物なんて、沢山もらってそうだけれど。
こういう店で作られた、手作りのアクセサリーなんかは持ってないだろうなと思い、ナイトはチェリアに合いそうなものを探していく。
「ネックレスとかイヤリングとか指輪とかでいいのがあれば」
「こういうのもお勧めだよ」
男性が勧めたのは、ストールを留めるアクセサリーだった。
「あー、うんそうだな。上品そうなこれにするか」
ナイトは金色のリングを選んで購入し、そのまま受け取る。
そしてすぐ、並んでいるチェリアを探す。平然と並んでいる彼女の姿をみつけ、ほっとした。
(しかしアレだ、マテオの皆の事を何とかしないといけないのに、何で彼女の事ばかり気にしてるんだよ)
チェリアにしろ、レイザにしろ、ルースにしろ、自分を犠牲にし過ぎたと、ナイトは思っていた。
そういった宿命を背負って生まれてきたからこそ、楽しく幸せに暮らすべきだろうと。
マテオのこと……どちらかといえば、自分はルースの側で彼女の助けとなるべきなのだろうけれど。
(だけど、今の彼女を放っておくわけにはいかないだろう? だから……うん、一人にしておくときっと勝手に抱え込んで独りで何とかしようとしちゃうから)
彼女の状態を知る自分が、止められるだけの力を持つ自分が、傍にいないと駄目だと思った。
(守りたいものが一つ増えただけだ、大切な物が増えただけ……だけ、じゃないか)
ナイトはそう、自分に言い聞かせていた。
「待たせたな。緑茶で良かったか?」
ナイトの分も購入して、チェリアは戻ってきた。
ナイトが代金を払おうとすると、チェリアは不要だと笑い飛ばす。
「ちょっとそこに座らないか」
ちょうど空いた街路樹側のベンチに、並んでこしかけて。
「これ、似合いそうだったから」
ナイトはカップをベンチの上に置くと、チェリアのマフラーに手を伸ばす。
そして、さっき購入したアクセサリーを嵌めた。
「こういう日って贈り物をするもんなんだろ? 知らないけど」
「うん、そうだけど……唐突で、驚いた」
チェリアは茶を飲む手を止めて、ナイトが嵌めたアクササリーを眺めていた。
鎧を纏っておらず、鍛えられた身体も見えない装いの彼女は、ただの一人の貴族の品のある女性だった。
守る、という気持ちが、ナイトの中に膨れ上がっていく。
「あんたが嫌だというまでは傍に居る、だから遠慮するな。遠慮するされる程度の中じゃない、つもりだしな」
チェリアに拒否されるまで、傍にいようと思う……が。
(今更だが結構大胆な事言っている気がするな……)
チェリアはどんな反応をするだろうか。
ナイトは緊張を覚えていく。
でも、どんな反応をされても、思いは変わらない。
(独りで抱え込んでいる――ひとりぼっちの女の子を放っておけるか)
それすら守れず、何が騎士か!
ナイトの決意が籠められた強い眼に、チェリアの顔が僅かな不安を帯びる。
そして「ありがとう」と、彼女はどこか不安そうな笑みをみせた。
(これほど物語の舞台装置として最適なイベントを利用しない手はありません)
エリザベスこと、マーガレット・ヘイルシャムは、取材のために街に来ていた。
薔薇騎士物語の外伝として、聖なる夜の話でも書こうかと思っていたのだが、マーガレットは帝国の聖なる日を知らない。
帝国女子の趣向に合わない変な描写をいれてしまっては、読者を白けさせてしまうだろう。
といった本音を秘めつつ『帝国の民俗風習を知ることは私の執筆活動に必要なのです』などと、エルザナ・システィックに頼みこんで、祝祭で賑わう街を案内してもらうことにしたのだ。
「ということで、本日はよろしくお願いします、エルザナさん、いえ、先生」
「と言われても、一緒に遊ぶことくらいしかできないけどね。こちらこそよろしく」
「早速ですけれど、あれはなんですか?」
広場に到着したマーガレットが最初に気になったのは、矢を店に向けて、弓を構えている人達の姿。
「ああ、射的ね。品物や的に当てて、落すとその品物が手に入るの。公国でも行われていたでしょ?」
「公都にいた頃は健康上の理由でほとんど外出しなかったので、市井のこういうお祭りは実は初めてなのです。的に当てて、落せばよいのですね」
店に近づいて、マーガレットは射的に挑戦してみることに。
そして、エルザナに習い、なんとか矢を放つことに成功はしたのだが。
「……あ、当たらない……これあたらないですよ。エルザナさん」
当たらない、むしろ、的まで届かない。
「先生、ここは一つお手本を見せていただくわけには? 代金はこちらが持ちますので」
「私もこういうゲームはそんなに得意じゃないのよね」
そう言いながらも、エルザナは弓を構える。
(なんだか様になってますね。絵になります)
真剣な彼女の横顔は凛々しく、美しい。
何度か挑戦して、エルザナが射落としたのは3等賞と書かれた木札だった。
「やった、おに……陛下の像。似てるー」
彼女が受け取ったのは、皇帝の木彫りの像……。
「はい、これはサービスだよ。お姉ちゃんたち綺麗だから、大サービス」
射的を終えた後、店主は2人に小さな袋をくれた。中には沢山のキャンディーが入っている。
「ありがとー!」
「ありがとうございます」
お礼を言って、キャンディーが入った袋を手に提げて、2人は次の店へ歩き出す。
(帝国の文化は興味深い。美人だからこれはサービス、とかあったり)
エルザナと一緒に回ると色々得だなとマーガレットは思う。
自分一人では、射的にしろ、輪投げにしろ、景品を獲得することはできないだろうし、変な男性に絡まれるような気もする。
だけれど、エルザナはそういった誘いも、軽くあしらう術をもっていた。
(そして、この食べながら歩くという背徳的な試み)
次の店で買ったリンゴ飴を舐めるマーガレット。
「飴おいしい。ただ棒に突き刺されただけのリンゴの飴には思えませんね」
「うん、美味しい~。お祭りの雰囲気が、美味しくしてくれてるのよ」
「そうですね。マテオ・テーペにも、リンゴも飴もあったはずですのに、こんなに美味しいものは食べたことがありませんでした」
人も、食料も少なく、こんなに大きなお祭りがおこなわれることはなかったから。
マテオ・テーペに残る人々は、今も危機に瀕したままで、食事を楽しむことも満足にできていない。
自分だけこうして楽しんでいることに、マーガレットは罪悪感も感じていた。
「来年は皆で来れると良いですね」
そんなマーガレトの呟きは、エルザナの耳に届かなかったのか。
「ね、次はあれやってみよう、宝釣り!」
エルザナは答えずにマーガレットを引っ張るのだった。
『聖なる日には、会いに行くぜ』
使用人に手紙を託し、ウィリアムは、宮殿の部屋に籠っているアーリー・オサードにそう伝えてあった。
窓の鍵を開けておいてくれと。
まあ、傭兵騎士なので、堂々と訊ねる事も出来るわけだけど。
使用人に見られて、あらぬ噂でも立つと色々と拙いことが起きかねないから。
いや、寧ろ肉食系とはそういうものだと、噂話の影響を受けてたいたウィリアムは思い込んでいた。
そして、当日。
「よう」
苦労して窓から忍び込んだウィリアムが、アーリーの部屋に入った。
しかし仄かな明かりのついた窓際に彼女はいなかった。
「ってベッドの方か、もう寝てんじゃん」
そっと、近づいて、ベッド脇に腰かけた。
起こすのも悪いかなと、そのまま見ていると……目が合った。
「起きてんじゃん」
「随分遅かったのね」
咎めるような目で、アーリーがウィリアムを見つめる。
「無理させちまったか? アーリーも素直な方じゃないし、押し付けすぎたか?」
「何が?」
「いやまぁ、いつもと違うことしてみたんで、変に思うわな」
「そうじゃなくてね」
そこで2人の会話が途切れる。
ウィリアムはなけなしの金で買った安酒を、ドンとサイドテーブルに置いた。
「とりあえず飲んでみるか? お互い酒の力借りてもいいことが有るかもしれんしな」
ベッドから下りて、カップを用意すると、2人はベッドに並んで腰かけて、酒を飲み始めた。
薄暗い部屋の中、2人の会話が弾むこともなく、酒だけ減っていく。
次第に酔いが回り、ウィリアムはカップをテーブルに置くと、アーリーに身体を寄せた。
「いやー、女の子同士の会話で聞いたんだが、恋愛事の達人が居てな。エリザベス先生とやらが、恋愛の達人らしいんだ」
「エリザベス先生って……」
名前に聞き覚えでもあるのか、目を逸らすアーリー。
「こんな動きもあるんだってさ」
突然、ウィリアムがアーリーの腰に腕を回した。
アーリーもカップを置いて、何故か俯く。
「あとは、そうだな」
と、ウィリアムは彼女をベッドの上に倒して、彼女の細い腕を掴んで、見詰めた。
「色々と勉強になるらしいぞ」
アルコールのせいか、アーリーの顔は真っ赤に染まっていた。見つめ返す瞳は、どこか不安そうで。
「んー、嫌か?」
「そう、じゃなくて」
「そうじゃないなら、いいんじゃねぇの?」
「はっきり言って」
何をだろうか、とウィリアムは考える。
気持ちは伝わっているはずだ。こ、これ以上何を言えと!?
「どうして、なの。欲しいわけじゃないの?」
「欲しい? そういえば、贈り合ったりする日だっけな。アーリーはなんか欲しい物あるか? といっても、アーリーの立場上大抵のものは手に入るんだろうが」
「……馬鹿ッ!」
アーリーがウィリアムを押し返そうとする。が、ウィリアムは強い力で彼女を押さえつけていて、振りほどけない。
「好きだとか、愛してるとか、言いながら抱きしめてよ。誰かから聞いた話じゃなくて、勉強になるからとか、理由なんかつけないで、あなたの素直な気持ちで、言葉にして、そして動いて……」
切なげな眼で、アーリーはこう続けた。
「私が欲しいものは、あなた」
聖なる日の夜。
2人だけのこの部屋で何があったのかは――。
2人共覚えてなかった。飲み過ぎたせいで。
●祝賀2日目
「わー、すごい! 出店が出てるとは聞いてたけど、こんなにたくさんあるんだ!」
広場を囲むようにずらりと立ち並ぶ出店の多さに、アウロラ・メルクリアスは歓声を上げた。
内容も様々なそれらに、一緒に遊びに来たカサンドラ・ハルベルトも目を丸くしている。
アウロラが目を輝かせて言った。
「ねね、どこから行ってみようか?」
「たくさんあって……迷っちゃうね」
「ちょっと回ってみよう」
人混みに揉まれながら二人は出店を見て歩いた。
小柄な二人は途中で人の流れに流されながらも、出店の様子はちゃんとチェックしていった。
アウロラが、食べ物を売っている店を発見して声を上げた。
「見て。あそこのおいしそう!」
「串に刺したフルーツに、ジャムとかかけてる……の、かな」
「そうみたいだね。いくつか種類があるみたいだし、別々のにして分けっこしない?」
「うん……!」
見た目も綺麗なその品に、カサンドラも笑顔になった。
間近で見ると、本土でも庶民はあまり食べることのできないいろいろな果物があることがわかった。
トッピングも果物のジャムの他にほんのり甘いクリームや、何にでも合いそうな蜂蜜などがあり、自由に選べるのだという。
他の出店より少し値段は高めだが、とても人気の店だった。
後ろで待つ人達にせっつかれながら、二人は別々のものを買って列を離れた。
人混みから外れたところに落ち着き、半分こにして食べる。
「おいしいね……!」
「うん。それに、とっても新鮮!」
顔を見合わせ、笑い合った。
次は、射的の出店に寄った。
やる気満々のアウロラが、射的用のおもちゃの弓矢を手にした。
「ねね、何か欲しいのある? お姉さん頑張っちゃうよ~」
「えと……じゃあ、あそこのクッキー……いい?」
「任せて。……えいっ。──あ、外れた」
アウロラの目が真剣みを帯びる。
「今度こそ……よし! 当たった!」
しかし、景品をもらうには棚から落とすか倒すかしないとダメだ、と店の兄ちゃんが言った。
「むぅ……なら、もう一発!」
今度は見事命中の上、棚から落とすことに成功した。文句なしだ。
「はい、カサンドラちゃん。お姉さんからのプレゼント」
アウロラは、クッキーの包みをポンとカサンドラの手に置いた。
ありがとう、と言ったカサンドラは嬉しそうに手の中のクッキーを見ていた。
その後、腹持ちの良い物をいくつか買い込み、運良く空いているベンチを見つけて腰を下ろした。
「ふー、けっこうたくさん手に入れちゃったね。──ところでさ『聖なる日』って、どういう日なの? 周りの人達が話題にしてたから、お祭りみたいなのがあるっていうのはわかったんだけど、どういうお祭りなのかは全然知らないんだよね」
「……聖なる日は、救世主様がお生まれになった日なの」
カサンドラは、家庭教師から教わった伝説をアウロラに話して聞かせた。
「へぇ……そんな由来だったんだ。なら、今日はその聖人……精霊……に感謝するお祭りだったんだね」
「うん……それと、救世主様が助けてくださった命にも、感謝して……喜びを分かち合うの」
それから話題は他愛のないことに移り、買い込んだものや射的で当てたクッキーを食べてゆっくり過ごした。
そして最後に、占いのテントを訪ねた。
アウロラの希望で、今後のことを視てもらった結果は……。
──救いの鳥がはるか高くに見えます。呼び寄せることができれば、輝く未来を掴めるでしょう。
広場の出店には、手作りの小物やちょっとしたアクセサリーを売っている店もあった。
棚に並ぶそれらの中から、ヴォルク・ガムザトハノフは木彫りのペンダントトップと革紐を買い、ジスレーヌ・メイユールにプレゼントした。
「わぁっ、ありがとうございます! さっそくつけてみますね」
ジスレーヌは紙に包まれたそれらを手に取ると、革紐を通して身に着けよう……としたところで、なぜかヴォルクに止められた。
「俺がつけてやる」
その言葉に、ジスレーヌはとたんに頬を赤くした。
「えと、あの……あ、ありがとう……ございます」
おずおずと差し出されたペンダントを受け取り、ヴォルクはジスレーヌの後ろに回ると、丁寧に首にかけた。
繋ぎ目の留め具をとめて、ジスレーヌの顔を覗き込む。
「ぴったりだ」
「えへへ、大切にします」
ジスレーヌは赤い顔のまま、嬉しそうに微笑んだ。
たまたまそのやり取りを目撃した幼い男の子と女の子が、キャッキャと囃し立てた。
「みろ、かっぷるだぞ! いちゃいちゃしてるぞ!」
「きゃ~っ」
「ちゅーはしないのか?」
「えっちぃ~」
パチーン、女の子が男の子のほっぺを叩く。
ヴォルクとジスレーヌには二人の姿も声も人混みに埋もれてわからず、何も知らないまま次の出店へと移動した。
「ヴォルク君、あそこでおいしそうなもの売ってますよ。行ってみませんか?」
「よし、おごってやる」
人をかき分けるように進む途中、ジスレーヌがすれ違う人とぶつかってしまった。
「あっ、ごめんなさい」
「いや、こっちこそ……ん? なんだ、お前らも来てたのか」
ジスレーヌがぶつかった相手はマティアス・リングホルムだった。
「お前は一人なのか?」
ヴォルクの問いに、マティアスは頷く。
「姫さんと部屋でささやかなパーティしようと思ってさ。その買い出しと、祝福の木を見に来たんだ」
「そうか、いっぱい買ってってやれよ。それで思い切り楽しんで、最後はギュッとしてチュッとするんだ」
「ヴォルク君、何を言っているのですか! もう~、恥ずかしいですよ!」
先ほどの女の子ではないが、ジスレーヌの平手がパチーンとヴォルクに飛んだ。
マティアスは苦笑し、ごちそうさま、と言って去って行った。
「もう、変な人と思われてしまいますよ!」
「変な人じゃない。リア充だ」
ニヤリとしてかっこつけて言ったヴォルクに、ジスレーヌは思わず吹き出した。
「爆発しちゃうから、熱すぎはダメです。ジュースも買って少し冷えましょう」
いろいろと買い込んだ二人は、空いているベンチを見つけた。
座ってからようやく、ジスレーヌは少し疲れていたことに気が付いた。
ヴォルクはジャムを挟んだサンドパンを取り出すと一口大にちぎって、ジスレーヌの口元に差し出した。
「あーん」
と言うと、彼女の顔がみるみる赤くなり、耳まで達した。
目をキョロキョロさせて、すっかり挙動不審である。
そんな様子をステラ・ティフォーネに見られていたとも知らずに、二人は聖なる日を満喫したのだった。
「出店とかで焼き菓子と蝋燭をちょっと多めに手に入れて、ここで簡単なパーティでも開かないか?」
と、マティアス・リングホルムが提案すると、ルース・ツィーグラーはそれに賛成した。
そこで買い出しと祝福の木を見に出かけた先で、マティアスはヴォルクとジスレーヌに遭遇した。
狙っているのか無自覚なのかわからないが、仲の良さを見せつけられた。
二人の前を去ってからは、本来の目的を果たすため出店を見て回った。
特別な二日間というだけあり、庶民の日常にはあまり出てこない食材が使われた食べ物屋が数多く見られた。
「これとこれと……あとこれもな」
肉や魚を使ったサンドパンに、ナッツやハチミツのクッキー、焼き色が絶妙な厚みのあるビスケット。
さらにピクルスやオレンジピールの蜂蜜漬けなどを、いくつもの出店で買い込んだ。
「……っと、蝋燭忘れてた」
と、思い出したマティアスの目に、タイミング良く蝋燭を売る出店が飛び込んでくる。
その店の蝋燭は、植物や幾何学模様などが描かれた綺麗な蝋燭だった。
ルースが好みそうな柄のものを選び、多めに購入。
そうしたのは、部屋を少しでも街のように飾って灯せば綺麗かなと思ったからだ。
火を灯すのは、火属性のマティアスができる。
最後に置き物を売っている出店で、洒落た彫刻を見つけたのでそれを購入した。
買い物をすべて終えたマティアスは、祝福の木を目指す。
この木の周りは、もっとも多くの人が集まっている。
日中は宮殿のバルコニーから眺めてもほとんど視認できないが、夜になったらどうだろう。
光を点滅させる魔法具の輝きが見えるかもしれない。
それはなかなかに神秘的な眺めではないだろうか。
まだ日が差している今の祝福の木は、オーナメントに太陽光が反射してキラキラと輝き、明るい雰囲気を出している。
集まった人達はみんな笑顔だ。
祝福の木はいつまでも眺めていられそうだが、そうもいかない。
ルースが待っている。
帰りが遅いと文句の一つも飛んでくる……かもしれない。
(宮殿の中も慌ただしかったな。おいしいご馳走を食べられるかもな!)
何も出ないということはないだろう。
それならいったいどんなものが出てくるのか、マティアスは楽しみに思った。
祝福の木から離れ、広場を出る。
マティアスの足取りは軽い。
戻ったマティアスが持って来た品々にルースは目を丸くし、それから嬉しそうにした。
それから二人で部屋に蝋燭と彫刻を飾り、テーブルに屋台の食べ物を並べる。
手軽に作れる屋台料理であっても、特別な日のものはやはり特別おいしく感じられ、食が進んだ。
「夜はパーティよ。準備しておいてね」
どうやらマティアスの期待通りになりそうであった。
この日、一人で遊びに出る人もいないわけではない。
ステラ・ティフォーネもその一人だった。
彼女ははじめ神殿前のバザーを見て回り、それから広場のほうへ足を延ばし屋台を見物した。
途中、目を引くものがあれば買っていった。
そろそろ休もうかとベンチに腰掛け、これまでの戦利品の中から食べ物と飲み物を取り出す。
作り立てのそれらは、寒さで冷えた手をじんわりと温めてくれた。
少しずつ口にしながら、目の前を行き交う人達をのんびりと眺める。
家族連れもカップルも友人同士も、みんな楽しそうに笑っていて、その雰囲気はステラも楽しませた。
(この時間は身分問わず、すべて平等に与えられた時間ですね……)
広場は貴族も富裕層も貧しい者も集まりごった返している。
ところで、誰かを待っているふうでもなくベンチに一人で座り、屋台の食べ物を食べている美女──ステラは、けっこう注目されていた。
その中に声をかけようか迷っている独身男性が多数いる。
人が集まるこの祝祭は、男も女も出会いを求めてやって来る人も多いのだ。
そしてステラに興味を持ったあるいは一目惚れした男達は、ライバルの存在に気づくと視線で牽制しあい、さらに声をかける順番を決めた。
勇気ある最初の一人が行動に出ようとしたその時、ステラの横のベンチの年若いカップル(?)が、うらやましすぎるイチャつきを始めた。
それを見てしまった男達は敗北感に襲われ、一人また一人とその場を去って行ったのだった。
そんな悲劇などステラは知らないが、横のベンチの二人連れの顔はよく知っている。
微笑ましいやり取りに、思わず口元が緩む。
それと同時に、何とも言えない気持ちにもなった。
(何となく肩身が狭く感じるのは、気のせいでしょうか……)
横の二人以外にも、ぴったり寄り添って歩いたり、見つめ合っていたりというカップルを何組も見てきた。
そのたびに、独り身であることを突き付けられてきたのだった。
隙間風にも似た寂しさを振り払うように、ステラは立ち上がった。
手早く戦利品をまとめて、祝福の木へ向かう。
器用に人々の間を縫って、綺麗に飾り付けられた木がよく見える位置で足を止めた。
(早く相手を見つけないといけませんわね。来年はお相手がいますように……)
祝福の木は、ステラの未来を寿ぐようにきらめいていた。
イベント特需、などと表現したら伝説の救世主はどんな顔をするだろうか。
しかし現実を生きるリキュール・ラミルにとって、祝祭日の二日間は大事なかき入れ時であった。
注文品の卸がすべて終わり、ホッと一息つく。
が、これで仕事が終わったわけではない。
彼はプレゼントが詰まった大袋を担ぎ、まだまだ人で賑わう夜の広場へ足を運んだ。
立ち並ぶ出店にはリキュールのポワソン商会と取り引きのある店も多く、その内の一店ハオマ亭の出店に立ち寄った。
ポワソン商会から果物を仕入れたハオマ亭は、形よく切った果物を串に刺してジャムなどをかけて売っていた。
出店を仕切っているのは看板娘のパルミラ・ガランテだ。
客が途切れたタイミングでリキュールが顔を出すと、パルミラが笑顔で出迎えた。
「こんにちは、リキュールさん! 果物、とっても新鮮で大好評なんですよ。ありがとうございました!」
「商品に責任を持つのは当然でございます。今後もどうぞご贔屓に」
商人らしい挨拶にパルミラはクスッと笑い、串に刺したリンゴにハチミツをかけた一本を差し出した。
「一番人気のものです。食べてみてください」
「おや、先手を打たれましたな。手前もプレゼントを持参したのでございますよ」
大袋から取り出して渡すと、パルミラはパッと表情を明るくした。
「わぁっ、ありがとうございます! そういえば、あの蒸留酒はどうなりました?」
「おかげさまで。飲食店のいくつかから注文をいただくことができました」
ほくほく顔で言ったリキュールに、パルミラもにっこりした。
再び客の流れが戻ってきたため、リキュールは店を後にした。
その後もいくつか出店に顔を出してプレゼントを渡し、最後に訪ねたのはパルトゥーシュ商会の出店だった。
ここでは子供向けのおもちゃを売っていた。
会長のフランシス・パルトゥーシュも来ていて、リキュールを見るなり「よぅ」と気さくに手を上げた。
そして彼の表情を見て「ほぅ」と息を吐きニヤリとする。
「その顔は、そうとう儲けたな?」
「いえいえ、とんでもございません」
「ははっ。それはともかく、この二日間は大きなトラブルもなくて良かったよ」
「その通りでございますね。どのお顔も晴れやかで。そういえば、こちらでは子供向けのおもちゃを扱っているのでしたな」
「ああ。積み木とかお散歩ワンコとかな。兵器もいいが、こういった他愛ないものもいいな。それとな……」
と、フランシスは急に声を潜めて、リキュールにもっと近くに寄るよう手招きした。
「大人向けの……ゴニョゴニョ」
「なんと」
「あははっ。騎士団やスヴェルの奴らには内緒な!」
と、口止め料替わりにフランシスはワインを一本プレゼントした。
「仕方ありません、聞かなかったことにいたしましょう……。これは手前からでございます」
リキュールもフランシスにプレゼントを渡した。
「ありがとう!」
嬉しそうなフランシスにリキュールも目を細くした。
ポワソン商会の家訓に『儲けを溜め込まず、世間に還元すべし』という一文がある。
それを忠実に守り疲れた体を押して取り引き先を訪ね歩き、明日の商機を招いてくれと願う。
けれど、そのさらに根底にあるものは、プレゼントを贈った相手に喜んでもらえることの嬉しさだ。
願わくば『聖なる日』の祝福があらんことを──。
リキュールは心の中でそう祈った。
日が暮れて祝福の木がキラキラと点滅し始める頃、ルティア・ダズンフラワーの両手には大きな買い物袋がいくつもぶら下がっていた。
「付き合わせてしまってすみません。それに、荷物まで持っていただいて……」
ルティアは隣のグレアム・ハルベルトを申し訳なさそうに見て言った。
「いえいえ。うちの分も選んでいただいて、助かりました」
答えたグレアムも大きな袋を抱えていた。
彼らが持つ袋の中には、家族や家で働く者達への贈り物がたっぷり詰まっている。
最初は二人とも家族の分だけのつもりだった。
ところが途中でルティアの脳裏に家で働く人達の顔が次々と浮かび、彼らの分も買うことにしたのだ。
グレアムもその影響を受け、ルティアにアドバイスをもらいながらプレゼントを選んだ。
そして気づけば両手いっぱいになっていたのである。
二人共鍛えているとはいえさすがに腕が痛くなり、空いているベンチを探した。
見つけたベンチに荷物を下ろし、ルティアは改めて広場の賑わいを見渡した。
帝国にはこんなに人がいたのかと驚いてしまうくらい、たくさんの人であふれている。
活気に満ちた様子に、彼女の口元に笑みが浮かんだ。
「本当に、今日は素晴らしい賑わいですね」
「ええ。見ているだけで楽しくなってきます。これからも、この国の人達の平穏を守っていきたいと……あ、すみません。仕事の話なんて無粋でした」
ルティアはクスクス笑うと、袋の中からリボンで飾り付けられた箱を一つ取り出した。
「グレアム様、いつもありがとうございます」
感謝を込めて差し出すと、グレアムは驚きと喜びの表情でそれを受け取った。
「ありがとうございます。俺からも、これを」
グレアムもルティアに箱に入れられた贈り物を渡した。
二人で中身を開け、微笑む。
ルティアからは木彫りのスノーマンのブローチで、グレアムはさっそく身に着けた。
「大切にしますね」
グレアムは、そっとブローチを指先で撫でた。
ルティアへは二羽の兎のガラスの置き物だった。
手のひらに乗せると、周囲の明かりを反射してキラキラと輝いて見える。
「綺麗……ありがとうございます」
それから少しすると蝋燭の時間がやって来た。
商店街の人達が、手の中に収まるくらいの小さな蝋燭台が付いた蝋燭を配り、火を灯していく。
広場は小さくても温かな色の明かりでいっぱいになった。
ルティアは手元の灯から隣のグレアムの灯り、そしてその灯りを見つめる彼の横顔へと目線を移していった。
彼女の胸に、スヴェルに所属してから知ったことや感じた多くのことが去来した。
自分の生は、実に多くの人々に支えられていた。
商人、物を作る職人、農家、未来を担う子ら……皆、かけがえのない人達である。
(この皆の平穏を守りたい)
偶然にも先ほどグレアムが口にしたことと同じことを、ルティアは強く思っていた。
その時、不意にこの広場に満ちる大きな祈りを感じた。
集まった人達の手の中の小さな灯りが一つ一つ合わさり、不思議な一体感を生み出しているようだった。
(皆それぞれに大切な人と、祈りを捧げているのですね……)
ルティアにとって大切な人はグレアムだ。
そのグレアムと、この時間を共に過ごせた今日はとても嬉しい一日であった。
* * *
赤や緑、金色のオーナメントで彩られたバザー会場は、沢山の人々で賑わっていた。
アトラ島から訪れたタウラス・ルワールと、レイニ・ルワールは主にアクセサリーを扱っている店を見て回っている。
「これがいいんじゃない?」
レイニが手に取ったのは、深い紫色のリボン。タウラスの髪を結ぶためのものだ。
「それでは、レイニさんにはこちらを」
同じ色のイヤリングを選んで、タウラスはレイニにプレゼント。
「早速つけてみようか。あ、ううん。夜、部屋に戻ってから付け合うとかも、なんかいいわよね。こういう日だし」
なんて、一緒に過ごす夜を妄想しながら、レイニが幸せそうに言ったその時。
「ルワールくんらぁ~楽しんでる?」
顔を赤く染めた女性――メリッサ・ガードナーが、フェネックを腕の中に抱き締めながら、ニコニコ笑顔を向けている。
「わんわん」
フェネックはメリッサと似たケープを纏い、メリッサの胸に抱かれ気持ち良さそうにしていた。
「なんかおいしそうなものとか~キレイなものあった~? 奥さんがキレイってノロケはいらないからね~」
ふわふわ、心地良さ気な笑顔を浮かべているメリッサ。
彼女の手の中にあるのは、良い香りのする液体の入ったカップ。
「ホットワインですね……」
中身を確認して、タウラスは軽く苦笑した。
レイニの顔からも笑みが消えており、不思議そうにメリッサを見ている。
「はじめまして~メリッサでーす」
にこっと、メリッサはレイニに笑いかける。
「妻のレイニです。主人の……オトモダチかしら?」
昼間っから酔っぱらってるメリッサに、レイニは既に疑惑の目を向けていた。
「ルワールくんとは……ん~? なんだろ~? 友達らけどぉ……もうちょっと違うってゆーか……あ! 元婚約者のほうがインパクトあるかな!」
「……ああそうですか。この人も酒癖が悪くて、過去の事はとやかく言うつもりはありませんので、今宵はお2人で昔話でも楽しまれては?」
真顔でそう言って、立ち去ろうとるレイニの腕に、タウラスは「ちゃんと説明します」と、自分の腕をからめて引き止める。
「誤解を招くことは言わない約束でしたよね?」
「あとねあとね、これおいしいよ~おかわりしちゃったぁ」
「おかわり……それでそんなに上機嫌なんですね」
タウラスはやれやれという表情で、ため息をつく。
「ん? ホットワインってノンアルじゃないの?」
「温めることで度数は下がりますがゼロではないですよ。おかわりはそれで最後にしてくださいね」
「わかった!」
と、メリッサは残っていたホットワインを飲み干す。
「メリッサさんを独りにするのは心配ですし、蝋燭の時間までゆっくり話して過ごしましょうか?」
不機嫌そうなレイニに、タウラスはメリッサは旧友で恋愛関係にはなかったことを説明をした。
「……そうですよね?」
タウラスがメリッサに訊ねると、うんうんとメリッサは楽しそうに返事をして、にこおっと笑う。
「昔のルワールくんのお話、もっとしちゃう~?」
「誤解を招く発言以外なら、いくらでも」
そう釘をさして、タウラスはレイニに彼女を紹介をしながら、歩きはじめた。
「俺にハーブのことを教えてくれたのは彼女なんですよ。おかげであなたに美味しいお茶が淹れられます」
「あっ、あそこで温かいコーヒー売ってる~大人の味だって~ルワールくんたちのぶんも、買ってくるよ~」
ふわふわな足取りで走りだしそうなメリッサの腕をぎゅっと掴んでタウラスは止める。
「ウイスキー入りのコーヒーのようです。やっぱり放っておけませんね」
タウラスがレイニを見ると仕方なさそうに、レイニは頷いた。
メリッサとタウラスの関係を疑っているわけではないようだが、レイニはメリッサをあまり快く思ってなさそうだった。
「ふたりはわりに似ていると思います。レイニさんもそこまでお酒は強くないですし、自分を磨いたり鍛えることも好きですよね?」
メリッサを見守りながら言うタウラスの言葉に、「そうかしら?」とレイニは答える。
魔力と体力に秀で、その他は著しく劣るメリッサと、魅力に溢れ、交友関係が豊かなレイニ。整った外見を除き、対照的に見える2人だけれど、2人を良く知るタウラスは、似た部分を感じ取っていた。
(猪突猛進気味なところも似ているけれど、言わないでおこう……)
それは心に秘めておく。
レイニとしてはタウラスとの貴重な2人きりの時間を過去の女(友人だとしても!)に邪魔されたくなかったという気持ちをどうしても抱いてしまっていたけれど。
でも、せっかくこんな日に、彼の大切な友に会えたのだから――。
「その仔可愛いわね。私にも抱かせてくれる?」
「うん、とってもとっても可愛いの~懐くかな~」
近づいてきたレイニに、メリッサがフェネックを向けると、フェネックは嬉しそうにレイニに飛びついていった。
「あ……懐いてる。すごい簡単に~。なんで~」
「ふふふ、よしよし」
そして、2人でフェネックを撫でながら、並んで笑顔で歩き出す。
和やかに話しだす2人を、タウラスは後方から穏やかに見守り、歩いていくのだった。
「見て、どっかの国のお菓子だって。魚の形の焼きパン? あれ食べたい! 魚より食べたい!」
フェネックの飼い主の一人であるアールも、バルバロに誘われてバザーに来ていた。
彼女達海賊は、長い間海で過ごしていたため、菓子類などは殆ど口にすることが出来ていなかった。
「まだそっち食い終わってねぇだろ」
人混みをかき分けて屋台に進んでいくアールの手を、バルバロは急いで掴んだ。
逸れないようにと、手を繋いでいた2人だが、買ったものを食べようとちょっとの間手を離した隙に、アールはどこかに飛んで行ってしまう。
(一瞬たりとも目を離せねぇ、まるでガキのようだ)
などと思いつつも、そんなアールを可愛く思う。
(考えてみりゃあ、私はアールのことを何も知らない……何が好きか嫌いか、何を喜んで何を悲しむか、何も、何一つ……)
普段のアールは、明るくて元気な娘だった。だけれど、記憶を失っているせいか、表情を曇らせ、指輪を握りしめながらどこか遠くを見ていることもある。
(もっと、アールのこと知りてぇな……そうすりゃもっと、アールを笑顔にできるんじゃねぇかな……)
バルバロはアールのことを大切に想っていた。
自覚をしてから、その気持ちは膨れるばかりで――この感情が、どういった意味での大切なのかは、まだ分からないけれど。
ただ、自分では感情を抑えられないくらい、どうしようもなく『大切』になっていた。
「ほら、座って食うぞ。海の様子を見る必要もねぇしな」
温かな焼きパンを手に嬉しそうにしているアールを、バルバロはベンチに引っ張った。
「うん。……あちちっ、中のクリーム熱すぎー!」
「気を付けて食え……あちゃっ! はふ、ふ」
アールに気を取られながら焼きパンを食べたバルバロも、熱さに驚き、慌てて冷たい飲み物を飲んだ。
「あはははは」
「ふ、ははははは」
そして、2人は顔を合わせて笑い合う。
思い切り笑ったあとで――。
「……悪ぃ。メリッサ達への土産、忘れちまった。ちょっと買ってくるから、食いながら待っててくれ」
そういって、バルバロは立ち上がった。
「待って……られるよな?」
歩きかけたバルバロだが、ふと不安に駆られて振り向く。
「うん、待ってるよ。ちゃんと戻ってきてよね」
「ああ、すぐ戻ってくるからな、動くなよ」
そう言い残して、バルバロは人混みを突っ切って、目星をつけていた店に急いだ。
数分後。
バルバロが戻ると、アールはベンチに座っていたカップルたちと仲良くなり、くだらない話で笑い合っていた。
「あー、バルバロ。ちゃんと戻ってこれたんだね、えらいえらい」
などと言いながら、立ち上がったアール――そんな彼女を包み込むように、ふわりと。
「ん?」
「……寒いだろ。やるよ」
バルバロは青いショールをアールの肩にかけた。
それはアールが先ほど、目に留めていたものだ。
「あ、ありがと……」
礼を言われたバルバロは、照れ隠しのように顔を逸らして、一方を指差す。
「甘いもんばっかじゃなくて、そろそろメシにしねぇか? 祝祭限定の料理もあるってよ。行ってみようぜ」
そういうバルバロに、体当たりをするように、アールが飛びついてきて。
「うん、行こう!」
腕に腕を絡め、ぐいっと引っ張って満面の笑顔で歩き出すのだった。
2日目の夜になっても、広場は人々で賑わっていた。
祝福の木に飾り付けられた魔法具が小さな光を放ち、輝いている――。
「ああ、祝福の木はとても美しいですね」
キラキラ輝く祝福の木に近づきながら、アレクセイ・アイヒマンは感嘆の声を漏らした。
「是非チェリア様とこの光景を見たかったので、一緒に来れて嬉しいです」
アレクセイは隣を歩くチェリア・ハルベルトに目を向けて、見詰める。
祝福の木を眺めるチェリアに、色とりどりの小さな光が降り注いでいる。
彼女の神秘的で端麗な横顔に、アレクセイは見惚れてしまう。
「チェリア様は俺を幸せにする天才です」
彼のそんな呟きが耳に届いたのか、チェリアがアレクセイに顔を向けた。
「……アレクセイは時々、反応に困ることを言うよな」
チェリアはなんだか少し、恥ずかしげな笑みを浮かべた。
「さあ、折角ですから屋台を見て回りましょう」
アレクセイは屋台の方に手を向けて、チェリアと共に歩き出す。
ただこの時間、屋台には多くの人が集まっていて、長蛇の列ができていた。
「凄い人ですね……逸れないか心配です」
少し迷いながらアレクセイは、チェリアが自分の横に並ぶのを待って。
勇気を出して、彼女の手を取った。
「これなら、温かいですし逸れないで済みますね」
軽く照れながら微笑みかけると、チェリアは戸惑いのような表情を浮かべてアレクセイを見詰めたあと、ふっと表情を崩した。
「さあ、何を食べましょうか」
アレクセイはニコニコ笑顔で、チェリアに問いかける。
「綿菓子」
彼の笑みを見ながら、チェリアが答えた。
「お好きなのですか?」
「アレクセイと一緒だから。こういうの、私にはあまり合わないから、さ」
綿菓子や、子どもや女の子達が好みそうな屋台に、チェリアはアレクセイを誘う。
彼女の家は格式が高く、子どもの頃、こういった屋台に来ることはなかったようだ。
ただ甘いだけの砂糖菓子や、果実に蜂蜜をつけただけの、シンプルなお菓子をチェリアは好んで選び、食べていた。
「射的がありますよ。チェリア様、一つ勝負しませんか?」
射的の屋台を見つけて、アレクセイはチェリアを誘った。
そして、一つだけを狙い、全身全霊を込めて射落す。
「チェリア様、お手をどうぞ」
手に入れてすぐ、アレクセイはチェリアに手を向けた。
不思議そうに、チェリアは右手を彼の手の上に差し出した。
彼女の右手の薬指に、アレクセイは青い石のついた指輪をはめる。
「ふふ、似合うか?」
青い石で飾られた指を、チェリアは自分の顔の位置に持ってきて、アレクセイに見せる。
「わあ……やっぱり凄く似合う……!」
歓喜して、アレクセイは満面の笑みを浮かべた。
「玩具で申し訳ないですが……」
「本物だったら受け取るわけにはいかないし……ありがとう。アレクセイにはこれを」
チェリアは自らが射落した可愛くて大きな熊のぬいぐるみを、アレクセイに持たせた。
そして、蝋燭を持ち感謝をささげる時間が訪れた。
チェリアのことを沢山知ることができ、部下として共にいることが出来ていて、今、こうして隣に居るそのことに、アレクセイは深く感謝をする。
(ありがとうございます。チェリア様が健やかに笑顔で過ごせますように)
これからもチェリアの近くに居られますように――と。
少しの静かな時間を過ごしてから、アレクセイはチェリアを見詰めて尋ねる。
「チェリア様は何に感謝を捧げましたか?」
「今、こうして感謝をささげることができていることを。共に感謝をささげる人々が居ることを。アレクセイは?」
「私は……チェリア様と今こうして過ごせる時間に感謝を捧げました」
そう、アレクセイが言うと。
チェリアは少し照れて微笑を浮かべ、「ありがとう」とアレクセイに感謝をした。
☆ ☆ ☆
二人の男女が、静けさに包まれた道を歩いていた。
神殿主催のバザーも終わった夜更け。いまだ賑わう広場からも少し外れたところ。
多くの人が集まる広場から少し離れてしまえば、逆に辺りはいつもよりも静かなくらいだった。
「たまには、こんな風に静かなのもいいだろ? 二人きりなのも、久しぶりだ」
二人のうち女性の方――ヴィーダ・ナ・パリドが、隣にいるセゥに優しく声を掛ける。
そしてゆっくりと、そっと手を重ね合わせ――繋ぐ。傍から見ている者がもし居たとしたら、自然な流れのように見えたかもしれない。しかし、本人からすれば普段はなかなかできないことだった。
それでも聖なる日だから、特別な日だから、そして周りに人気が無いからこそ、いつもより積極的になれている気がする。
「ああ、なんだかこう……良い夜だ」
敢えて手をつないだことには触れずに、セゥもつぶやくように言葉を発した。その言葉が闇夜にゆっくりと消えていく。
少しの間、沈黙が続く。二人はゆっくりと歩き続ける。
「聖なる日、特別な日……。セゥとこんな風にいられるのは、まぁ……その、幸せだって思うよ……。それに、いつもより……カッコいいぞ」
一つ一つ紡ぎだすように、ヴィーダは口を開いた。自分では柄ではないと思っているそんな台詞を口にするごとに、顔が赤くなっていくのを感じる。
そう今日はこの地域での聖なる日ということで、自分たちなりにいつもとは違う服を着ていたのだった。セゥも正式な儀式の際の服とまではいかないが、いつもよりしっかりした生地の服を身に着けている。
「ヴィーダも、綺麗だ……いつも以上に」
もちろん、それはヴィーダも同じ。それを分かった上での「いつも以上に」という言葉が嬉しかった。それは即ち――いつも、そう思っているということだから。
心なしか顔が赤くなっているのも、握りしめられた手に込められる力が少しだけ強くなったのもまた、嬉しかった。
しばらくどこへ行くでもなく散歩を楽しんだ二人は、やがて街を見下ろせる高台にたどり着く。
折しも時刻は、現地の者たちから聞いていた、感謝の祈りを捧げる頃になっていた。
ヴィーダは祈りを捧げる。
全ての命に感謝を伝える。今、生きている人達だけでなく犠牲になった人達も含めた、多くの命に感謝を伝える。
そして過去の儀式のことを思い出す――命は全て、本当はもっと尊ばれるべきだったのに。
それから、大切な親友シャナと。
今も隣にいてくれる大事な人、セゥの存在に感謝する。
そうやって思いを馳せている間に、堪えられなくなってくる。
「セゥ、セゥ。何度でも名前を呼ぶからな。お前は、俺のところに戻ってくるんだ。俺も、お前の腕の中に帰るから」
祈りを終えたヴィーダは、セゥを抱きしめてそう告げていた。
セゥは、躊躇いもなく抱きしめ返してくれた。
誰もいないこの場所で、二人は時が止まっているかのようにしばらく抱きしめあう。
「は、早くシャナにも恋人が出来たらいいのにな。あ、もしかして嫉妬したりするのか?」
急に恥ずかしさが込み上げてきて離れたヴィーダは、誤魔化すようにセゥに声を掛ける。
それを分かってか分からずか、彼は微笑みながらゆっくりと首を振るのだった。
●担当者コメント
こんにちは、冷泉みのりです。
リアクションの一部を担当いたしました。
聖なる日シナリオへのご参加、ありがとうございました。
波乱続きのPC方にとって、少しでも良い思い出になれたら嬉しく思います。
それとPLの皆さんへ、良いお年を!
川岸満里亜です。
クリスマスシナリオへのご参加ありがとうございました!
慌ただしい時期の公開になってしまいすみません。
川岸は初日の***から初日ラストまでと、2日目の***から☆☆☆までを書かせていただきました。
☆☆☆以下は鈴鹿高丸マスターが担当しました。
今年も大変お世話になりまして、ありがとうございました。
引き続き、イベシナは楽しく描かせていただきたいと思います。
来年もどうぞよろしくお願いいたします
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から